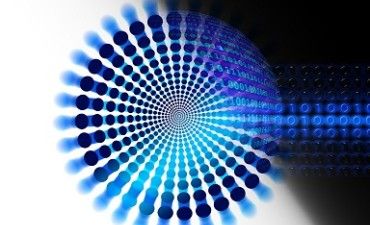「データ分析をやれ!」と言われたら、あなたならどうするでしょうか。多くの人は、分析手法の知識や分析ツールの使い方を習得しようとします。データ分析をするのだから、当然と言えば当然です。しかしそれだけでは、ビジネス実務でデータ活用し成果を出すことは難しいことでしょう。どのくらい難しいのかというと、「高校や大学などの高等教育で得たことを、実社会で活用し社会貢献するぐらい」の難しさです。これは多くの人が経験する「データ分析に立ちはだかる実践・活用の壁」です。今回は「学んだこと、活かせていますか?」というお話しをします。
【目次】
1. どのようなデータで、どのように分析をすればいいの?
2. 料理で例えると……
3. 知識を得、知っただけでは実践は難しい
4. 見習い期間が必要
5.「データとの格闘」と「人との格闘」
6. 活用イメージを持てるかどうか
7. OJT(On-the-Job Training)が必要
8. 再現トレーニング
9. 過去のプロジェクトの報告書を読むだけで十分か?
10. 写経で十分
11. キャリア採用か外注するか
【この連載の前回:(その287)実務で使える5つの数理モデル へのリンク】
1. どのようなデータで、どのように分析をすればいいの?
私は20年以上、データ分析の世界に身を置いています。ここ10年、情報爆発やビッグデータなどのキーワードと共に、データ分析に興味をもつ人が増えました。増えたのはいいのですが、私は次のような質問を、まさにここ10年よくされます。
「どのようなデータで、どのように分析をすればいいの?」
このように質問する気持ちも分かります。しかし、このような質問が一番困ります。なぜならば、なんて答えればいいのか分からないからです。
2. 料理で例えると……
データ分析は、よく「料理」に例えられます。データが「食材」で、分析が「調理」で、分析ツールが「調理器具」です。料理の場合、次のような質問になります。
「どのような食材で、どのように調理をすればいいの?」
このような質問を、プロの料理人にしても、その料理人は困ってしますことでしょう。なぜでしょうか。理由は簡単で、何の料理のことを指しているのか分からないからです。カレーライスのことを指しているのか、ハンバーグのことを指しているのか、チンジャオロースーのことを指しているのかで、当然ながら食材も調理法も変わってきます。例えば、「4歳の牛乳アレルギーと小麦アレルギーのある男の子でも美味しく食べられるカレーライス」とでも言ってもらえれば、答えようがあります。
3. 知識を得、知っただけでは実践は難しい
分析手法の知識や分析ツールの使い方を習得することは、料理で例えると、料理法の知識と調理器具の使い方を習得したに過ぎません。料理法の知識と調理器具の使い方を習得しただけで、お店に出せるぐらいおいしい料理を作れと言うのは無茶苦茶な話しです。先輩の指導のもと、現場での見習い期間が必要でしょう。
同様に、データ分析の手法の知識や分析ツールの使い方を習得しただけで、社内の「お困りごと」であるビジネス課題を解決し、ビジネス成果を出せというのは無茶苦茶な話しです。
4. 見習い期間が必要
先輩の指導のもと、現場での見習い期間が必要でしょう。要するに、知識を得、使い方を知っただけでは、ビジネスの実務でのデータ分析・活用の実践は難しいのです。ここで言うと実践とは、単にデータ分析をしてみました、ということではありません。
データ分析・活用の結果、例えばビジネスプロセスが何かしら効率化したり変革が起こったりし、売上アップやコストカットなどの利益変動が起こった、ということを指します。
5. 「データとの格闘」と「人との格闘」
では、データ分析の手法の知識や分析ツールの使い方を習得すること以外で、何が必要なのでしょうか。ビジネスの現場でデータ分析・活用をするとき、データを集計したり分析したり、数理モデルを構築するといった「データと格闘すること」よりも、関係者に説明したり現場と議論をするといった「人と格闘すること」が重要になることが多いです。そのあたりの習得が、先輩の指導などが必要になります。苦手な場合は、得意な人と組み必要がでてきます。
6. 活用イメージを持てるかどうか
「データとの格闘」と「人との格闘」の中でキーになるものとして「活用イメージ」というものがあります。文字通り、データを現場で活用するイメージです。このイメージを持ってデータを格闘できるかどうかは非常に重要です。このイメージは現場を知る努力なくしてはあり得ません。しかし、現場に精通しているからといって、データを現場で活用するイメージを持てるわけでもありません。
このイメージを想像する力が必要です。要するに、データ分析の手法の知識や分析ツールの使い方を知っていても「活用のイメージを持てるほどの想像力」が足りていない場合、ビジネス成果を出すのが非常に難しいです。
7. OJT(On-the-Job Training)が必要
この「活用のイメージ」を持てるようになるには、多くの場合、実務経験が必要です。先輩の指導のもと、現場での見習い期間が必要です。端的に言うと、OJT(On-the-Job Training)が必要です。OJTとは、職場で実務をさせる職業教育・訓練法の1つで、実務を通じて知識やスキルなどを身に着けさせようとするものです。
OJTには、当然ながらデータ分析でビジネス成果を出し続けているプロが必要になります。昔からデータ分析・活用の盛んな会社や部署であれば、そのようなプロがいるため、OJTの仕組みさえ構築できれば問題ないかもしれません。しかし、そのようなプロが身近にいない場合もあります。
OJTの仕組みがまだない場合もあります。そうでない場合、どうすればいいのでしょうか。データ分析・活用のイメージを含まらせるトレーニング法は、OJT以外にはないのでしょうか。
8. 再現トレーニング
私が20代のころ実践したやり方があります。それは、過去のデータ分析プロジェクトを、再現するという「再現トレーニング」です。報告書などに沿って一からデータを整備し集計し分析しモデル構築などを実施し、再現していきます。
このとき、報告書も一から自分で作成し再現します。一つ一つ丁寧に再現していきます。もちろん、報告書のコメントの一字一句再現していきます。これは、OJTだけでは物足りなかった私が実践した方法です。OJTで経験できるプロジェクト数には限りがあります。より多くの経験値を積むために実施しました。
9. 過去のプロジェクトの報告書を読むだけで十分か?
もしかしたら「過去のプロジェクトの報告書を読むだけで十分ではないのか」と、思った方もいたかもしれません。私も最初、そのように思いました。しかし、報告書を読むだけでは、表面をなぞっただけで、具体的なイメージを含まらせることはできませんでした。この再現トレーニングのポイントは「この部分は再現しなくてもいいだろう」と思い端折らないことです。例えば、データ整備も端折らない、グラフ作成も端折らない、レポートのコメントも端折らない、という感じです。
10. 写経で十分
当時の私が得たかったのは「もし仮に、明日同じようなプロジェクトが始まったとき、具体的にどのように手を動かせばいいのかが見える」というレベルのスキルです。写経に過ぎないと思われるかもしれませんが、そこから得られるものは非常に多く、単に過去のプロジェクトの報告書資料を読むだけでは得られないものが、手を動かして再現することで得られます。
例えば、なぜこのような分析を実施した...
要するに、報告資料を読むだけでは得られなかった「意図」を垣間見ることができたのです。
11. キャリア採用か外注するか
しかし、データ分析・活用の盛んな会社や部署でない場合、その道のプロがいないだけでなく、過去のデータ分析を活用したプロジェクトが十分でないケースも多いでしょう。そのような場合、経験者をキャリア採用(中途採用)するか、社内のデータ分析プロジェクトを外注し、その過程を事細かに残し後で再現できるようにしておくことでしょう。ただ、社内に理解者や強烈にバックアップしてくれるエライ人がいないと、思うようにはいかないと思います。
最初は、必ず成果のでそうなテーマを選び、意地でもビジネス成果をだし、それを教材化し、社内に「得た成果」と「これから得られるであろう成果」をプレゼンしつつ、個々人のレベルアップする道筋も併せてプレゼンし普及活動すると、いいのではないかと思います。