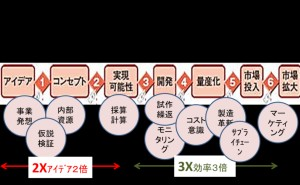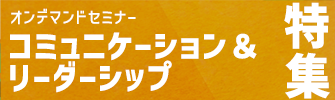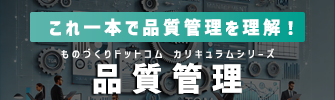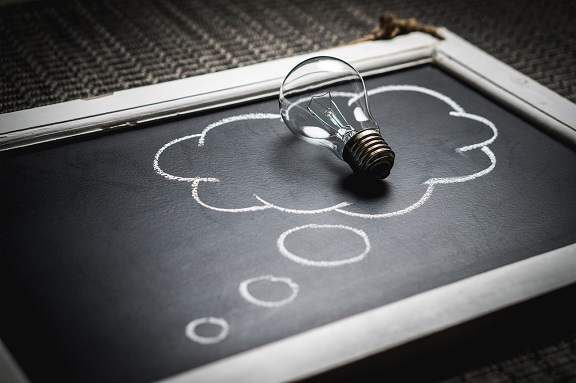
▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
こんな経験ありませんか?
- 「あの案件、先に手をつけておけば良かったのに…」
- 「もっと早く導入しておけば、あんなに手間取らなかったのに…」
そう、“行動すれば良いと分かっているのに、動かない”。これ、実は意思が弱いわけじゃないんです。むしろ人間らしい証拠とも言えます。なぜ人は動けないのか?
- 「わかっちゃいるけど、動けない」
人はなぜ行動を後回しにするのか?今回は、そんな時の意識の保ち方についておはなしします。「行動できない理由」を知れば、あなたはもっと動けるようになります。
1. 変化よりも安心が好きな「現状維持バイアス」
人間は、本能的に「変化」を嫌います。なぜなら変化は不安やリスクを伴うからです。例えば、今の仕事が効率悪くて辛くても「なんだかんだで慣れてるし」と思ってしまう。いわば「不便だけどこの椅子座り慣れてるし、立ち上がるの面倒だな」状態です。でも、ちょっと考えてみてください。座り慣れたその椅子、実はボロボロで、いずれ壊れるかもしれないのです。早め...