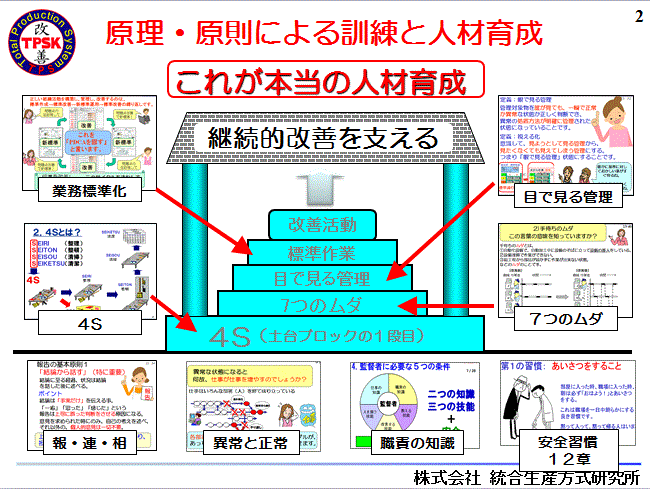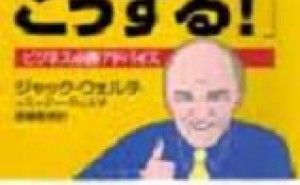1、海外出向先での悪魔のサイクル
海外に出向して現地人との関係が何故「悪魔のサイクル」になってしまうのでしょう?まずこの点について説明します。
会社への帰属意識が低く、個人主義が徹底している国々では、業務上のミスはその人個人のミスという意識が非常に強く、責任を何とか回避しようという基本的思考の上に仕事が乗っているため、グループやチームで仕事を進めようとする我々日本人とは基本的に考え方が異なり、そこに心理的な齟齬が最初に発生します。
日本では「じんざい」を「人材」と書き、この「材」を企業としての「財」に変えようと、各種教育・訓練やジョブローテーションを行い長期に渡って育てようとします。しかし海外では即戦力の「人才」を必要とし、本人達にも何々の専門で仕事をしているという発想が根本にあります。従って専門的な知識の吸収意欲は非常に高いものがありますが、それ以外は殆ど興味を示さず、日本式の「多能工化」などと言って職場を変えたりすると、途端に抵抗したり辞職したりします。
従来日本企業が行ってきた、個人を責めずに仕組みを責めるという考え方は非常に理解しにくいのです。その事を前提に「悪魔のサイクル」を見て頂くと、何故そうなるのかがおぼろげながら判って頂けるのではないでしょうか。
海外出向先において、日本人が心配すると「問題無い」、問題が発生すると「知らない」「仕方ない」、問題対策を確認すると「大丈夫のはず」、見直しを指示すると「ただちに」と言ってやらない。現地人からのこれらの答えは全て自己責任回避が根底にあり、日本式の仕事の進め方を推進したい一心で、このような場面において通訳さんを使って「そうじゃない」と説明しようとすると、責任所在明確化回避、相手と通訳者本人の面子保護、日本語と外国語の文法や表現の差異により益々判らなく深みにはまって行ってしまうのです。
最近では日本でも異なった世代間で同様の事が起こり始めており、日本的な良い点は積極的に伝承して行くべきなのだと感じますが、多様化する価値観や考え方の世代間相違によって日本人同士でも意思疎通が難しくなっているようです。
2、海外出向先で発生するトラブルの特徴的パターン
仕事が日本から海外に進出する様になり、それに合わせて日本人が海外に出て行くケースも増え、それと同時に出向した日本人と現地人の間でもトラブルが非常に増えています。海外で仕事を上手く進めるために知っておいた方が良い、特徴的な失敗パターンを数例挙げてみます。
パターン1:古い日本式
ご本人は真剣にやっているのですがどうも空回りし、気が付けば相手にしてくれるのは通訳さんだけ。こんなケースのご相談をよく受けました。伺って様子を拝見しながらお話を聞いてみると、最も多かったのが日本式の強制、それも二言目には「バカヤロー!」
すごく熱心に古い日本式で指導されていますが、これが通じるのは昔の日本だけ。今では日本でも全く通用しない事は言うまでもありません。 海外でもこの方式を受け入れる土壌がある場所では比較的うまく行きますが、聞く耳を持たない土壌相手にこれをやると一回でダメになり、その後何をしても何を言っても受け入れてもらえなくなります。
パターン2:日本では・・・
このケースは二言目には「日本では・・・。」と常に海外進出先と日本を比較する発言です。現地人に言わせると、日本が進んだ技術の国と言う事は十分に判っており、そこを日本人から十分に吸収して能力を向上させて、自分や家族、ひいては国のために尽くしたいと思っているが、毎回、毎回「日本では・・・。」と日本の優秀性を言われると、その人の話しは聞きたくなくなるそうです。ここにも相手の言う事を受け入れる土壌の有無と、自分や自国の面子を非常に大事にしている事が窺われます。
パターン3:出来ない・・・
海外では「才」であると書かせていただきましたが、出向者が「やってみせる」これが出来ないと最初からうまく行かなくなります。突然海外に送り込まれて、専門部門のみならず果ては担当外領域までカバーしなくてはいけないのが海外出向者。この時に自分の担当領域で「やってみせる」事が出来ないと、あっという間に現地人の間で噂が広がって、そこから後は推して知るべしになります。 日本では本人が実務を回さなくても、組織とマンパワーによって部下が回しているという状況は普遍的ですが、この海外でこの理屈はまず通じません。場合に...