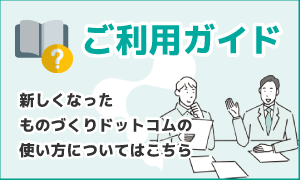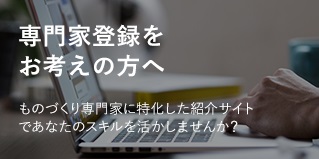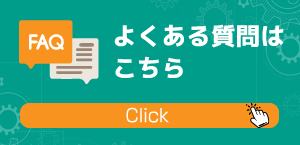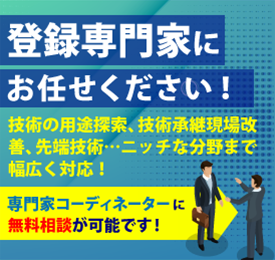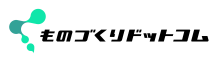L16直交表の場合交互作用も考えると、割り付ける因子の数が限られてきますが、どのように割り付ければいいでしょうか?
「超実践品質工学」をコアとしたデータエンジニアリングで、設計・開発をお手伝する、
株式会社ジェダイトの鶴田(つるぞう)と申します。
直交表の誤差列の問題ということで、品質工学(タグチメソッド)ではなく実験計画法の範疇ですが、ご回答いたします。
まず「実験の精度が上がる」の意味を明確にしたいと思います。前提として実験計画法の基本的な原則(フィッシャーの3原則)は守られ、計測精度についても考慮されているものとして回答します。
「実験の精度が上がる」の意味が、残差(計測精度や偶然誤差)の推定精度がよいという意味でしたら、残差の自由度(情報量)が多いほどよいわけです。L16直交表実験の場合、繰り返しをとらなければ、自由度は15ですから、できるだけ主効果や交互作用を割り付けないほうが、残差の推定という意味では有利になります。逆に直交表にたくさんの要因を割り付けるとそれだけ残差の自由度が小さくなり、残差の推定精度が悪くなります。残差の自由度が稼げない場合は、小さい(有意でない)要因を残差にプールしたり、繰り返しや反復を行って実験全体の自由度を大きくします。自由度の確保と実験(直交表)の大きさのジレンマがあります。
「実験の精度が上がる」の意味が、主効果の推定精度がよいという意味でしたら、交互作用の問題になります。つまり有意な交互作用が出る列に、主効果を割り付けてしまったとすると、その主効果の推定精度が下がってしまいます。事前に交互作用の情報が分からないことも多いので、できるだけたくさん交互作用を割り付けて実験したくなりますが、ここでも実験(直交表)が大きくなってしまうというジレンマがあるわけです。
ご質問のL16直交表の場合、交互作用を調べたい因子が4個以下、独立性が高い因子が5個以下であれば、前者の4個の2因子間交互作用は6個ですので、自由度15で割り付けができます。ただし、残差の自由度がないので、検定を行いたい場合は、小さい交互作用をプールして残差とするか、それでも足りない場合は、繰り返しや反復を行って、残差の自由度を確保することになります。
また、「一般的にどれくらい誤差列を設ければ」ということについては、実際にデータを解析してみて、1つも有意な因子がなく、現実と合わないというような場合は、やはり誤差(残差)の自由度が足りないということが言えます。まったく経験的な指標でいえば、実験の自由度(L16直交表なら15)の半分くらいは、残差の自由度になっていないと検定が意味のある(役立つ)結果にならないと感じます。
以上のように、原因系を交互作用も含めて調べていくというのは、大変なことです。本質問の実験の目的がよくわかりませんが、特性の改善が目的であれば、実験計画法よりも品質工学(タグチメソッド)の実験を行うほうが近道な場合も多いと思います。また具体的な事例のご質問が可能であれば、投稿してくださいね!
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら