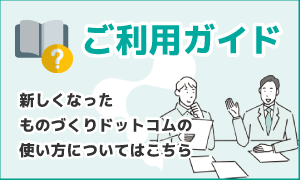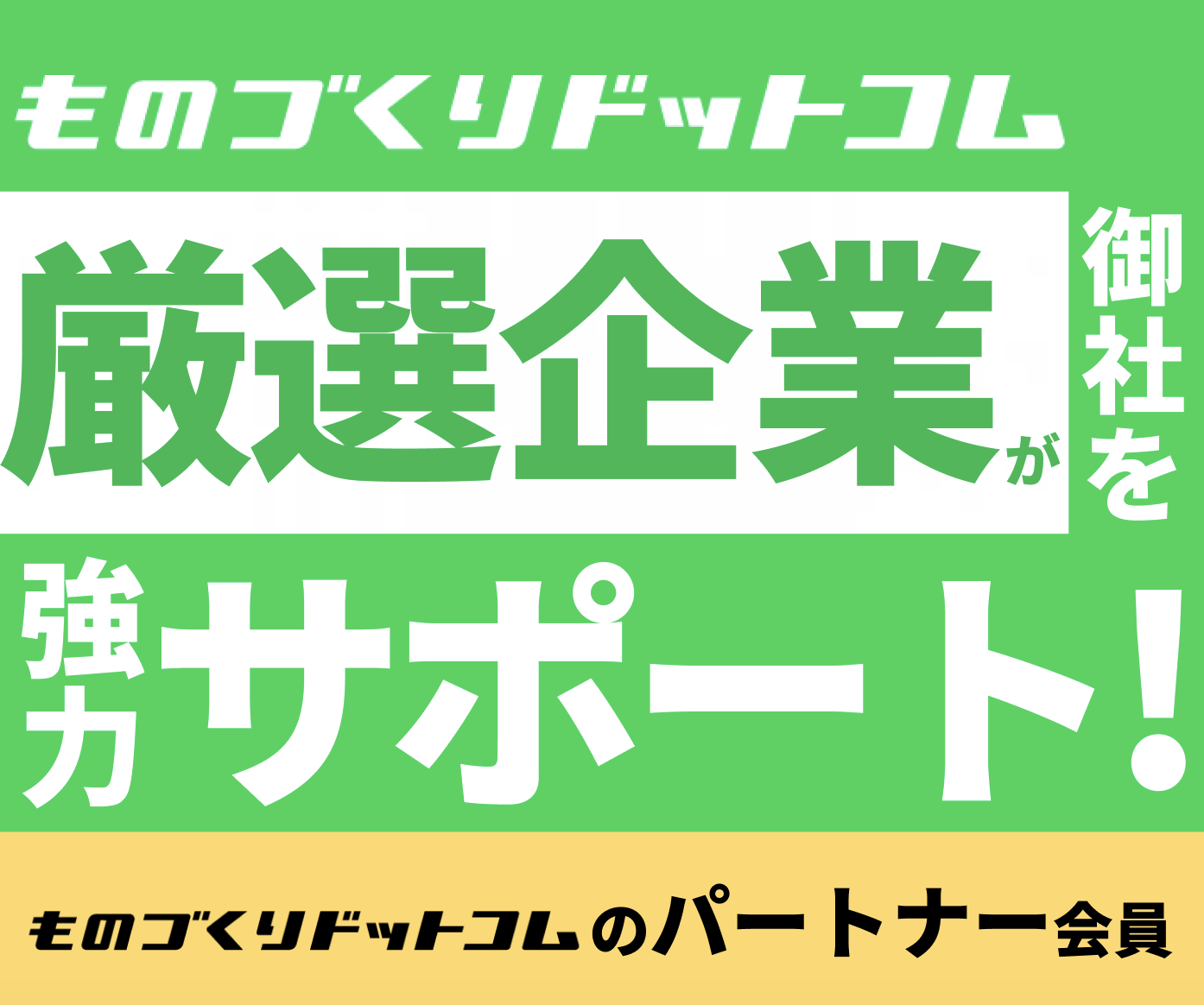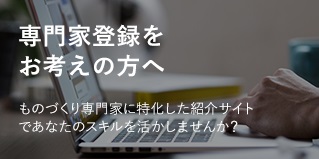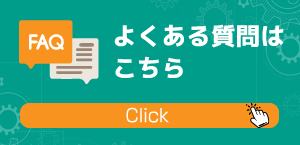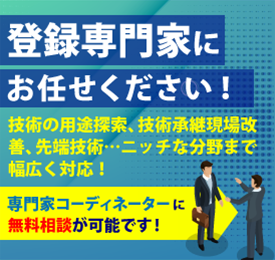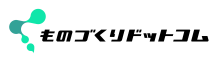直交配列表による分割実験を行う場合は、問答無用で反復回数を2にした方がよいのでしょうか
交互作用の検出も考えています。
宜しくお願い致します。
「超実践品質工学」をコアとしたデータエンジニアリングで、設計・開発をお手伝する、
株式会社ジェダイトの鶴田(つるぞう)と申します。
直交表の内部だけで分割実験を行えるかどうかについては、質問No.265の回答を参照してください。
反復は直交表実験そのものを2回繰り返す(直交表の中で各条件を2回繰り返すのではなく)ので、反復が1次要因となります。したがって、直交表単独で分割実験を行えない(直交表の自由度が小さい)場合でも、直交表の外側に反復をとることで分割実験になります。
また直交表が大きい場合でも、反復をとった場合データ全体の自由度がそれだけ大きくなり、反復をとらない場合にくらべて誤差の自由度が大きくなるため、誤差の推定精度が高くなり、要因効果が有意になりやすいというメリットがあります。
問答無用で反復が2回がよいのか、10回がよいのかは、実験コストによるでしょうね。
|
|
追記の質問にお答えします。
>要因効果が有意になりやすいということですが、要因のほとんどが有意になってしまって有意とそれ以外の区別ができなくなってしまわないでしょうか。
要因効果が有意になりやすいというメリットとはどのようなことですか。
まず後者の「要因効果が有意になりやすい」のメリットについてです。そもそも実験計画法(直交表実験に限らず)の分散分析の目的は、特性値yに対して、有意な要因を見つけ、またそれが複数ある場合は寄与率などで効く要因の順位付けし、次の行動を決めることにあります。したがって、どの要因も有意にならなければ(これはどの要因も効いていないという意味ではありません)、どの要因に対しても行動をとることができません。ふつうは、なかなか有意な因子が見つからなくて困るものです。その場合に有意でない要因を誤差にプールしたり、3水準の要因を1次の効果と2次の効果に分解して2次の効果だけ誤差にプールしたり、いろいろ策を弄するわけです。
そういうわけで、前者の「要因のほとんどが有意になってしまって有意とそれ以外の区別ができなくなって」しまうのは悪いことではなく、たとえすべての要因が有意となってもそれはすべての要因が少しずつ効いているということであり、その効き方は寄与率などで知ることができるということです(ただし下記の留意点3には注意する必要あり)。
ここで有意性や寄与率の解釈にあたっての留意点をいくつか述べておきましょう。
1つ目は、ある要因の寄与が統計的に有意であるからといって、技術的、経済的に意味があるかどうかは別問題ということです。有意とは、あくまで残差(偶然誤差)に比べて変動(平均平方)が大きいということが(ある危険率のもとで)主張できるだけです。技術的、経済的に意味があるか(行動が変わるかどうか)は統計の枠外で判断しなければなりません。有意というのは、そのような技術的、経済的に意味があるかどうかを俎上(まな板の上)に載せるための1つの条件にすぎないということです。
留意点の2つ目は、水準数が多い要因はその分平方和も大きくなるので、寄与率が大きくなるという点です。寄与率は変動(平均平方)の按分ではなく、平方和の按分になっていますので、2水準の要因と10水準の要因では後者のほうが平方和は大きくなりやすいですし、当然寄与率も大きくなります。
留意点の3つ目は、残差の自由度が大きすぎる場合は誤差変動Veが非常に小さくなり、ほとんどの要因が有意になりやすいということです。無意味に多くの繰り返しや反復をとったり、要因の水準を多くしたりしないようにしましょう。
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら