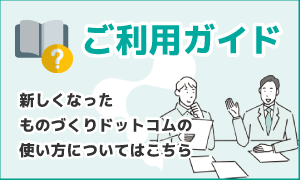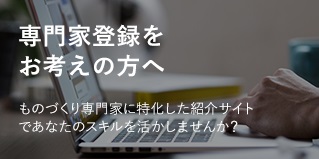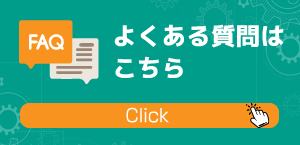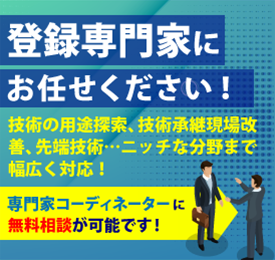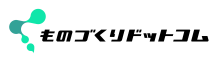疑問にお答えします。
直交表は極めて協力なツールですが、魔法ではなく、「統計的な手抜き」です。
4水準Aと3水準Bの2因子の「二元配置実験」の場合、組み合わせは12通りで全てですから、12回の実験で交互作用A×Bを含めて全ての要因効果を評価できます。
ただし各効果の有意差を判定しようとすると、実験誤差と比較しなくてはならないために、同じ組み合わせを繰り返す必要があり、たとえば全ての組み合わせを2回ずつ実施するなら、おっしゃるように24回の実験となりますが、実験誤差を求めるためだけに全部2回やるのは、ちょっと労力/費用的にもったいない気がしませんか?
例えば要因効果A、Bと交互作用A×Bを計算した所、どれかが非常に効果が小さかった時に、それを「実験誤差程度の効果」と考えることができれば、それを他の因子効果と比べれば、繰り返さなくても有意差判定が可能になります(プーリングといいます)。なんと実験数が半分になるわけです。しかしこれは当然ですが12回と24回の実験が全く同じなわけではありません。「効果の小さい要因効果は実験誤差とさほど違わない」という経験則で割り切って、大幅に手を抜いたということです。
直交表も似たようなことが言えます。L16直交表の場合、2水準因子もしくはそれらの交互作用を合わせて15個まで評価することができます。本来2水準15因子の組み合わせは2の15乗=32768通りありますが、(高次の)交互作用効果に目をつむることで、大幅に実験効率を上げているのです。
一般にこれも「2次以上の交互作用は考慮に値しないことが多く、仮に大きかったとしても実用的に利用することが難しい」という経験則で割り切った手抜き法です。
15列の一部に因子を割り付けないことで、実験誤差を計算すれば、16回の実験中で、有意差判定まで可能になります。
あらゆる場合に直交表実験を勧めるものではありませんが、個人的感覚として、ほとんどの要因実験に「正しく」直交表を使うことで、開発効率が数倍から数十倍向上します。
お金と時間が無限にある人は、要因実験で全ての組み合わせを実施して精密な結果を求める選択肢がありますが、その時も組み合わせを正しくしないと統計的な分析が不可能となり、多大なお金と時間を単にドブに捨てることになります。
どの様に実験するにしても、実験計画法(通常は有意差判定、配置実験、直交表などが含まれる)を学習して、より効果的/効率的な実験を心がけて下さい。
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら