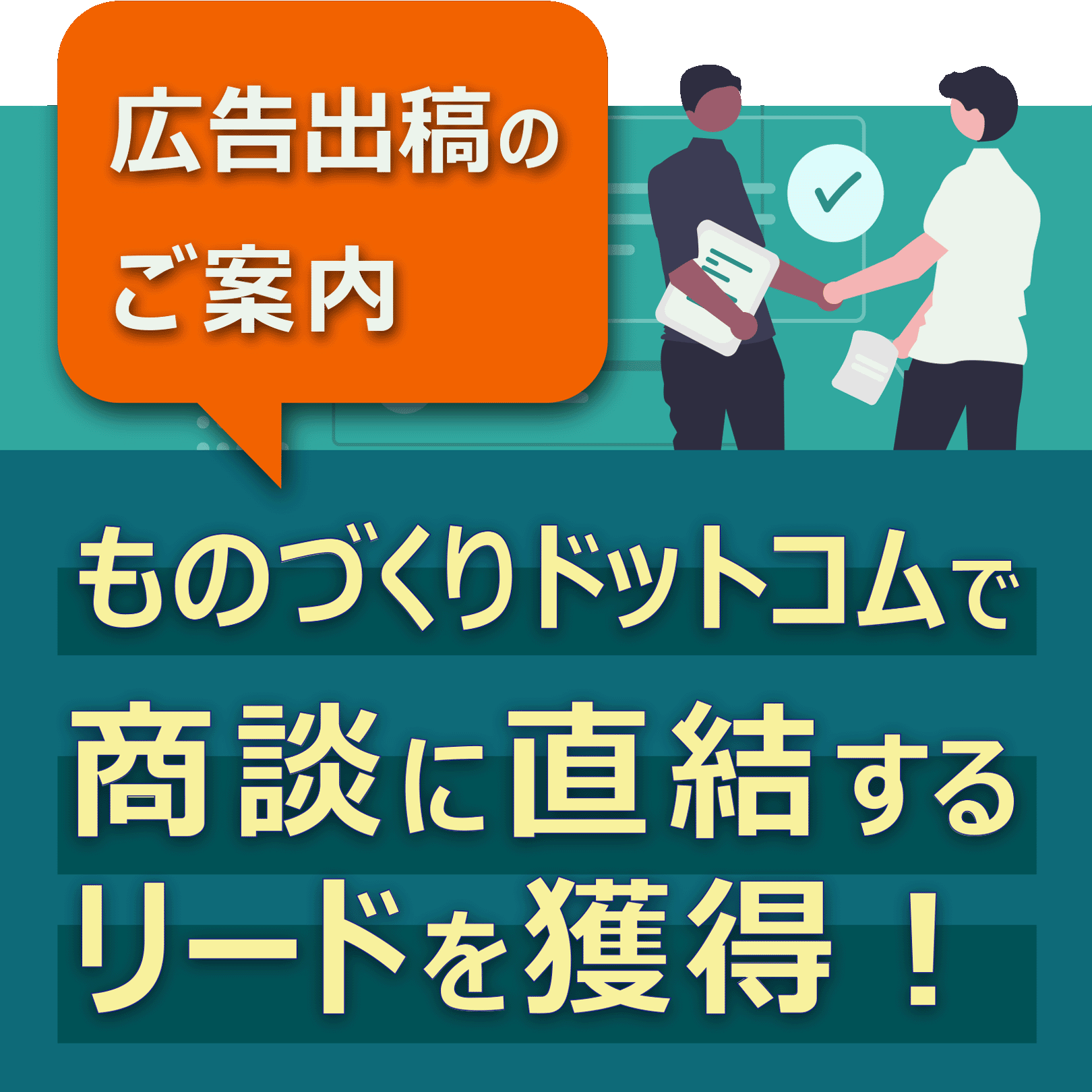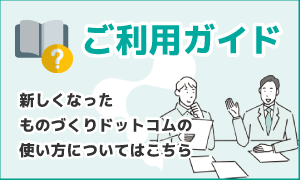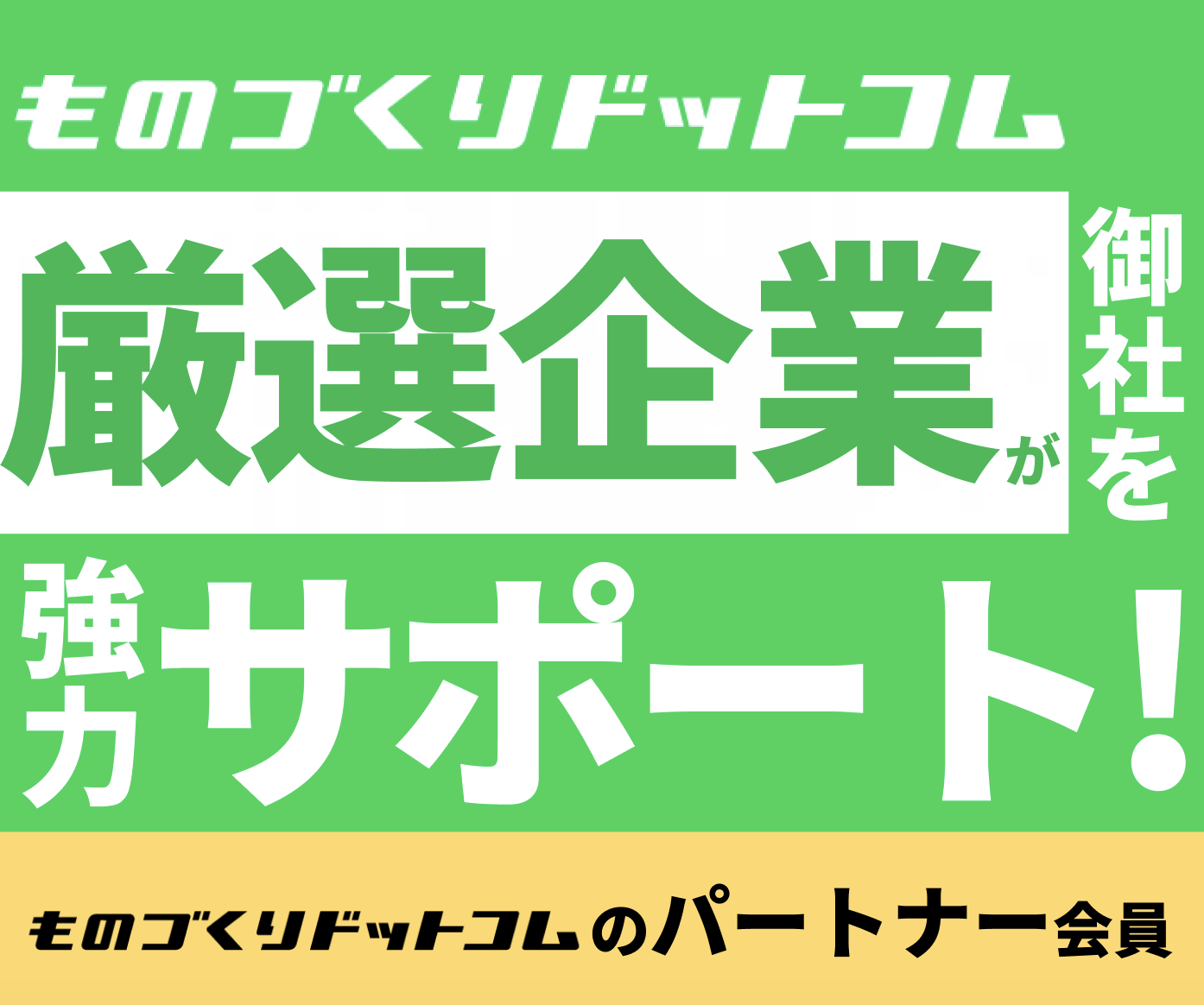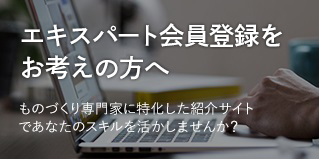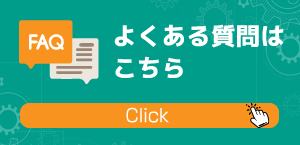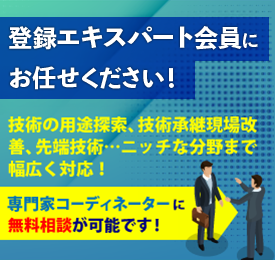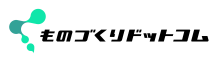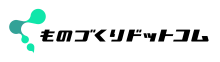
また、誤差要因を割り付ける際にはどこの列に入れるのが良いのでしょうか?
直交表への因子割り付けは、慣れるまで色々と悩ましいですよね。
8列すべてに制御因子を割り付けずにブランクとする、即ち誤差列として扱うことで、因子がないにもかかわらず変動する大きさを評価することができますので、実験誤差や設定した因子間の交互作用の大きさを評価することが可能になります。
誤差列と因子列の分散比で有意差検定することも可能です。
しかし誤差列の変動を実験誤差と交互作用の要因とに分離することはできません。
何よりも、せっかく8つの制御因子を評価できる機会を自ら放棄してしまうのは、いかにももったいない。良い設計をする時に、制御因子と誤差とどっちの評価が大事だろう?という観点です。
ということで近年は、直交表に最大限の制御因子を割り付け、どうしても使いきれない列がある時にだけ誤差列として利用することが多くなっています。
ちなみに誤差列を割り付ける時は、どの列に設定しても構わないのですが、交互作用がある場合は設定する列を変えるとその分だけ結果が変わってきます。
そんなことを気にするよりは、試してみたい組み合わせが現れるように、誤差列を含めて因子の割り付けを考えてみてはどうでしょう?
ご参考になれば嬉しいです。
また質問して、使いこなしてくださいね。
|
|
パラメータ設計でも、特に制御因子間の交互作用が複雑に絡み合うことの多い化学系を得意としている対馬と申します。
直交表へ因子をわりつける際に考慮しなければいけないことは、その因子の役割です。すなわち、設計者が自由にその値を決めることのできる制御因子か、設計者がその値を決めることができない(制御/管理できない)誤差因子かです。
例えば、引張強さは大きいほどよく、温度が高くなると強度が弱くなるという場合は、温度は誤差因子になります。 その場合には直交表にわりつけるのではなく、外側にわりつけて、標準的な温度と強度を悪くする温度でそれぞれ18通りの実験をします。 また、誤差因子が複数ある場合には調合して、標準的と思われる条件と結果が最悪になると予想される条件の2水準にして、それぞれ18通りの実験をします。
おっしゃっている誤差要因が誤差因子に当てはまるなら、以上のような考え方で進めるのがいいです。 制御因子に当てはまるようでしたら、因子としてわりつけて問題ありません。
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら