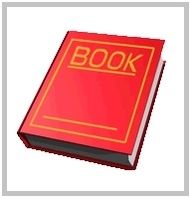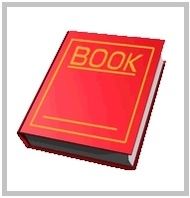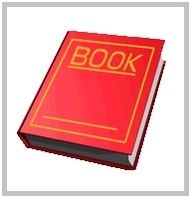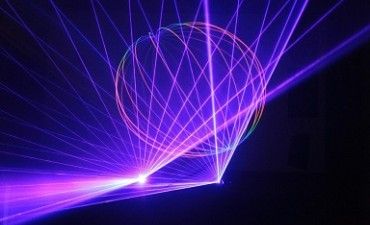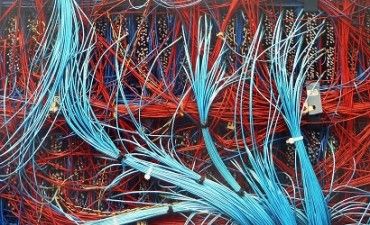エネルギー貯蔵装置の活用に向けた展望
開催日:2022年 5月16日(月)
セミナー趣旨
カリフォルニア州は、2050年のパリ協定遵守に向かって、全セクターでの脱炭素化が急速に進んでおり、これは全米にとっての先進モデルとなっている。発電セクターでの再エネ発電比率は順調に伸びており、「2030年の再エネ発電比率60%」に向かってまっしぐらに進んでいる。2022年現在でも、日によっては、短時間ではあるが80%以上が再エネ電力になる。
反面、変動の大きい再エネ発電比率が増えることと、ベースロードがなくなることによる問題点も出始めており、その準備・対策が果たして間に合うのか不安も多く、講師は、これを「2030年問題」と呼んでいる。カリフォルニア州政府は、色々な施策で乗り越えようとしているが、現時点では「大型のエネルギー貯蔵装置による力による抑え込み」が主な対策となっている。2013年に制定された州法(AB2514)による、大手電力会社への1.3GWの設置の義務化を契機に、エネルギー貯蔵事業者と電力会社間の新規契約が一気に増加しており、準備・設置・テスト期間を経て、2020年から急速にオンラインになり始め、2021年末には累計で4GWとなった(分散型を含む)。
2022年2月に州政府によって承認されたプランでは、2030年までの大型ソーラー施設増設14GWに対して、大型エネルギー貯蔵も同量の14GWを増設するという破格の計画になっている。カリフォルニア州の春・秋のピークは30GW程度なので、その巨大さが分かるであろう。通常のピークならバッテリーで半分を賄うことができる。
これに伴い、エネルギー貯蔵装置は、これまでの主な活躍の場であった「アンシラリーサービス市場」から、今後は「エネルギー市場」そのものに移って行くことになる。「変動吸収(長中短期)は、エネルギー市場のリソースで賄う」というこれまでのカリフォルニア州の方針を、さらに一歩進めることになるが、これは大きな実験でもある。
運輸セクターに目を向けると、2021年のカリフォルニア州の新車販売台数に占めるBEV(バッテリー電気自動車)販売シェアは、驚異の9.5%となった(全米では3.4%、日本は1%前後)。カリフォルニア州では2035年にガソリン車の販売が禁止されるが、このペースで進むと、意外にすんなりと「Late Majority(34%)」まではEV化が進むかもしれない(Laggards(16%)はICEに拘り続けると思う)。
EVメーカーとして有名なテスラは、EVに留まらずに、定置型エネルギー貯蔵装置、太陽光発電施設、マイクログリッド、家庭向け冷暖房装置、エネルギーマネージメントシステム等への積極進出と、「自前での垂直統合」を目指している。特に定置型エネルギー貯蔵装置(分散型と大型の両方)では大きなシェアを誇る。これは、EVで用いるバッテリーセルとの共通利用を最初から考えているだけではなく、エネルギービジネスの理解と、今後あるべき世界観に向けた地道な努力の賜物でもある。これらのビジネスモデルは「諸刃の剣」的なところはあるが、今のところイーロンマスクはうまく乗り切っている。
米国(シリコンバレー)に30年以上居住し、エネルギービジネスとテスラの動向をつぶさに見てきた講師が、最新のトピックスを交えながら、大型エネルギー貯蔵装置の動向と、テスラのエネルギービジネスの現状と今後の動向をお伝えする。
セミナープログラム
1.背景
(1)脱炭素に向けたエネルギー革命
(2)バイデン政権の目標
(3)カリフォルニア州の目標
2.カリフォルニア州の大型エネルギー貯蔵
(1)2032年までの再エネとエネルギー貯蔵の目標
(2)エネルギー貯蔵事業者・系統運用者・電力会社にとっての経済性
(3)大型エネルギー貯蔵施設の有効活用に向けた制度設計
(4)アンシラリーサービス市場とエネルギー市場の使い分け
(5)再エネ併設型と単独設置型の使い分け
(6)続く火災事故
3.テスラのエネルギービジネス
(1)ビジネス向けと家庭向けエネルギー貯蔵で大きなシェアを持つも、供給が追いつかない
(2)カリフォルニア州で稼働が始まった巨大なエネルギー貯蔵施設
(3)エネルギーを貯めるだけでなくどう活用するかがポイント
(4)バッテリー自社製造にいよいよ乗り出す
(5)新しいフォームファクター4680セルの量産化と低価格化が鍵
(6)ギガファクトリーの動向
(7)パナソニックと中国との協業モデル
セミナー講師
阪口 幸雄(さかぐち ゆきお) 氏 クリーンエネルギー研究所 代表
セミナー受講料
1名につき 40,000円(税込)
受講について
■セミナーオンデマンドについて
<1>収録動画をVimeoにて配信致します。
<2>動画の配信期間は公開日より2週間ですので、その間にご視聴ください。
2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可能です。
受講料
40,000円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
ペロブスカイト電池とは?仕組み・信頼性・シリコン太陽電池との比較
【目次】 ペロブスカイトは、太陽光発電やエネルギー貯蔵技術において注目を集めています。この材料は、従来のシリコンベースの太陽電池に比... -
GPSとは?位置情報の仕組みから活用事例・未来の可能性まで徹底解説
【目次】 グローバル・ポジショニング・システム(GPS)は、私たちの日常生活に欠かせない技術となっています。スマートフォンやカーナビ... -
レーザー技術とは?原理や応用技術、用途や将来性を解説!
【目次】 レーザー技術は、現代の科学技術の中でも特に注目されている分野の一つです。レーザーは「Light Amplification... -
無線通信技術とは?仕組みや種類、規格の特徴など最新情報を解説!
【目次】 無線通信技術は、私たちの日常生活に欠かせない重要な要素となっています。スマートフォンやWi-Fi、Bluetoothなど、...