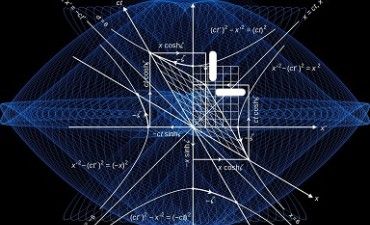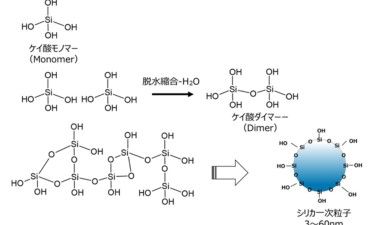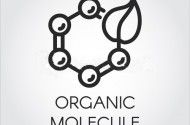
多層フィルム・軟包装におけるリサイクル技術の最新技術・研究動向と再生材料の利用・認証・課題と展望
~水平リサイクルの現状・異材質ラミネート包材の多層分離事例・脱インク・剥離・再生樹脂の開発・認証習得~
★包材から包材への水平リサイクルを目指す取り組み、モノマテリアルだけではない、異種材料を利細工するための多層ラミネート構成の分離・脱墨の技術とは?
★相溶化と添加剤の活用方法の現状とは?再生・リサイクル樹脂の開発動向や採用、廃棄軟包装材料の回収・選別方法とは?
★再生樹脂製造時のインキによる臭い防止などの課題にどう取り組むのか?
セミナープログラム
【第1講】 溶媒抽出法によるラミネートフィルムの分離とその再利用
【時間】 13:00-14:30
【講師】崇城大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 工学博士 池永 和敏 氏
【講演主旨】
COVID-19のパンデミックにより、家庭内での食品の消費が急増したことは、記憶に新しいと思う。すなわち、我々は、冷凍食品やスナック菓子のプラスチック製の袋を多量に消費したことになる。その殆どが、耐酸化措置として、アルミニウムの薄層を含むPET、PEおよびPPの多層フィルム(ラミネートフィルム)であり、複合材であるため単純な光学選別も役に立たず、多くの場合、燃焼もしくは埋め立てられるプラスチックの1つになっている。
講師らは、溶媒抽出を用いると極めて容易にフィルムの分離が可能であり、単純なラミネートフィルムの場合には、構造解析も可能となることを報告している。本講座では、ラミネートフィルムの分離と再利用の可能性について、焦点を絞り、解説する予定である。なお、実際の分離したフィルムなどについては、画面を通して、ご覧に入れる予定である。
【講演キーワード】
COVID-19、溶媒抽出法、ラミネートフィルム、多層フィルム、ラミネートフィルムのリサイクル、ケミカルマテリアルリサイクル
【習得できる知識】
プラスチックのリサイクルの基礎、ラミネートフィルムの層構造、溶媒抽出法、ラミネートフィルムの分離・精製、ATRイメージング法
【講演のポイント】
講師は、2005年から、マイクロ波を用いたポリエステル等のケミカルリサイクルの研究を行っている。現在、新しいコンセプトで、廃棄プラスチック中のPE、PPおよびPSなどの溶媒抽出法についても、ケミカルマテリアルリサイクルの観点から、研究を進めている。本講義では、その溶媒抽出法をラミネートフィルムへ適用すると、ラミネートフィルムの分離分析が可能となり、その0.01-0.03mmのフィルムの層構造にもメスを入れることが可能となった。なお、ATRイメージング法(パーキンエルマー・ジャパンの協力)を用いて、その層構造について確認したことにも言及する予定である。
【プログラム】
- プラスチックの生産・製品・用途・廃棄
- 一般的なプラスチックのリサイクル
- 溶媒抽出法について
- 溶媒抽出法によるラミネートフィルムの分離・精製
- まとめと今後の展望
【第2講】 軟包装材の廃材の対応法について ~各国動向・3R・多層包装材リサイクルの手法~
【時間】 14:40-15:55
【講師】三菱ケミカル株式会社 スペシャリティマテリアルズビジネスグループ グローバル企画本部 戦略部 GXグループ GX推進本部 事業開発部 小林 修二 氏
【講演主旨】
軟包装材の廃材を「なぜ」「どのように」処理するのかについて、各々の観点から、各国の動きや、各社の取組事例をみながら皆さんとともに整理をしたい。
資源循環は変化と成長が早く、情報が重要であることは言うまでもない。そこで資源循環を作る業務に携わるものとして、どんな情報をどのように集め、どのように考えているのかを、概説させて頂き、皆さん各々で概説内容をご評価を頂くことで、皆さんの今後の業務の進め方の方向性の確認をして頂ければと考える。最後に特に多層包装材の廃材の処理は、必要でありながら困難を極めるが、各社の取り組みの具体例を整理する。
【講演キーワード】
海洋プラゴミ 各国 プラゴミ プラゴミ対応 3R Reduce Reuse Recycle リサイクル 多層包装 資源循環 具体例 情報収取
【習得できる知識】
軟包装の廃材の処理に対する各国の動きや、各社の対応方法についての具体例を把握できる。特に多層包装材の各社の対応方法について把握できる。
【講演のポイント】
資源循環の構築に情報は欠かせない。資源循環を作る業務を行うものとして、その目線で、集める情報や考え方、情報収取の方法について、一例ではあるが概説するので、同じような業務を取り進める皆様の参考にはなると考える。資源循環は多くの企業の協業で成り立つものであるので、今回の講習を通して、情報の取り方だけでなく実際の情報についても交換できる関係性の構築も図れる。
【プログラム】
- 海洋プラゴミの危機的状況
- プラゴミに関する各国の動き概要
- 3R ~3Rのどの手段を選定するか~
- Reduce 重量減/薄肉化/アルミ化/紙化 具体例
- Reuse 具体例
- Recycle ケミカルリサイクル/脱墨技術/回収分別/リサイクル技術実証例 具体例
- 多層包装材
多層包装材の資源循環の為のリサイクル技術 具体例 - 最後に
【第3講】 Co-Ex及び多層ラミネートフィルムの循環型パッケージ促進 の対応と脱墨・剥離技術の課題
【時間】 16:05-17:20
【講師】住本技術士事務所 所長 住本充弘 氏
【講演キーワード】
循環型パッケージ、モノマテリアル、脱インク、剥離技術、アップサイクリング、EU 2022/1616、Recyclable認定
【習得できる知識】
循環型パッケージの対応の仕方、Recycled plasticsの理解、EU2022/1616の概要、アップサイクリングの世界の動き、モノマテリアルの言葉の使い方、グリーンウォッシュの意味
【講演のポイント】
循環型パッケージの促進に向けて、特に軟包装材料のrecycled polymers使用、脱インク・剥離技術、メカニカルリサイクルのアップサイクリング対応の現状と課題についてinterpack 2023の事例や最近の国内外の事例を説明し今後の対応法をさぐる。
【プログラム】
- Co-Ex及び多層ラミネートフィルムの再生再利用の課題
- 分別排出、回収・選別方法
- 再生再利用の施設の整備
- Recyclable認定事例と包装食品の輸出の障壁
- 相溶剤の利用事例
- FDA及びEFSAの再生樹脂への対応
- 異物混入の懸念 --ブロックチェーンによるtrace
2-2 認証取得, certified resinsの必要性 - EU 2022/1616の概要
- 異物混入の懸念 --ブロックチェーンによるtrace
- モノマテリアルではなく主構成分がPP、PE,PET、紙
- 的確な表示に修正が必要なモノマテリアル使用
- 回収streamの存在の有無確認
- アップサイクリングに向けて
- 脱墨・脱離(剥離)技術の動き
- プラスチック包装の脱インキはなぜ必要か
- 脱墨技術の状況とメカニカルリサイクル
再生樹脂製造時のインキによる臭い防止が必要、特許の事例
欧州における脱墨・剥離ビジネスの事例
日本の軟包材の脱墨の事例 - 脱離技術のビジネス事例
脱インキ用プライマーの利用、水性の食品安全性の剥離剤
スペインアリカンテ大学開発の脱インク技術と世界への普及 - 異材質ラミネート包材への脱インク及び剥離の対応をどうするか
裏刷りラミネート包材の脱インキは、剥離技術が必要、現在の開発状況
- 日本の軟包装材料の循環型パッケージ推進の課題
まとめ
【第4講】 複合フィルムのマテリアルリサイクル樹脂
【時間】 17:30-18:15
【講師】東和ケミカル株式会社 常務取締役 棚窪 重博 氏
【講演主旨】
※ 現在考案中です。
【プログラム】
- 東和ケミカル社の概要
- 複合フィルムリサイクルを手掛けた背景
- 廃棄プラスチックを資源とする中国の台頭
- 複合フィルムリサイクルの必要性
- 複合フィルムのマテリアルリサイクル技術の開発
- 複合フィルムリサイクル樹脂「東和ハイブリッドPP®」
- 他社様への提案
- 食品工場から出る廃棄アルミ蒸着包材のマテリアルリサイクル
- リサイクルコンテナ・パレットの特徴
- 「東和ハイブリッドPP®」の展望
- 包材から包材への水平リサイクルを目指して
セミナー講師
- 第1部 崇城大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 工学博士 池永 和敏 氏
- 第2部 三菱ケミカル株式会社 スペシャリティマテリアルズビジネスグループ グローバル企画本部 戦略部 GXグループ GX推進本部 事業開発部 小林 修二 氏
- 第3部 住本技術士事務所 所長 住本 充弘 氏
- 第4部 東和ケミカル株式会社 常務取締役 棚窪 重博 氏
セミナー受講料
【1名の場合】55,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
受講料
55,000円(税込)/人