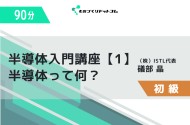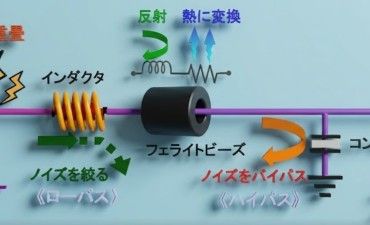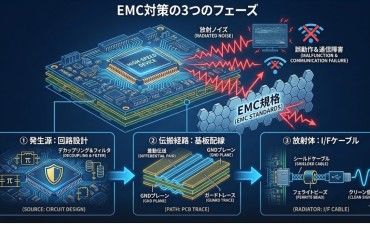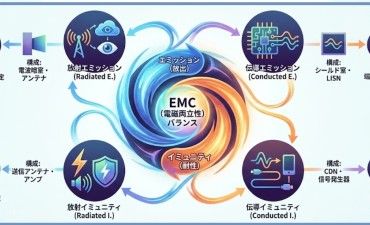次世代半導体に向けたウェハ材料の応用と展開
~ダイヤモンド半導体・シリコンゲルマニウム半導体・二酸化ゲルマニウム半導体~
2024年3月8日開講。佐賀大学大学院 嘉数氏、東洋アルミニウム株式会社 鈴木氏、立命館大学 金子氏の3名講師からダイヤモンド半導体、シリコンゲルマニウム半導体、二酸化ゲルマニウム半導体の特徴、応用、可能性について解説します。
■本講座の注目ポイント
★次世代の高出力・高効率パワー半導体として期待される3種の半導体、ダイヤモンド半導体、シリコンゲルマニウム半導体、二酸化ゲルマニウム半導体の基礎から特性、今後の課題、将来の可能性についてわかりやすく解説!
セミナー趣旨
■本セミナーの主題および状況
★次世代の高出力・高効率パワー半導体として期待される3種の半導体、ダイヤモンド半導体、シリコンゲルマニウム半導体、二酸化ゲルマニウム半導体の基礎から特性、今後の課題、将来の可能性についてわかりやすく解説!
■本講座の注目ポイント
★ダイヤモンド半導体は究極のパワー半導体と呼ばれているがここ数年の間、大口径ウエハ結晶成長技術、半導体デバイス技術が急速に発展。その現状を解説!
★新しいSiGe仮想基板の形成技術でありNEDO先導研究プログラムでの研究も進めている、Al誘起SiGe液相成長手法について、メカニズムと応用例を紹介!
★GeO2はパワー半導体として新しい材料だが、新しい候補材料として大きなポテンシャルを秘めている。新材料のため、市場に浸透する時は多くの技術課題を解決する必要がある。その魅力について物性や作製手法を中心に解説!
セミナープログラム
【第1講】 ダイヤモンド半導体の基礎、特徴、応用例、今後の課題
【時間】 13:00-14:15
【講師】佐賀大学大学院 理工学研究科 教授/佐賀大学海洋エネルギー研究センター(併任) 教授 嘉数 誠 氏
【講演主旨】
ダイヤモンド半導体は、Si, SiC, GaNより、さらにワイドギャップの半導体で、次世代の高出力・高効率パワー半導体デバイスとして期待されています。講演では、ダイヤモンド半導体の基礎から、ダイヤモンド大口径ウェハ結晶成長技術、最近の優れたパワー半導体デバイス特性、パワー回路の特性、さらに、今後の課題や将来の可能性について、わかりやすく解説します。
【プログラム】
1. なぜダイヤモンド半導体が注目されるか
2. ダイヤモンド半導体の物性
3. ダイヤモンド半導体のこれまでの応用例
4. ダイヤモンド半導体のマイクロ波CVD成長
5. ヘテロエピタキシャル成長
6. ダイヤモンド半導体の不純物ドーピング技術
7. NO2 p型ドーピング技術
8. ダイヤモンドMOSFETの作製
9. ダイヤモンドMOSFETパワー回路の作製
10. 今後の課題と可能性
【質疑応答】
【キーワード】
ダイヤモンド、パワー半導体、パワーエレクトロニクス
【PRポイント】
ダイヤモンド半導体は、究極のパワー半導体と呼ばれていますが、ここ数年の間、大口径ウエハ結晶成長技術、半導体デバイス技術が急速に発展しました。講演では、その現状を解説いたします。
【習得できる知識】
ダイヤモンド半導体の物性、結晶成長技術、半導体デバイス作製技術
【第2講】 シリコンゲルマニウム半導体の特徴と成長技術の開発
【時間】 14:30-15:45
【講師】東洋アルミニウム株式会社 先端技術本部 粉体技術研究ユニット 電子機能材開発チーム 鈴木 紹太 氏
【講演主旨】
本講演では、シリコンゲルマニウム(SiGe)半導体とその基板技術について紹介します。SiGeは、Si半導体への部分的な使用により高速性や低消費電力などの特性を与えることに使用されています。一方SiGe基板は、一般的な引き上げ法やゾーンメルト法では均一な組成のインゴットを作れないことからSiGe基板を用いたデバイスは実用化されていません。そこで、私たちは、スクリーン印刷を用いた新たなAl誘起SiGe液相成長手法を開発しています。この手法では、低コストでSiGe仮想基板を形成することができることから、新たな用途を期待して、成長メカニズムや制御についての研究を進めています。この技術に関する紹介と、今後の展望について紹介します。
【プログラム】
1.シリコンゲルマニウム(SiGe)半導体について
1.1 SiGe半導体の特徴
1.2 SiGe半導体の用途
2.SiGe基板と成長手法について
2.1 SiGe成長手法
3.スクリーン印刷を用いた新規SiGe成長手法
3.1 スクリーン印刷を用いたAl誘起SiGe液相成長技術
3.2 成長メカニズムと成長制御
3.3 研究の取り組みと応用例
4.デバイス応用への検討
5.まとめ
質疑応答
【キーワード】
シリコンゲルマニウム、SiGe、半導体、液相成長、スクリーン印刷
【講演ポイント】
東洋アルミニウム及び講演者は、金属粉を使用したペースト技術開発を長年行っている。本講演では、新しいSiGe仮想基板の形成技術でありNEDO先導研究プログラムでの研究も進めている、Al誘起SiGe液相成長手法について、メカニズムと応用例を紹介する。
【習得できる知識】
SiGe半導体の特徴
スクリーン印刷によるSiGe半導体の形成技術と課題
SiGeを基板とした超高効率太陽電池
【第3講】 二酸化ゲルマニウム半導体のパワー半導体応用可能性
【時間】 16:00-17:15
【講師】立命館大学 総合科学技術研究機構 教授・RARAフェロー 金子 健太郎 氏
【講演主旨】
昨今、パワー半導体業界には新材料による新たな市場形成が始まっています。例えばSiCはこの10年間の大幅な低価格化により徐々に市場に浸透し始めており、高周波デバイス用途ではGaNが絶対的な地位を築こうとしています。近い将来、SiCやGaNより大きなバンドギャップをもつ高性能なデバイスはいずれ必要になりますが、新材料が市場で受け入れられるには厳しい条件をクリアしなければいけません。それは①基板、薄膜、加工のコストが低い②SiCやGaNよりも優れた低損失性③p型とn型のドーピング手法による作製の実現性、の3つが基本条件です。本セミナーではその条件をクリアし、候補材料となり得る新しいパワー半導体材料である二酸化ゲルマニウム(GeO2)の物性や作製手法についてお話をします。
【プログラム】
1.SiC、GaNの今後の動向
2.新しいパワーデバイス材料、二酸化ゲルマニウム(GeO2)の可能性
2-1 GeO2の可能性
(バンドギャップ4.6 eV、p型とn型が作製可能(理論予測)、高い移動度、安価に基板作製可能)
2-2なぜ、GeO2の薄膜合成は困難なのか?
2-3 GeO2厚膜の合成
2-4 GeO2混晶
2-5世界のGeO2研究
質疑応答
【キーワード】
パワー半導体 二酸化ゲルマニウム GeO2 SiC
【最大のPRポイント】
GeO2はパワー半導体として新しい材料ですが、新しい候補材料として大きなポテンシャルを秘めています。新材料なので、市場に浸透する時は多くの技術課題を解決する必要がありますが、その魅力について物性や作製手法を中心にお話しします。
【習得できる知識】
新しいパワー半導体材料であるGeO2の半導体としての特徴や世界の研究状況などの知識が得られます
セミナー講師
- 第1部 佐賀大学大学院 理工学研究科 教授/佐賀大学海洋エネルギー研究センター(併任) 教授 嘉数 誠 氏
- 第2部 東洋アルミニウム株式会社 先端技術本部 粉体技術研究ユニット 電子機能材開発チーム 鈴木 紹太 氏
- 第3部 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授・RARAフェロー 金子 健太郎 氏
セミナー受講料
【1名の場合】44,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
主催者
開催場所
全国