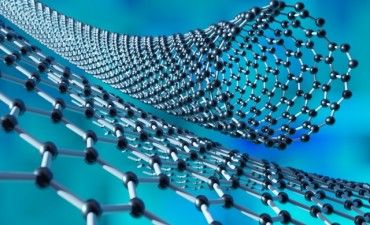文系でもわかるレオロジー超入門 ~ 数式に頼らない直感的理解による材料設計
■注目ポイント
★レオロジーを実践的に使いこなすためのベースとなる基本的な事項を実感として理解し、材料の持つ「流動と弾性」という二面性をイメージとして持てるように解説!
セミナー趣旨
我々の身の回りの材料の大半は流れるという性質を持っています。当然、それぞれの材料ごとに流れ易さは異なりますが、非常に長い時間をかければ岩や大地も流れていきます。その流れるものを測る学問がレオロジーです。レオロジーの本質をきちんと理解することで、各種の材料の違いを明確に区別する方法がイメージでき、材料設計のポイントもわかってきます。
本セミナーは、レオロジーを実践的に使いこなすためのベースとなる基本的な事項を実感として理解し、材料の持つ「流動と弾性」という二面性をイメージとして持てるようになることを目指します。これらの理解を深めることで、液状材料の流動特性の違いの理由や、高分子材料の力学特性の設計方法の指針を身につけることができ、開発への展開の第一歩が踏み出せるものと期待しています。
【講演のポイント】
材料の開発において、対象とする材料の特性を評価することが必須です。たとえば、液状材料を設計する場合には、その流動特性を理解するためにレオロジー測定が有効です。また、高分子材料の硬軟や耐久性のような力学的な特性の評価には、線形粘弾性理論に基づく粘弾性スペクトルが役立つことが知られています。本セミナーを通じてレオロジーや粘弾性測定についてのイメージを掴めば、実際の測定や解析に活かすことができるようになります。
直感的に感じる違いをきちんとした理解へと結びつけるために、本セミナーでは、「箇条書き」や「図解」を多用します。そうすることで、単に抽象的な概念としてだけではなく、ブレイクダウンしたイメージとして直感的に捉えていきます。また、数式だけに頼ることなく、数式が表したいことを理解して、イメージと数式をつなげていきます。
受講対象・レベル
・レオロジーが何の役に立つのかを理解したい方
・レオロジー測定はやっているけどどういう意味かよくわからない方
・知識としてこの技術を理解しようとしている方(上記以外の方々)
習得できる知識
●レオロジーとは何なのか?
・刺激を与えて応答を測ること
・物質の本質は流れる。
・流れやすさを決めるものは?
●材料の違いを理解する。
・材料の熱特性の成り立ちがわかる。
・材料の強さの原因がわかる。
セミナープログラム
1.はじめに
i.レオロジーとは?
ii.会社の仕事とレオロジー
iii.人の感覚とレオロジー
iv.レオロジーを理解するために
2.レオロジーを始める前に、
i.数学的な事項の確認から
ii.物理的に考えるときに必要となること
3.レオロジーのはじめの一歩
i.レオロジーのはじめの一歩
ii.弾性体の力学的な刺激と応答
iii.力学モデルについて
4.物質の物理を理解するために
i.レオロジーで扱う関数について
ii.微積分について
iii.物理モデルを物質の物理とつなげるために
5.物理化学として物質を見直すと
i.物質の三態について
ii.流れるということは?
iii.応力の由来は?
6.粘弾性の基礎
i.粘性と弾性についての再確認
ii.粘弾性のモデル化
iii.少しだけ実事象に近づけると
7.全体のまとめ
【質疑応答】
セミナー講師
ソフトマターデザインラボ合同会社 代表社員(元東亞合成株式会社 名古屋クリエイシオR&Dセンター) 佐々木 裕 氏
セミナー受講料
【1名の場合】49,500円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。
主催者
開催場所
全国