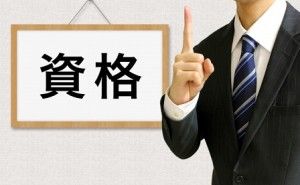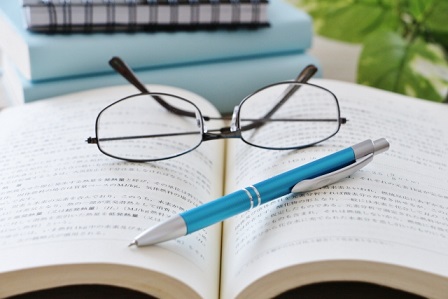
1.内容が明確に伝わる文を書く
【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。
令和4年度の技術士第二次試験の受験申込受付期間は同年4月1日(金)~4月18日(月)です。
受験生は、申込書の一つとして「業務内容の詳細」を提出します。そのため、提出期日までに業務内容の詳細を書いてそれを提出する必要があります。そこで、今回の記事は、「業務内容の詳細の中で書く文」をテーマにした内容です。業務内容の詳細を書くときに注意する文の解説です。文の書き方に注意することで、自分が担当した業務の内容を試験官に明確に伝えることができます。
弊社:ジェイタプコでは、技術文書の書き方のセミナーなどで、「内容が明確に伝わる文の書き方」として、以下の6つの書き方を解説しています。
- 具体的な文を書く
- 意味が明確な文を書く
- 能動態の文を書く
- 短い文を書く
- 肯定文を書く
- 文法を守って文を書く
この中から、業務内容の詳細を書くときに特に注意する文の書き方を3つ選び3回に分けて解説します。3つの書き方とは、具体的な文を書く、能動態の文を書く、短い文を書くです。今回は、「具体的な文を書く」について解説します。
技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら⇒【特集】技術士第二次試験対策
口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。
こちらの記事も読まれています⇒「業務内容の詳細」の書き方のポイント(技術士第二次試験対策を例に)
2.具体的な文を書く
これは、文を読んだときその内容が頭の中に浮かんでくるような具体的な文を書くことです。以下の文を読み比べてください。
Ⅰ:解決策として画期的なシステムを提案し実施した。
Ⅱ:解決策としてAI(人口知能)を取り入れたシステムを提案し実施した。
Ⅰの文を読んでも内容が頭の中に浮かんできません。「画期的なシステム」が何を意味するのかがわからないからです。このため、文の内容が明確に伝わりません。これをⅡの文のように、「AI(人口知能)を取り入れたシステム」と具体的に書くことで文の内容が頭の中に浮かんできます。頭の中に浮かんでくることでこの文の内容が明確に伝わります。
具体的な数字を入れて文を書くことも具体的な文を書くことです。これは、「定量的な文を書く」と言い換えることができます。
Ⅲ:今回の提案で、提案前に比べて橋梁の維持管理費を大幅に削減することができた。
Ⅳ:今回の提案で、提案前に比べて橋梁の維持管理費を約3割削減することができた。
Ⅲの文では、「大幅に削減することができた」と書いてあるため削減の規模が頭の中に浮かんできません。これをⅣの文のように「約3割削減することができた」と具体的に書くことでこの文の内容が頭の中に浮かんできます。
Ⅱや...