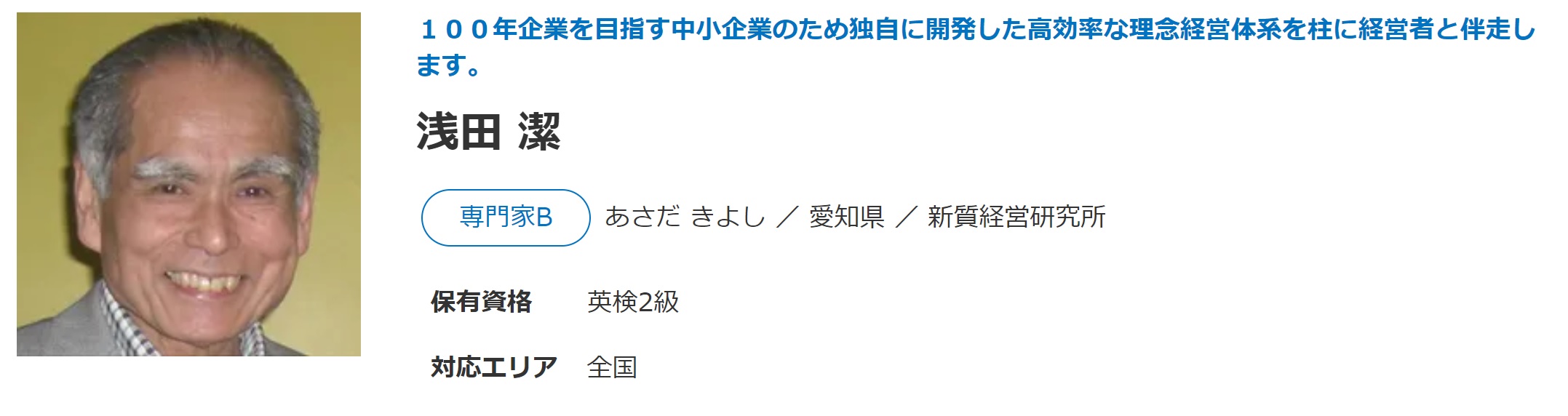新QC七つ道具 アロー・ダイヤグラム法の使い方が無料でお読みいただけます!
◆アロー・ダイヤグラム法とは
ネットワーク理論をプロジェクトの計画・立案・管理に適用したPERT(Program Evaluation and Review Technique)やCPM(Critical Path Method)のネットワーク図を用いた日程の計画と管理の方法を「アロー・ダイヤグラム法」と呼び、この効果は、アロー・ダイヤグラム法のアウトプットにより複雑な計画の全貌を細大漏らさず一望できるところにあり“余法をもって代え難い”ところです。
◆日程計画とその進捗管理に“アロー・ダイヤグラム法”を用いることによって出来ること
- きめの細かい計画が立てられる。
- 計画の段階での案の練り直しがしやすいので、最適な計画を立てることができる。
- 実施段階に入ってからの状況の変化、計画の変更などに対する対処がしやすい。
- 一部の作業の遅れが全体の計画に及ぼす影響についての正確な情報が迅速に得られるので、対応策が早く打てる。
- 計画の規模が大きくなればなるほど、効率よく管理できる。
- 進捗管理の重点が明確になるので、効率よく管理できる。
アロー・ダイヤグラム法の使い方について、ものづくりドットコム 登録専門家の浅田 潔氏が詳しく解説しています。
【アロー・ダイヤグラム法の使い方 連載記事】
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その1) 挑戦計画立案
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その2) 基本ステップ
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その3) 管理点抽出
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その4) 作業抽出・カード作成
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その5) 作成
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その6) 作業日数
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その7) 結合点日程
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その8) 日程短縮検討
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その9) 効用
- アロー・ダイヤグラム法の使い方(その10) 事例
【執筆者紹介】
<<この連載を利用の際のお願い>>
ここで紹介する連載の転載は固くお断りします。少人数での個人的な勉強会での使用のみに限定してください。
◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!