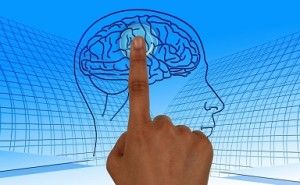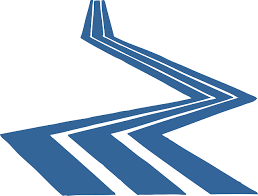
1. 何を楽と感じるか、苦労と感じるか
人が成長する時に楽をした方がよいのか、苦労した方がよいのか色々な意見があると思います。しかし、これはどちらでも構わないし、その二択にはあまり意味がないと思います。成長するためには目標に対する行動や継続的な努力が必要です。それを「楽」と感じるか「苦労」と感じるかは人それぞれ主観的です。客観的ではありません。しかし、傾向として現状と同じことの繰り返しでは成長はなく、それなりに負荷をかけなければ成長につながることは難しいでしょう。結果的に多くの人が成長のためには苦労したり、大変なことだと思うでしょう。
では苦労することはよいことか?と問われた場合、それも意味がありません。成長につながる負荷を苦労と感じることと、成長に無関係なことで苦労を感じることは全くの別です。まさに無駄骨になります。このことは楽をすることはよいことか?という問いに対しても同じことが言えます。この問いは「楽」が何を指しているか示していません。日々の鍛練を楽と感じる人もいれば、サボることを楽と感じる人もいます。
何かを成し遂げるにはそれなりに知識や経験、時間が必要なことがあります。これが正しい成長過程を進んでいれば、楽と感じるか苦労と感じるかはあまり問題ではありません。
2. 自信と経験、同じことを経験しても、考え方で異なる
何か新しいことをはじめる時は不安があります。成功するかもしれません、失敗するかもしれません。もしこれが一度成功したことを繰り返す時は自信をもって進めることができます。それは仕事でも他のことでも同様です。成功した経験を多く重ねるうちに自分の中に自信が育っていきます。
なにか一つの分野で成功を経験すれば、他のはじめての分野でも「出来るかもしれない」と思うことができます。自信を身につけるにはこのような成功経験を繰り返すことが有効です。この成功経験は決して大きいものである必要はありません。小さな成功でもよいのです。多くの人が難なくできることでも、自分の成功経験としてよいのです。「時間通りに集合する」という当たり前のことでも成功経験とすれば、自信の成長につなげることができます。
では、失敗ばかりを経験していた場合はどうでしょうか。これには2パターンあります。失敗を繰り返すうちに自信をなくすパターンと、失敗を経験の1つとしてとらえて、前進するパターンです。同じことを経験しても、なぜ考え方が異なるのでしょうか。両者を分けるものは何でしょうか。
これは本人以外にも周囲の人の反応も影響しているでしょう。励まされるか、非難されるかで変わります。ですが、最も重要なのは本人です。いわゆる打たれ弱い人と打たれ強い人とも言われます。続けられる人は単なる意志の強さだけでなく、目標に対する責任、一つの失敗をしっかり振返り改善しているか、色々な検証を行っているか、小さな変化に気付けるかなどの行動をともないます。この場合、行動は経験と同じ働きとなり自信につながっていきます。
3. 影響力、周りの人を動かす影響力とは
影響力のある人とはどのような人でしょう。その人の言葉や提案に周りの人が自発的に考えたり行動したりすることでしょう。嫌々ではないことが重要です。他には自然とその人の話題(ゴシップではありません)や意識する人が多くなることでしょう。影響力のある人はまるで太陽のように周りの人を明るくすることもあります。これはその人自身が元気に生き生きとしていることが大事です。そのような態度は見た目にも自信に溢れています。
影響力を身につけるのに重要なことは誠実さ、責任、行動力などです。口先だけの人には人はついていきません。誠実さの元になるのは自分で決めたことをキチンと実行することです。これも小さなことから始めると良いです。誰も見ていなくても有言実行を実施するのです。責任はcommitmentです。自分の意思決定、選択、行動に対して「自分が行ったこと」とすることです。誰かに言われた、影響されたときは責任とはなりません。そうせざるを得ない状況もありますが、基本は、責任は自分がとります。誠実さ、責任、行動力がともなわなければ周りの人を動かす影響力は乏しいものになるでしょう。
◆連載記事紹介:ものづくりドットコムの人気連載記事をまとめたページはこちら!