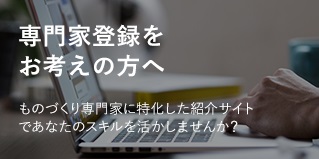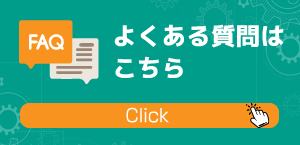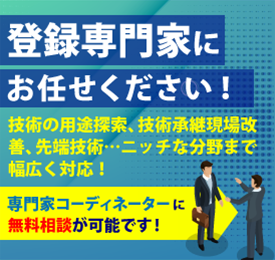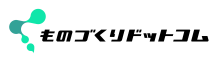制御因子間に交互作用がある場合の対処法も教えて下さい。
制御因子間の交互作用は調べることに意味がないからです。
一方、制御因子と誤差因子の交互作用を調べることはロバストネスのレベルを調べる意味があるからです。
|
|
追加です。何らかの方法により、制御因子間に交互作用が発見されたとしたら、その結果はあてにならないので、信用出来ない。再度計画し直しです、
これを田口玄一は、交互作用を割り付ける無駄、交互作用が出たら、役に立たないという意味で、さらに無駄と言われました。品質工学の素晴らしい考え方です。
|
|
品質工学のコンサルティングをしております対馬と申します。
パラメータ設計においては、制御因子間に交互作用があるまま実験を行なうと、実験結果の精度が悪くなり、再現性が期待できなくなります。 特に、化学系では交互作用が複雑に絡み合っている場合が多く、その交互作用をなくすためのテクニックが必須であり、実験をうまく行なうための最大のポイントであると言っても過言ではありません。
以下に、ご質問のうち、制御因子間に交互作用がある場合の対処法(交互作用を生じさせない方法)について説明します。
(1)スライディングによる水準設定
熱処理の実験において、因子Aは処理温度、因子Bは処理時間とします。
温度を上げれば時間が短く、温度が低ければ時間を長くするというのが明白であるにもかかわらず、AとBの水準を独立に設定すれば、明らかにまずい組合せができてしまいます。
このような場合には、温度Aの水準によって、時間Bの水準の値を表1のように、範囲をずらして設定するのが合理的です。 このような水準設定法をスライディングといいます。
温度と時間を含めて、圧力と温度、圧力と時間の関係など、エネルギー量が影響するものについては、スライディングによる水準設定が必要です。
表1 Aの水準別のBの水準値
B1 B2 B3
A1(160℃) 5分 10分 15分
A2(200℃) 4分 8分 12分
A3(240℃) 3分 6分 10分
(2) 従属関係がある場合の水準設定
ある因子がどの因子に作用するかで、水準値の設定が変わってきます。
発泡の実験において、表1.1のように、因子Aは発泡剤の量、因子Bはセル調整剤の量とする実験は間違いです。
セル調整剤Bは、発泡剤で発泡したセルを安定化させるものですから、発泡剤Aに作用します。 したがって、表2.2に示すように、セル調整剤Bは発泡剤Aに対する比率にして、水準を設定しなければなりません。
× 表2.1 交互作用が生じる水準値設定
水準1 水準2 水準3
A:発泡剤の量 2g 5g 8g B:セル調整剤の量 0.2g 1.0g 2.4g ↓
〇 表2.2 交互作用が生じない水準値設定
水準1 水準2 水準3
A:発泡剤の量 2g 5g 8g B:発泡剤量に対する
セル調整剤の比率 0.1 0.2 0.3
交互作用が複雑に絡み合っている場合でも、ある因子の働き・役割、それがどの因子に作用するかといった知見があれば、交互作用を生じさせない実験を組むことができますので、参考にしてください。
以 上
|
|
化粧品業界で品質工学を活用している深澤です。
ご質問のような疑問は、よくあることです。
私も実験計画法の通信講座を担当した際、交互作用について、説明すべきか、説明は不要か悩みました。
品質工学で主に使用している混合型直交表のL18に「交互作用」が基本的に割り付けることができません。この直交表だけ説明するなら、交互作用のことは説明不要ですが、基本的な部分で動特性のSN比を計算する際には、交互作用が関係します。
つまり、入出力の関係が、誤差因子と交互作用を持っていて、SN比最大化は交互作用の利用ということになります。
しかし、内側直交表で制御因子間の交互作用は考えない、というのはどうも直感的に解釈できません。
そもそも、要因配置実験では交互作用が重要な解析対象でした。フィッシャーの実験計画法でも、交互作用があるから配置の検討が必要だという解釈でした。
実際に実験してみると、いたるところに交互作用が出てきます。そのことが再現性を悪化させ、実験自体が役に立たないものになってしまうのです。
特に制御因子にエネルギー的パラメータ(温度とか電力とかなど)を組み込んで実験すると、実験NO.毎に実験の場がエネルギー的等価性を確保できないため、交互作用の塊になります。それを回避すべく「水準ずらし」により、エネルギー等価性を確保してきました。田口先生の「タイルの実験」などは交互作用問題といっても良いでしょう。
交互作用がないのではなく、交互作用があるから、交互作用効果が出ないように実験を配置することが重要です。
しかし、パラメータが離散型(分類データの場合)には積極的に交互作用を利用することになります。
また、A×Bの交互作用効果を計算するとき、ABの変動からAの変動とBの変動を差し引いて、交互作用変動を求めます。つまり、交互作用変動は「残渣変動」といえるのです。要因効果は主効果の組み合わせで表現する方が、妥当性が高いでしょう。結果の解釈を分かりやすくすることが「汎用性」があるともいえます。
交互作用が出ないように実験を配置することができれば、結果の頑健性も向上し、結果の汎用性も上がるでしょう。
交互作用は難物です。この交互作用に果敢に取り組むことで、より高いレベルの解釈が可能になります。ラオタンも頑張ってください。検討を陰ながらお祈りしています。
|
|
制御因子間の交互作用がある立場でどうしたら良いか?考えてみよう。
宮川先生の「品質を獲得する技術」の第5章に以下の説明がある。
直交表を使用するシーンで,交互作用を積極的に求めるという立場をとったときはどうであろう。
直交表に誤差要因を割り付ける原因究明の実験では,交互作用の割り付けに意味がある。予期せぬ不具合は誤差要因の組み合わせ効果で発生することが少なくないからである。しかし,制御因子については話が違う。制御因子については要因効果の関数形,パターンに興味があり,それが技術的ノウハウになる。制御因子間の交互作用についても,そのパターンを知ることが大事である。そのための解析は,少数の自由度を持つ単純な構造を見いだすことである。たとえば,2つの量的因子間の1次×1次の交互作用というのは単純な構造である。これを求めるにはあらかじめ比較的自由度の大きい交互作用を観測し,そこから単純構造を抽出するという流れになる。しかし,2^k型直交表に割り付けられる交互作用の自由度はもともと1だから,それ以上の次元の縮約はできない。つまり,交互作用解析自体が存在しないといってよい。
このように考えてくると,直交表実験で制御因子間の交互作用を割り付けることはムダだという結論になる。制御因子間の交互作用を求めるならば,別な配置(例えば要因配置実験)が必要である。
品質工学の立場は,早く良い結果を導き出すことであり,その際に重視するのは主効果で表現できるモデルである。交互作用効果に興味があるのなら,別の検討を行うことを推奨する。
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら