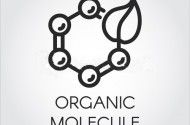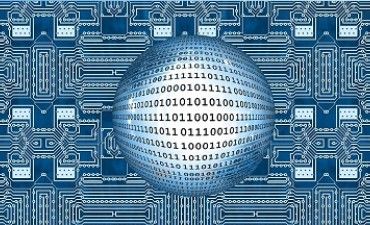★最新のエレクトロクロミック材料の動向、及び調光ガラスなどの応用展開について紹介!
★また、エレクトロクロミック材料(メタロ超分子ポリマー)に関して、その特性とデバイス化について詳細に紹介!
セミナー趣旨
電気を流すと色が変わる材料はエレクトロクロミック材料と呼ばれる。本講演では、最新のエレクトロクロミック材料の動向、及び調光ガラスなどの応用展開について紹介する。また、講演者が研究を進めているエレクトロクロミック材料(メタロ超分子ポリマー)に関して、その特性とデバイス化について詳細に紹介する。
【講演キーワード】
調光、遮光、遮熱、省エネ、エレクトロクロミック
【講演のポイント】
エレクトロクロミック(EC)調光ガラスは窓自体が調光機能を有する次世代窓として注目されている。EC材料とデバイスに関する基礎から最近の研究動向を紹介する。また、具体例として講演者が開発しているメタロ超分子ポリマーも紹介する。
習得できる知識
エレクトロクロミック材料及びデバイスの知識と最新開発動向
メタロ超分子ポリマーのエレクトロクロミック特性
メタロ超分子ポリマーを用いたエレクトロクロミックデバイスの詳細
セミナープログラム
1.エレクトロクロミック材料とは
1.1 動作原理
1.2 他の表示材料(液晶、有機EL)との違い
2.代表的なエレクトロクロミック材料とその特性の比較
2.1 無機系エレクトロクロミック材料
2.2 有機系エレクトロクロミック材料
2.3 金属錯体系エレクトロクロミック材料
2.4 金属ナノ粒子系エレクトロクロミック材料
3.調光ガラスなどの応用展開の現状
3.1 調光ガラスへの応用
3.2 防眩ミラーへの応用
3.3 不揮発性表示素子への応用
4.世界動向
5.エレクトロクロミックデバイスの課題と将来展望
6.メタロ超分子ポリマーのエレクトロクロミック特性
6.1 動作原理
6.2 エレクトロクロミック特性
6.3 他のエレクトロクロミック材料との比較
6.4 マルチカラーエレクトロクロミズム
6.5 黒色エレクトロクロミズム
6.6 近赤外エレクトロクロミズム
6.7 2次元ナノシート
7.メタロ超分子ポリマーを用いたエレクトロクロミックデバイス
7.1 デバイス作製法
7.2 低電圧駆動化
7.3 メモリ性
7.4 エレクトロクロミックスーパーキャパシタ
8.実用化への取り組み
【質疑応答】
セミナー講師
国立研究開発法人物質・材料研究機構 グループリーダー 博士(工学) 樋口 昌芳 氏
【受賞】
発明協会 令和4年度全国発明表彰 未来創造発明賞 受賞
セミナー受講料
【1名の場合】39,600円(税込、資料作成費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
受講料
39,600円(税込)/人
前に見たセミナー
関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
RO膜(逆浸透膜)とは?RO膜による水処理の仕組み、メリット・デメリットをわかりやすく解説
【目次】 水は私たちの生活に欠かせない資源であり、その水質は健康や環境に大きな影響を与えます。近年、世界中で水資源の不足... -
IGBTとは?原理と仕組み、その利用法をわかりやすく解説
【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、... -
熱雑音とは?知っておくべき基礎知識と対策法をわかりやすく解説
【目次】 電子機器や通信システムにおいて、熱雑音は避けて通れない問題です。特に、精密な測定や高性能なデバイスを求める現代においてその... -
SiC MOSFETとは?仕組みや利用における利点と欠点について解説
【目次】 シリコンカーバイド(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、次世代のパワーエレクト...