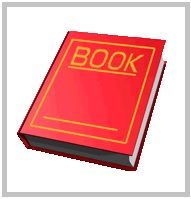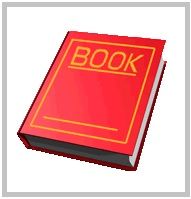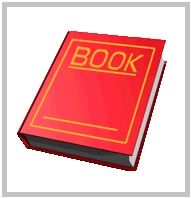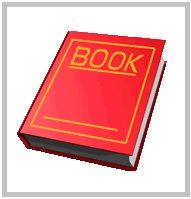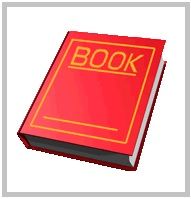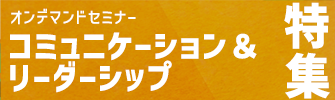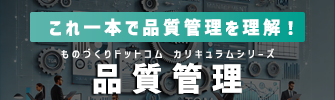【医療機器】プロセスバリデーションの具体的な計画書・記録書・報告書の作成セミナー
【プロセスバリデーションの手順書配布】
>> プロセスバリデーションでは、計画書、記録書、報告書を揃える必要がある。
いったいどのような手順でプロセスバリデーションを実施し、記録を作成すれば良いのか
【ここがポイント】
■ 医療機器におけるプロセスバリデーション
■ プロセスバリデーションの実施方法、記録方法
■ プロセスバリデーション報告書作成
■ 短時間で要点を理解!!
本セミナーでは、プロセスバリデーション手順書を配布し、
具体的な計画書、記録書、報告書の作成方法を分かりやすく解説します。
■特典■
このセミナーはアーカイブ付きです。セミナー終了後も繰り返しの視聴学習が可能です。
Live受講に加えて、アーカイブでも以下の期間視聴できます。
視聴期間:10営業日(開催後、1週間程度の編集期間後に視聴開始予定)
※プロセスバリデーション手順書配布
セミナー趣旨
プロセスバリデーションを実施することによって、当該プロセスが恒常的に規格に合格した製品を通常の操作条件において生産できることを高度に保証することが必要です。
そのためには、管理する変動要因を適切に把握しなければなりません。
適格性評価で確立した実生産の条件で製品を製造し、様々なアクションレベル、それを含んだ標準操作手順書(SOP)の内容を確認し、チャレンジテストの繰り返しでよりプロセスの保証を高めなければなりません。
製品やプロセスのデータは、プロセスのアウトプットが規格内である通常の変動範囲が決まるように解析されるべきです。
通常の変動範囲を知ることで、コントロールされた状態か特定のアウトプットを製造できるのに一定の許容範囲にあるかが明確になります。
変動幅を軽減し管理すると高度な品質保証につながります。
プロセスバリデーションの実施手順は、試験法バリデーション、洗浄バリデーション、滅菌バリデーション等に対しても同様に応用することが出来ます。
また、プロセスバリデーションを実施する前に構造設備の適格性評価を実施する必要があります。
適格性評価が実施された構造設備を用いて、実生産スケールで実際に製造してみることが必要です。
さらに、手技(手作業)で実施している特殊工程においては、作業者の適格性評価が必要です。
その際にバリデーションを実施するロット数(N)は、統計的手法を用いて適切に決定する必要があります。
プロセスバリデーションでは、計画書、記録書、報告書を揃える必要があります。
いったいどのような手順でプロセスバリデーションを実施し、記録を作成すれば良いのでしょうか。
本セミナーでは、プロセスバリデーション手順書を配布し、具体的な計画書、記録書、報告書の作成方法を分かりやすく解説します。
セミナープログラム
1. はじめに
・バリデーションの考え方の誕生
・バリデーションとベリフィケーションの違い
2. 適格性評価とは
・適格性とは(Fitness for purpose)
・構造設備における適格性評価(Qualification)とプロセスバリデーション
・適格性評価(Qualification)とは
・適格性評価とバリデーションのステージ(PIC/S GMP Annex 15)
・適格性評価(Qualification)
・据付時適格性評価(IQ)
・運転時適格性評価(OQ)
・性能適格性評価(PQ)
・FDAプロセスウィンドウ
3. バリデーションとは
・医薬におけるバリデーションとは
(FDA Guidelines on General Principles of Process Validation – 1987)
・プロセスバリデーション(PV)
・PIC/S GMP Annex 15 ~バリデーション実施対象~
・コンピュータ化システムとは
・GMPにおけるコンピュータ化システム
・GMPにおけるハードとソフト
・GMPハードとGMPソフト
・CSV、適格性評価、バリデーションの関係
・適格性評価とプロセスバリデーション
4. プロセスバリデーションとは
・プロセスバリデーション
・ISO-13485 目次
・7 製品実現
7.5 製造およびサービスの提供 7.5.6 製造およびサービス提供に関するプロセスバリデーション
・820.75 プロセスバリデーション
・820.75 プロセスバリデーションの要点
・カシメ工程のプロセスバリデーション
5. 工程設計について
・量産移行とプロセスバリデーションと設計バリデーションの関係
・生産技術部門の役割
・工程設計関連手順書の関連性
・工程設計とバリデーションの関係
・製造工程におけるリスクマネジメントについて
・リスクマネジメント関連文書
・リスクマネジメント組織について
□質疑応答□
※内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
セミナー講師
【関連の活動など】
日本PDA 第9回年会併催シンポジウム 21 CFR Part 11その現状と展望
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 基礎研究部会主催(東京)
東京大学大学院医学系研究科 臨床試験データ管理学講座などにて多数講演。など
セミナー受講料
※お申込みと同時にS&T会員登録をさせていただきます(E-mail案内登録とは異なります)。
33,000円
※当セミナーは、定価のみでの販売となります。
受講について
Zoom配信の受講方法・接続確認
- 本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。PCやスマホ・タブレッドなどからご視聴・学習することができます。
- 申込み受理の連絡メールに、視聴用URLに関する連絡事項を記載しております。
- 事前に「Zoom」のインストール(または、ブラウザから参加)可能か、接続可能か等をご確認ください。
- セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
- セミナー中、講師へのご質問が可能です。
- 以下のテストミーティングより接続とマイク/スピーカーの出力・入力を事前にご確認いただいたうえで、お申込みください。
≫ テストミーティングはこちら
配布資料
- PDFテキスト(印刷可)
受講料
33,000円(税込)/人