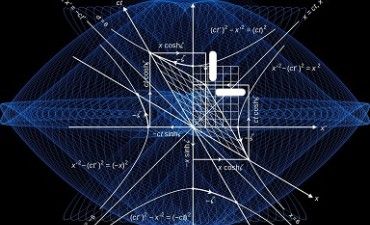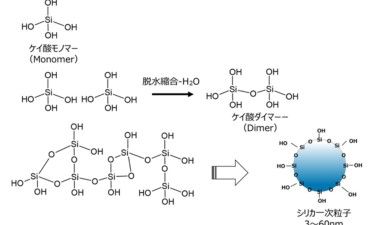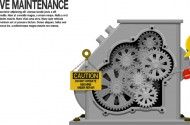
連続晶析プロセスの条件設定、スケールアップ事例とトラブル対策
★温度制御・溶媒制御のポイント、結晶品質の一貫性確保、連続運転時の安定化対策(詰まり・汚れの管理)
日時
【Live配信】2025年5月8日(木)10:00~16:45
【アーカイブ(録画)配信】2025年5月19日(月)まで申込受付(視聴期間:5月19日~5月29日まで)
セミナープログラム
【10:00~11:30】
【第1部】 連続晶析中の核生成・結晶成長メカニズムと結晶化不良対策
大阪公立大学大学院 工学研究科 物質化学生命系専攻 准教授 堀江 孝史 氏
【講座主旨】
近年,高効率化,環境負荷低減の要求の高まりによって,晶析プロセスの連続化に期待が寄せられている。本講演では,連続晶析の概要を理解するために,晶析の基本からモデリング手法を中心に解説を行う。最初に,連続化によって得られる一般的なメリットと,設計において考慮すべきポイントを紹介する。次に,晶析プロセスへの展開を見据え,連続式反応器のモデリング手法について反応工学的な見地から説明する。晶析の基本やメカニズム,さらに,結晶成長や物質移動の速度過程について触れた後,連続晶析装置,とくに完全混合槽型連続晶析装置(MSMPR)を用いた際の晶析プロセスの解析手順について解説を行う。最後に,ポピュレーションバランスモデルについて詳しく説明をした後,連続式管型晶析装置へ適用した事例として振動流バッフル反応器の結果を紹介する。
【講座内容】
1.連続化の背景
2.連続式反応器モデル
3.晶析の基本
4.核化現象と結晶成長
5.ΔL法則
6.核化速度と結晶成長速度
7.連続式晶析装置
8.モーメント変換
9.ポピュレーションバランスモデル
10.2次核化を抑制する方法
11.連続式管型晶析装置の事例紹介
【質疑応答】
【12:15~13:45】
【第2部】 連続フロー晶析で粒子群特性を制御するための操作上の留意点
東京農工大学大学院 工学研究院 教授 滝山 博志 氏
【講座主旨】
分離精製や粒子群製造の目的で「再沈」や「再結晶」とも呼ばれる晶析操作が行われている。ところがその操作の少しの違いが、最終製品や生産性に影響を与える。例えば、純度、多形、粒径分布など粒子群特性に関わる課題である。結晶性物質を製造する上で最も基本的な概念は、結晶化現象をつかさどる推進力「過飽和」である。槽型装置を用いた回分晶析では、結晶化とともに過飽和が消費されるため、それを補うように、冷却や非(貧)溶媒添加などを調整しながら行う必要がある。しかし、連続晶析の場合、極端に表現すると定常状態となっていれば、経時的な調整操作は必要としない。この考え方が重要で、連続晶析であれば、結晶粒子群の安定製造が可能となる理由がそこにある。ただし、例え連続晶析であっても過飽和を推進力とする結晶化現象の理解は必須で、その関係を正確に把握できていれば、より精密な特性制御が可能となる。
このセミナーでは、連続フロー晶析がなぜ注目されるのか、その本質を解説するとともに、結晶粒子群の特性制御について、過飽和の観点から紹介し、どうやれば、結晶粒子群に所望の特性を作り込めるのかに答えながら、晶析の操作戦略について解説したい。
【講座内容】
1.「再沈」「再結晶」と晶析との接点
1.1 有機合成と工業晶析操作との接点とは
1.2 晶析操作によって作り込める製品特性とは
1.3 連続フロー製造が注目される理由とは
2.晶析操作の工夫による結晶粒子群の特性制御
2.1 結晶化の推進力と固液平衡
2.2 核発生と成長
3.今すぐ役立つ結晶粒子群を創るためのポイント
3.1 安定した結晶を思い通りに創りたい場合
3.2 結晶の純度を思い通りに良くしたい場合
4.思い通りに結晶を創るための晶析操作設計法
4.1 晶析操作設計の留意点
4.2 結晶粒子群の連続フロー製造での留意点
5.まとめ
【質疑応答】
---------------------------------------
◆講師プロフィール◆
専門分野:晶析・異相界面工学
学位:博士(工学)
略歴・活動・著書など:
平成 4年3月 東京工業大学 総合理工学研究科 修了 博士(工学)
平成14年8月 東京農工大学 工学部 化学システム工学科 助教授
平成23年4月 東京農工大学 大学院 工学研究院 教授
平成27~31年度 化学工学会・材料界面部会・晶析技術分科会代表
平成23年~現在 EFCE Working Party on Crystallization Guest Member
平成30~令和6 日本海水学会 編集担当理事
令和2~令和6 分離技術会副会長
令和6~ 日本海水学会 副会長
令和6~ 分離技術会会長
【14:00~15:30】
【第3部】 連続晶析の適用とスケールアップでの留意点
東京農工大学大学院 工学研究院 教授 滝山 博志 氏
【講座主旨】
晶析は化学工学あるいはプロセス化学の分野であり、有機合成の分野で“再沈”=“結晶化”=“晶析”と理解されることは希である。晶析にはFrom Molecules to Crystallizersと題する教科書があるように、常にスケールアップが意識される研究分野である。結晶を構成する分子やイオンを、規則正しく配列させるというミクロな現象を、温度や流速というマクロな操作変数で制御するためには、なぜ結晶化が生じ、なぜ結晶化が変化するのかというメカニズムの理解は必須である。
連続晶析でも回分晶析と同様、特異な固体物性をどう発現させるのかというProduct Innovationと、結晶粒子群をどの様に製造するのかというProcess Innovationをシームレスにつなぐことができれば、結晶性物質の製造について革新的な技術が創成されることが期待できる。
このセミナーでは従来の槽型晶析装置と連続フロー晶析装置の特徴を比較しながら、スケールアップの考え方も紹介し、なぜ連続フローへのパラダイムシフトが起きているかを解説する。そして、反応晶析や非(貧)溶媒添加晶析などの晶析法毎に、どうやれば望ましい結晶粒子群を製造できるのか、その操作戦略を立てるためのコツを解説する。
【講座内容】
1.結晶粒子群の連続フロー製造へのパラダイムシフトとその理由
1.1 国内外の研究動向
1.2 工業晶析に要求される粒子群特性
2.連続晶析装置の基本的考え方
2.1 粒子群の数値解析
2.2 様々な連続晶析装置
3.連続フロー晶析と晶析法の組み合わせ
3.1 槽型晶析装置の限界
3.2 反応晶析の連続フロー化
3.3 非(貧)溶媒添加晶析の連続フロー化
3.4 高剪断場を組み合わせた連続フロー晶析
4.晶析のスケールアップ
5.まとめ
【質疑応答】
【15:45~16:45】
【第4部】 連続晶析による結晶多形及び粒子径の制御法開発
UBE(株) 医薬事業部 CDMO営業部 営業統括グループ 主席部員 宮坂 充 氏
【講座主旨】
近年、規制当局により連続生産に関するガイドラインが整備されるなど、フロー合成や連続生産を利用した医薬品製造法の開発が注目を集めている。UBEでも、フロー合成や連続生産を取り入れた医薬品原薬・中間体製造に関わる研究開発を行ってきた。
医薬品原薬の結晶多形や粒度分布は、製剤中での安定性やバイオアベイラビリティに影響を及ぼすため重要な物性である。しかしながら、工業的な製造スケールにおいて、これらの物性を精密に制御する事は困難である。特に熱力学的に不安定な準安定晶や微細な結晶を再現性良く、工業的に得る事は非常に難易度が高い。本講座では、UBEでのフロー合成・連続生産の取り組みについて紹介するとともに、連続晶析法を取り入れた自社開発医薬品の結晶多形制御法や精密な粒子径制御法の開発事例について報告する。
【講座内容】
1.UBEの医薬事業の紹介
1.1 UBEにおける医薬事業
1.2 UBEのフロー合成・連続生産に関する取り組み
2.自社開発医薬品の連続晶析事例
2.1 自社開発医薬品におけるバッチ晶析の課題
2.2 プラグフロー晶析を準安定晶の粒度分布制御法開発
2.3 テイラーボルテックス晶析を利用した結晶多形制御法開発
2.4 今後の展望
【質疑応答】
---------------------------------------
◆講師プロフィール◆
専門分野:有機化学、プロセス化学
学位:博士(工学)
略歴・活動・著書など:
・2011年 3月 大阪大学大学院工学研究科 博士後期課程修了
・2011年 4月 宇部興産株式会社(現UBE株式会社)
研究開発本部 有機化学研究所
・2017年 4月 医薬事業部 医薬研究所
・2017年10月 医薬事業部CMC開発部
・2023年 4月 医薬事業部 医薬品営業部
・2024年12月 医薬事業部 CDMO営業部 現在に至る
セミナー講師
【第1部】大阪公立大学大学院 工学研究科 物質化学生命系専攻 准教授 堀江 孝史 氏
【第2・3部】東京農工大学大学院 工学研究院 教授 滝山 博志 氏
【第4部】UBE(株) 医薬事業部 CDMO営業部 営業統括グループ 主席部員 宮坂 充 氏
セミナー受講料
1名につき66,000円(消費税込/資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき60,500円〕
受講について
■ Live配信セミナーの視聴環境について
- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
- 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test - 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
- セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
- Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
- Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。
- パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
- セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。 - 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
- 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、
録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。 - 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
- 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- Zoomのグループにパスワードを設定しています。
- 部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
■Live配信・アーカイブ配信セミナーの受講について
- 開催前日または配信開始日までに視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時またはアーカイブ配信開始日に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。 - 出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。 - 開催前日または配信開始日までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日または配信開始日までに資料の到着が間に合わないことがあります。 - 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
- 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
- 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- アーカイブ配信セミナーの視聴期間は延長しませんので、視聴期間内にご視聴ください。
申込締日: 2025/05/19
受講料
66,000円(税込)/人