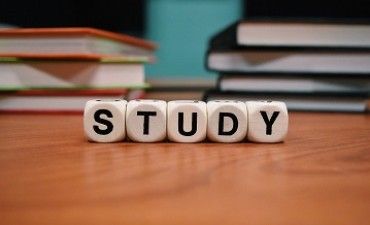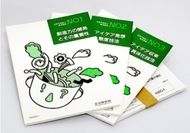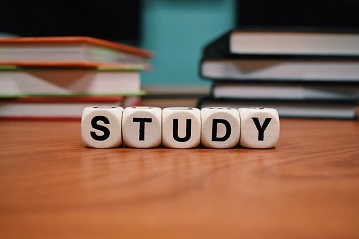
先日、電車でシートに座りながら、解説書を読んでいる方がいました。本当はいけないのでしょうが、解説書を広げて読まれていたので、自然とタイトルが目に入ってきました。そのタイトルは、ISOマネジメントシステム関係の書類でした。そして、驚いたのは、その解説書がボロボロで、側面も手垢で黒ずんでいる状態で、相当「読み込んでいる」感が伝わってきたのです。また、ページを開くたび、視線を上に上げ、頭の中で何かを考えたり、思い出したりしながら読んでいるのです。きっと、何度もなんども書籍を読み返し、色々と考えたり思ったりしていたのでしょう。私は、心の中で「頑張って下さい!」とつぶやいてしまいました。
自分の頭の中で考えること。本当に大切なことです。これこそ、リスキリングを促進する際の姿勢です。今回は、「自ら考える人財」を育てる、思考のスイッチについてのお話です。
1.「Why」思考で、マネジメントシステムを構築する
自ら考える人財を育てるにはwhy思考をまわす。組織全体で、取り組みたい思考法です。私は、ISOマネジメントシステムの認証取得支援にたずさわり、多くの組織や業種にお世話になった覚えがあります。そして、各組織の最初のハードルが、要求事項の理解なのですが、組織によって理解の方法が次の2タイプに分かれます。
- 1つ目は、「なぜ?このような要求事項が定められているのか?」
- 2つ目は、「何をどうすれば要求事項に適合するのか?」
前者は「Why」を意識し、後者は「what」と「How to」を意識した要求事項の理解方法です。この意識の違いは、マネジメントシステムの構築/運用に影響する意識です。もう、お解りですね。「Why」思考で、マネジメントシステムを構築した方が、高いパフォーマンスをたたき出します。私達の脳は、Aという事象とBという事象の違い(ギャップ)を認識した時、「なぜ?」という思考スイッチが入ります。そして、このスイッチが入ることで、私達の脳は「考えはじめる」のです。また、逆の流れもあります。
私達の脳は、「なぜ?」と自ら問いかけることで、その違いを見つけ出そうとするのです。こちらも、観察力や洞察力が働きはじめ、思考プロセスが流れはじめます。「Why」は、考えはじめる、観察力や洞察力を磨くためのきっかけなのです。
2.「why思考」と「What/How to」
これを比べると「What/How to」は、手っ取り早く答えを手に入れることができるので、効率的で「why思考」は、時間がかかり非効率的です。よって、多くの組織では「What/How to」を取り入れたり、組織文化として根付いているようです。
ところが、「What/How to」思考には、弱みが隠れているのです。
「What/How to」思考が根付いた組織では、自ら考えることが少ないため、自律性に欠...