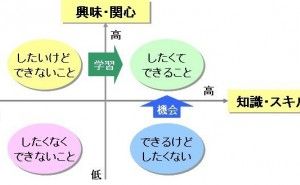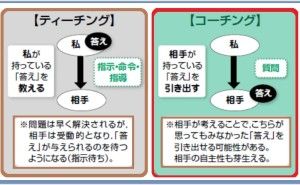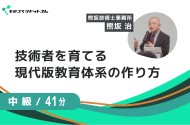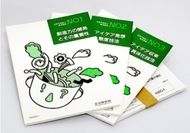自律型チームと依存型チームのどちらを育てるべきかと問われたのなら、どのリーダーも「自律型」と答えることでしょう。でも、このようなチームを育てるとき、まず何から始めたら良いのか分からない、というリーダーが少なくなりません。もし、あなたが自律型チームを育て上げたいのなら、最初にすることは「ビジョン作り」です。今回は、自律型チームを育てるビジョン作りについて、おはなしします。
最初に手がけることは、明確なビジョン作りから。いい加減なビジョンでは依存型チームが育ちます。「イメージを強く描くと、そのイメージと同じことが起きたとき、あなたは何かを意識します。」私が、NLP(神経言語プログラミング)を習っているときに、教わったことです。
1. 無意識から意識へ
例えば、1日5箱のタバコを吸っていた人が、NLPを使ったコーチングで、1箱までに減らすことが出来たそうです。この人は、タバコを吸うという行動を抑制しなければならなかったので、タバコを吸う直前の行動、つまり「タバコを箱から指で摘まむ」イメージを強く脳内に描くことを繰り返し訓練したのです。すると、タバコを吸おうとして指で摘まむ瞬間、その人には特別な意識が脳内に湧き上がり「あっ、タバコ吸うのを止めよう。」といった想いが、まるでスイッチが入ったかのように意識の中に出現し、タバコを吸う行動を自ら抑制したそうです。
また、面白いことに、他の人から貰ったタバコは止められなかったため、最後の一箱分が残ってしまったそうです。これは、事前に「自らタバコの箱を持って指を使って取り出す。」イメージが描かれていたため、他人から貰う事については行動抑制に繋がらなかったそうです。
後にこの人は、「タバコを手に持つ」というイメージを強く描くようにしたところ、完全にタバコを止められたそうです。おそらくこの人は、無意識にタバコを吸う行動をしていたと思うのですが、強いイメージを脳内に描く訓練をすることによって、無意識の行動から「意識する行動」に変えることに成功したのでしょう。
2. ビジョンとは
イメージとは、強く描けば描くほど、私達の行動を変えます。そして、このイメージを「ビジョン」と言っているコーチもいます。私達が組織で行動するに当たり、ビジョンはとても大切です。ちなみにビジョンとは「目を閉じたとき、目蓋の裏側に明確に描き出すことができるシーン」を指します。
このビジョンがあるからこそ、組織のメンバーが自律をして考え・行動を起こせるようになるのです。もし、ビジョンが弱い状態だと、事あるごとに上司や先輩の判断を仰ぐ依存型組織になってしまうでしょう。私が、組織やチームのビジョンを描くときに気を付けていることは、2つあります。
1つは「わかることば、できることば」で文書化することです。中には、難しい言葉や、得体の知れない横文字を使ってビジョンを文書化しているチームなどもありますが、メンバーが描くビジョンを聞いてみると、具体性に欠けることが多くあります。ビジョンの文書化は、理解を促進するような、ことば選びが必要でしょう。あとひとつは、描いたビジョンを体で表現することです。これは、目標達成した時のことを描いた場合、そのビジョンの状態を体で表現する、といった感じです。
3. 「いま」を体現する
もし、目標を達成したとき、メンバー全員で拍手をしながら笑顔で喜んでいる、というビジョンが描かれたのなら、それを「いま」やってみるということです。また、ゴールを目指すに当たっては、様々な課題や苦労もあると思います。この時の状態も「いま」体で表現する。そして、その悪い状態から脱したときの状態も、「いま」表現してみることも大切です。
私達の脳は、視覚・聴覚・情動覚が主な感覚です。そして、この3つの感覚を刺激するビジョンは最強です。視覚は、目蓋の裏側に描く映像。聴覚は、文書化(言葉で言い表した)したビジョン。そして、情動覚は、みらいに起こる出来事を「いま」体験する。
- ビジョンを描くことは、組織やチームが成長し、目...