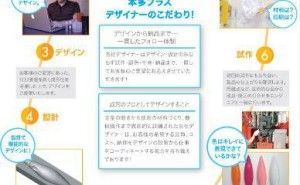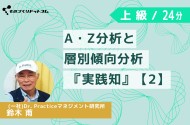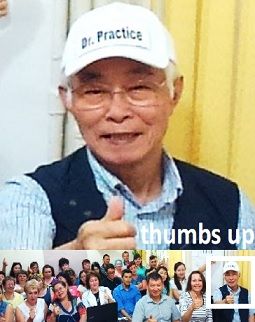IPI(Integrated Process Innovation)は、筆者が海外と国内で長年に亘ってものづくりの改善・革新を指導してきた経験から編み出した戦略的かつ実践的な方法です。ここでのプロセスは、製造プロセスのみならず経営戦略策定などのビジネスプロセスも対象にします。
「技法解説コーナー」で「IPI・・・マクロの目とミクロの目で革新を実現する法」について書きました。その中で、IPIについては“ほんの概略”を紹介しただけで、実践的技法の例(QC7つ道具ではなく8つ道具)が主でしたので、今回は、IPIの基本である「マクロの目」で見た発想と「ミクロの目」で見た挑戦で、経営を革新し飛躍的な発展を遂げている地方のおとうふやさんの事例を考察してみることとします。
相模屋とうふをご存知でしょうか。戦後、未亡人になったおかみさんが始めた町のおとうふ屋さんを、2代目が設備近代化によって平成16年頃には年商30億の中堅企業(おとうふ屋としては大企業)に発展させていました。しかしながら、原料価格が高騰する中で「おとうふ」という商品の性格から販売価格は上げられず、経営は楽でありませんでした。2代目社長の娘婿である鳥越氏は、雪印に営業マンとして勤めていて前代未聞の「食中毒事件」で奈落の底を経験し、事件が一段落した平成14年に相模屋に入社して、現場でゼロから「とうふづくり」の修行に励みました。鳥越氏はまたコスト削減など必死に経営改善にも取組みましたが、先行きの明るい見通しは立ちませんでした。
鳥越氏は3代目を継ぐにあたって「これまでの延長線上に未来はない」と覚悟を決め、業界の実態を俯瞰し(マクロの目でみて)、夢のある自社像を描いて取組むべき課題を設定することにしました。すると、①おとうふは日常品で安定した需要があり、メインは‘木綿’と‘絹’で昔から変っていない。②後継者がいないとか採算が取れないということで廃業するおとうふ屋が増えて供給能力が落ちてきている。
そして(日々の忙殺から離れて)タカのように空から眺めると、将来に亘って“安定したマーケットが広がっている”。にもかかわらず今のとうふ業界は、このマーケットに対応できる状況にない。という状況が見えてきました。ならば相模屋がこのマーケットに対応できるようになろう。理想の工場を作って「美味しいおとうふを安定して生産・供給できる会社」をつくるのだと、鳥越氏の目の前に明るい未来が広がってきました。
空から降りて工程を見ていくと、とうふを切るところまでは機械化できているがパック詰めは機械化できず手作業によっています。切った後で水に入れて冷まし手でパックに入れるのですが、注意深く作業してもどうしても雑菌が入るため賞味期限が短くなり、旨味が水に溶け出して味も落ちてしまいます。課題は「パック詰めを機械化する」ことでした。これが出来れば美味しい賞味期限の長いとうふが生産でき、賞味期限が長くなることで販路も広がり、日々の需要のバラツキにも対応できます。
ところが、このアイデアに対する関係者の反応は・・・ 「出来ない」「ムリ、ムリ」の大合唱でした。この「ムリ、ムリ」に対し鳥越社長は、ひとつひとつ「なぜムリなのか」「どうしたら出来るか」について対話を通じて解決策を見出し、平成15年7月についに業界一の第三工場を稼動させるに至ります。しかしこれが“壮絶な戦い”の始りでした。最大のお客さまから、「あなた達のレベルではこの大きさの工場は管理できません。いったい何を考えているんですか?これでは生産をお任せすることは出来ません」と、厳しく1000箇所もの改善点を指摘されたのです。
それから日夜、現場を「ミクロの目でみて」徹底的に改善を重ねてベストの状態(筆者の実践的品質向上のひとつである「ベスト・コンディション」と同類)にすることに成功し、1ヵ月後には、ついにお客様から「もう任せたよ」と言って貰うことができました。こうして、誰にもマネの出来ない「世界一のおとうふ製造工場(第三工場)」が完成しました。この工場は、他の会社が真似しようとしても出来るものではありません。
この革新により、年商は平成16年30億が平成22年120億と6年間で4倍になり、「美味しいおとうふを安定して生産・供給できる会社」の夢を実現させることが出来たと同時に、これまでのとうふ業界に革命を...