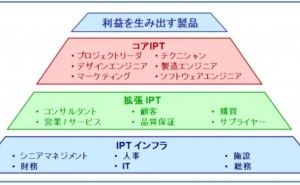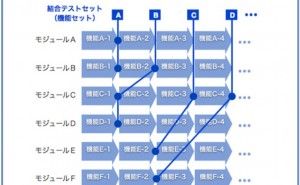◆ 技術者の創造性とモチベーションを引き出すマネジメントとは
失われた20年の間に日本はグローバルな競争力を著しく低下させてしまいました.日本の賃金は1997年を100%としたときに90%まで低下しました.海外では米国が116%,英国でも127%と伸びている中での一人負けのような状況にショックを受けました.
ここ数年,海外の学会に何度か参加しましたが,米国の機械学会ASMEが主催する国際大会や品質に関する国際大会QMODでも日本の存在感がとても低く,かつての技術立国,品質立国の面影をまったく感じなくなってしまいました.最近,日本人のノーベル賞受賞が続いてまいますが,ノーベル賞は過去の取り組みの結果であり,現在の日本の取り組みが将来の日本を決めてしまうのです.日本は食料も資源も海外に依存している国です.輸出産業で世界に貢献できなくなったときに今の生活を維持できるとは思えません.
日本の課題を解決する方法は既に過去の日本の中にあると言われています.一橋大学の名誉教授の野中博士は,かつての日本と今のグローバル企業にはあるが,今の日本企業からは消えてしまった”共感”がイノベーションの本質と仰っています.かつてのホンダの本田社長やソニーの井深社長は技術者と同じ目線で厚く技術論を交わしていたのです.技術の前に上下関係はありません.日本の品質管理の先駆者である西堀先生は創造性を育てる方法について,以下のように仰っています.
【創造性を育てる方法】
- 技術者が思いついたアイデアや提案を育てもしない先に評価してはいけない。
- 発案者は、ほかの人から見ればまるで馬鹿ではないかと思われる。よってそのアイデアは誰かが育てなければならない。
- 育てる者は、大物でなければならない。
- アイデアをモノにするには、馬鹿と大物がそろわなければならない。
実は大物はアイデアの中身を知る必要がないのです.ロジックではなく第六感で”何か知らんがそう感じる”が大切,ロジックばかりで批判ばかりやってるインテリではアイデアは育たない,と西堀先生が仰っています.
ロジックの世界で生きてきた方々には信じられないことかもしれませんが,7層方式のLIMDOW-MOが正にノンロジックの意思決定が成功の原動力だったのです.光ディスクの専門家のほぼ全員が大反対する中で,技術を知らない日立マクセルのたった一人の経営者が,おそらくは第六感で,こいつは面白いと感じたのだと思います.あの即断即決の意思決定が信頼につながり,我々技術者のモチベーションを飛躍的に高める効果が成功の原動力の1つでした.もし責任回避のスタンラリーで数か月も費やしていたら間違いなく事業化は失敗していました.
技術者の創造性とモチベーションを引き出すマネジメントを取り戻すこと,それが今後の日本企業,特に製造業がグローバルに生き残っていくために第一に必要なことである...