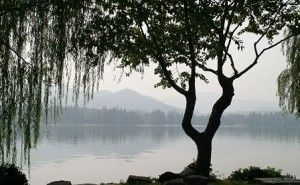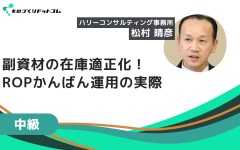コスト削減の一環として、請負を活用する工場が多くなっています (ここでの請負とは、自社工場内における他社や子会社への作業移管を指します)。
活用方法としては、原料・製品の入出庫/管理、検査/包装工程などの単純作業から、生産ラインすべてお任せしている工場まであります。
任せる範囲が増えるほど、製造コストにおける請負費用が大きくなりますから、いかに管理するかが重要になってきます。
私は請負会社に対する管理ポイントは3つあると考えています。
- 偽装請負といわれないか
- 請負費用は適正か
- 請負会社を育成しているか
1から3へいくほど、管理レベルは上がります。皆様の会社ではいかがでしょうか?請負会社に任せきりなら管理放棄ですね。請負会社の多くは、発注会社の言う通りしかやりませんから、発注会社がリーダーシップをとって管理していくべきです。
請負会社の管理ポイントの3つが押さえられたなら、より高いレベルを目指しましょう。皆さんは請負会社はどうあるべきだと思いますか? 目指す姿をイメージした上で、徐々に管理レベルを上げていきます。
私にとって請負会社の目指すべき姿は「仕事量に応じて最適人員化するマネジメント力がある」ことだと考えています(もちろん安全、品質、納期は前提です)。請負会社の所長や班長が「今日は出荷量が○tonだから3人はA倉庫、 4人がB倉庫ね」と日々柔軟に人員を変えていくのが理想です。
ところが、実際は仕事量に関係なく、最大の仕事量をこなせる人員を常時張り付かせるわけですからコストが高くなります。
しかし実は、コスト高の原因は発注会社にあります。
- 発注会社の仕事量の確定が遅い(当日にならないと分からない)から、どんな要求でも対応できるように請負会社が最大人員で固定している。
- 請負会社の作業範囲と権限が明確でなく、発注会社の指示待ちになっている(これはコンプライアンス違反の恐れもある)。
- 標準作業方法に対する標準時間を把握しておらず、請負会社...