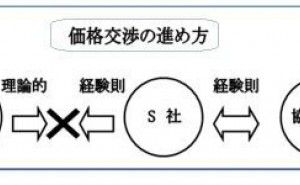【ものづくり現場の人財育成 連載目次】
前回のその1に続いて、クリーン化を通じて私が考えていることをお話します。
ものづくり企業の場合、製品品質は現場で作り込まれます。
設計品質がどんなに良くても、それを具現化する現場のものづくり基盤がしっかりしていないと、製品品質は確保できません。その先には利益が確保出来ないだけでなく、客先や市場のお客様に迷惑をかけ、クレーム、更には信頼も損ねることにも繋がります。その対応のために多くの費用がかかり、企業の存続さえ怪しくなる場合もあります。
ものづくり企業では、ゴミなどによる品質低下に苦労されているところも多いでしょう。食品業界でも異物の混入や商品の回収など時々耳にします。このようなことが起きないよう、現場の品質の作り込みレベルを向上させたい。このクリーン化の考え方、および活動はクリーンルームを保有している企業だけではなく多方面、広範囲の分野で共通の課題だと考えています。
しかしこれだけでは具体的に何をすればよいのか抽象的です。私はクリーン化や人財育成、安全は相互に密接な関係があると考えていて、セミナーや講演会などではその部分も大きなテーマとして時間をかけて説明しています。
この中にある人財育成ですが正しくは人材と書きます。でも私は25年くらい前から人財という字を使うようになりました。その理由は人は材料扱いをしているうちは育たない、財産として扱うことで成長が期待できる。でも真剣に育てないと、やり方次第で、成長しないばかりか減ってしまうこともあります。
戦国時代に武田信玄という武将がいました。“人は石垣、人は城”と言って人づくりに焦点を当てていました。全国でも珍しい城を持たなかった武将です。この人づくりについて興味があるところです。
人財育成は真剣勝負です。
最近は、この人財との表現を対外的にも、或いは正式文書でも用いる企業が増えました。社内で教育等を担当する部門では、人財という字を使った部門や課の名称に使うところも出て来ていると聞いています。こうなると、人を育てることにその企業の思いを感じます。
参考に辞書を見てみると、人材:一般的な表記。企業活動上での人的な「材料」との考えを示したもの。人財:技能等を習得し、長期にわたり企業を支え利益をもたらしてきた人のこと。とあります。こうなると人財の方を使いたくなります。また、その文字に相応しい人づくりをしたいと思います。
“人財育成は会社がすること”と考えがちです。一方的な押し付けになっていると感じることもあります。そして人事部門や経営側の立派な教育のロードマップが出来上がります。でもその通りに人は育っているでしょうか。
教育の一環として外部教育や研修に参加させる。社員にしてみれば、自分にその機会が与えられたと感じる人もいるでしょう。しかし、教育の機会を得られるよりも、会社で毎日同じ業務をこなしている方が楽だ。そしてこちらの都合も聞かずに行かされた、という被害者意識を持つ人がいるかもしれません。その先入観を持ちながらでは取り組む姿勢にも差が出るでしょう。
管理、監督者からは「せっかく教育に出してやったのになかなか伸びない」という一方的な見方やぼやきも出るでしょう。その時点で、その人...