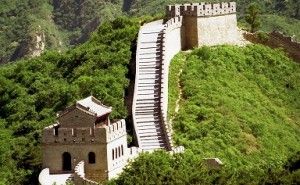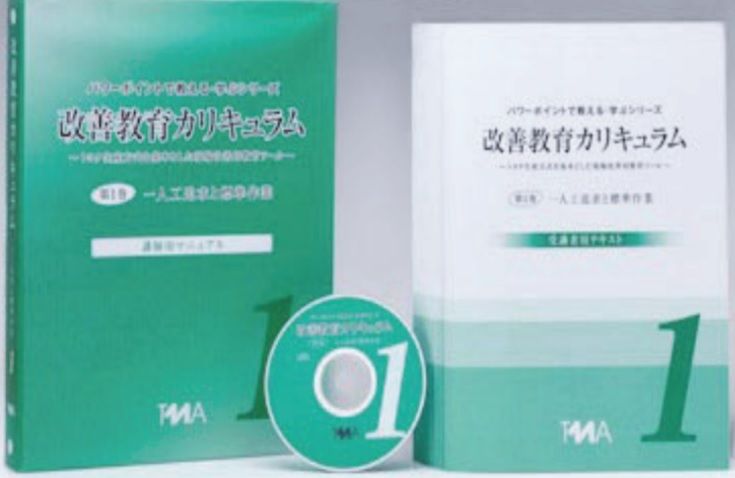「伝えたいことが、きちんと伝わっていますか」
現在のものづくりの現場では、情報の取り扱いがより重要となっています。この記事では、より正確に、より速く、より効率よく伝えるための実践方法についてお伝えします。
【見える化 連載目次】
- 1. 情報の取り扱いで競争力をつける
- 2. 見えないことの方が大切なことがある
- 3. 職場の全員がコスト意識を持つには
- 4. 問題を顕在化してトップが改善の現場に参加
- 5. 管理板から活動管理板へ
- 6. 納期遵守率を向上させるには
- 7. 生産計画変更と現場
- 8. 生産現場の生産管理板
- 9. 変化の状況を客観的に見る
1. 掲示板の本質を理解し活用する
工場内をその会社の人たちと一緒に巡回をする時は、現場だけでなく掲示板も確認していきます。この掲示板、企業の個性が出てきますので5Sと合わせて、その企業の管理レベルを伺うことができます。単なる周知徹底するものは別として、掲示物は多くの場合が、管理する側に立ったものが多いようです。しかし結果の羅列をグラフ化したものがほとんどで、そこには結果に対するコメントやこれらに対する指示内容など、残念ながら肝心な「伝えたいこと」が入っていません。
しかし管理する側(発信側)の方では、このような掲示物を工場内に示すことが、一つの儀式になっているようで、現場の人たち(受信側)がそれらを見て納得して、次はどのようなアクションをとるべきか考えている様には思えません。一見パソコンから出力された印刷物は、大変綺麗(きれい)で見やすいものですが、見る側(受信側)にとってはその内容までを覗(のぞ)き込むようなことは滅多にないようです。
そもそも何の目的で掲示物は、あのように現場に貼り出してあるのでしょうか。それは発信側が、その結果を元に現場でアクションが行われることを期待しているからでしょう。ではそれらの掲示物は、作成側が伝えたいことをキチンと伝わるようにした内容でしょうか。どうも私には疑問です。掲示物を作成した人は、伝えたい本人ではなく部下に任せて作らせ、後でホンのちょっと目を通しただけで済ましていることがあります。それらには、責任者の確認印がないことがほとんどです。毎月決まりきったことがグラフに記入されているだけでは、現場の人たちが関心を持つはずがありません。掲示を見る側は「今月も同じことが掲示してあるなあ」というくらいの意識しかなく、作成した内容が活かされることがない掲示になってしまいます。
2. アクションに結び付ける情報を伝える
数値やグラフを羅列しただけのデータでは、受信側は何をしたらよいかというアクションが、なかなか頭に浮かんできません。プリンタから排出された単なるデータではなく、何をすべきかという情報に咀嚼(そしゃく)して、アクションに結び付ける着火剤にすべきです。情報は「情が報われる」と書くように、一方向ではなく双方向のやり取りが込められています。ですから管理グラフや掲示物は、発信側の「思い」が、受信側に確実に伝わることが必要です。それは、発信側の作り方に問題があると思います。
受信側の人たちが、そこからアクションを起こし、狙った目標に対して結果を出すことが求められるはずです。相手に伝わってこそ、はじめて伝えたことになるのです。
最近はメールのやり取りが普通になって、手紙や葉書などの手書きによるものが、極端に少なくなってきています。今では絵手紙は非常に希少価値になり、相手からも喜ばれるようになってきました。筆者も時々筆と絵の具と使って、絵手紙を出しますが、下手でも貰(もら)った相手は嬉(うれ)しいようです。書き手側のことよりも、受け取る側のことを考える「心の余裕」を持ちたいものです。
3. 労を惜しまず作成する
管理グラフや掲示物は折角(せっかく)手間暇をかけて作成するのですから、できればそれ以上の効果や結果を導き出したいものです。では何が欠けているのでしょうか?
先に述べたように、その情報を活用する現場の人たちの立場に立ったものになっているかということです。知りたい、使いたいと思わせるように、発信側で工夫を重ね伝わるようにすべきです。その手間を惜しんでいては、返って来るものはほんの僅(わず)かになってしまうのです。そこで筆者が行っていることを、いくつか紹介します。
- タイトルの文字はできるだけ大きくし、グラフとの間の空白には、責任者がこの結果で何をしてほしいか、できれば1行で収まるよう簡潔に指示コメントを書く。
これを書くことで、そのグラフや掲示物の価値が全く変わり、生きたものになってきます。この少しの労力は絶対に惜しまないことです。 - いつまでも古い物を貼り出すことのないように、貼り出し期限も明確にしておく。
ビールと一緒で、情報が新鮮であることも大切です。古い物は見向きされなくなり、全体の掲示も見なくなっていきます。いつも感心を持たせることが必要です。 - 白黒ではなく、できるだけカラーの写真やイラストを入れる。白黒だけなら、マーカーで一本ラインを引くだけでも、オヤッ!と思わせます。
- 作成者を明確にする。それには、責任者のサインやハンコ、データ印がありますが、一番効果があるのは直筆のサインのようです。見た人は、一覧表に「いつ、誰」と...