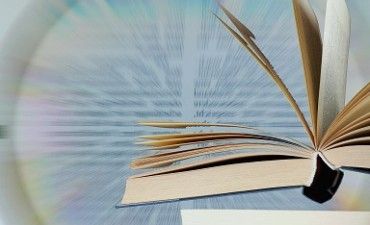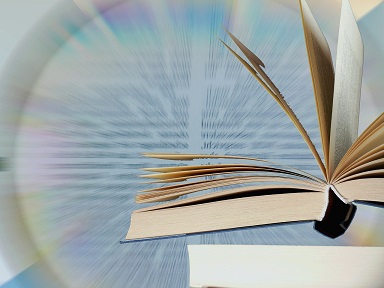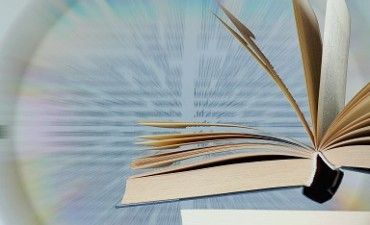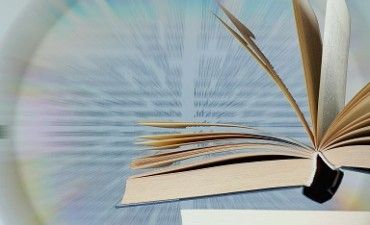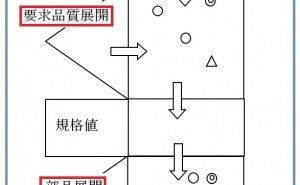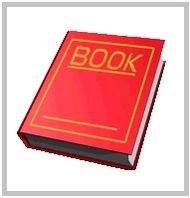(2) 顧客提供価値の仮説形成
次に社会における自身の技術の意義や役割を捉えたうえで、実際にどのような顧客に対して価値を提供できるのかを具体的に考える。研究開発部門が陥りがちなのは、自身は技術開発に関する取り組みを行えばよく、実際の用途については事業部が行うことであると、人任せにしてしまうことである。しかし研究開発の時点からどのような顧客にどのような価値を提供できるのかを想定しておくことで、むしろ多くのヒントを得られるようになる。具体的には、以下の手順で進めるのがよい。
① 技術から導かれる機能を想定する
技術原理そのものは、ユーザにとって実はあまり重要ではない。例えば蓄電池で言えば、材料として鉛を使おうがニッケルを使おうがリチウムを使おうが、少なくともエンドユーザからは関心が向けられない。重要なのは、その蓄電池が連続で何時間使えるかとか、エネルギー効率はどの程度であるかとか、何千回充放電できるか、などの機能である。ユーザから価値を認めてもらうには、技術原理から機能に「翻訳」する必要がある。その技術があることで、どのような機能を実現できるのかを考える。
② 機能に基づいて顧客をターゲッティングする
機能が分かれば、どのようなプレーヤーがその機能で喜ぶのかについて考えることができる。蓄電池の例で言えば、五千回の充放電ができるという機能を、どのようなプレーヤーがどのようなシーンで価値を感じるのかを想定するのである。生産財であれば具体的な顧客名を挙げて検討するのもよいだろう。生活者向けであれば、具体的にどのような人物であるのかというイメージをメンバーで共有するのもよい。
③ 想定されるターゲットのニーズや業務への貢献を考える
新技術である場合、顧客自身も気づいていないニーズということもある。従来からの業務プロセスや生活習慣の改善というよりは、まったく新しいプロセスや習慣の提案になる場合などである。潜在的なニーズを掘り起こす可能性を検討したい。...