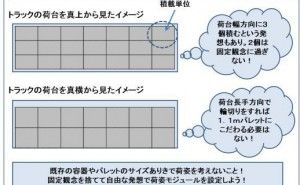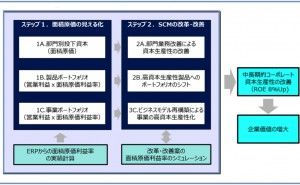1.サービスレベルアグリーメント
◆ 業務変更時の対応
荷主と物流事業者、工場の製造工程と物流部門など、それぞれの間でどのような物流サービスを実施するのかきちんと決めていますでしょうか。これがしっかりしていないと、後になって何かと問題が発生してしまいます。そこで、会社間ではサービスレベルアグリーメント(SLA)を、工場内では標準作業書を作成する必要があります。まずSLAについて考えてみましょう。これは契約ですから業務開始前に決定し、両社で合意のサインを取り交わす必要性が求められます。荷主と物流事業者間でしっかりとした契約が結ばれていないケースが多く、強い立場の方が有利となる事象が発生しやすいのです。
たまに耳にするのですが「ついでだから○○もやってほしい」と荷主から要請されるケースがあるようです。これに対して、物流事業者側も「あまり追加工数も発生しないことだし、引き受けても問題ないだろう」といった対応をしてしまうことがあります。ところが、この小さな追加業務の積み重ねが、結果として大きな負担になることが考えられます。いくつもの荷主からちょっとずつ追加業務が来た結果、一人区増えてしまったというようなことが発生するのです。
この追加業務に追加金額を徴収していなければ、会社の利益を圧迫することは目に見えています。在庫数量のFAXを一枚送付するという業務だけでも本来なら価格を設定し、荷主から徴収しなければならないことは当然のことでしょう。
しかし遠慮があるのか、前述のようなことを言われたのか、あるいは単に面倒くさいのか、追加業務について見積もりを出さないことがあります。海外では契約社会ですから、このようなことはあり得ないことでしょうが、このあたりの曖昧(あいまい)さが日本社会なのかもしれません。
新規契約の場合は請け負う業務の内容を、追加業務があった時にはその業務についてSLAに列記しましょう。そしてそれ以外の業務が発生した際は「別途見積もる」という一言を加えておくのです。業務は追加だけではなく、やり方が変更になることもあるでしょう。その際もSLAの記載を変更します。これは条件変更に伴う契約の変更ということになります。
フェアなやり方は条件変更でコストが上がれば価格を上げ、コストが下がれば価格を下げるという方法でしょう。物流でよくある条件変更は物流量の変更です。契約当初の条件よりも物流量が増えれば単位コストが下がる可能性があり、その場合には価格を下げます。また、物流量が当初の条件より減れば単位コストが上がる可能性がありますので、価格を上げることになるでしょう。もちろん、物流量が何パーセントを超えて増減した場合は、価格を変えるということを契約当初に合意しておくことが望ましいと思われます。

2.標準作業書
◆ 標準作業書にサービス水準を明記する
工場内物流も物流事業者と同様の考え方を持つべきでしょう。つまり自分たちが提供するサービスについて標準作業書に明記するのです。製造工程で当たり前に作られている標準作業書ですが、物流となると作成率がぐっと低くなる傾向にあります。しかし、いつも申し上げている通り、品質の高い物流作業を高効率で実施するためには、標準作業の設定が不可欠ですので、物流部門は自部門の行う各物流作業の標準作業を設定し、それを標準作業書に落とし込むことを心掛けましょう。そして標準作業の中にうたわれた物流サービス水準について、きちんとお客様である製造に提示することが望ましいでしょう。
標準作業が設定されていないと、作業者によって仕事の仕方が異なる可能性が出てきます。結果的に製造に対するサービス水準に差が出てしまい、これでは品質や効率を一定に保つことができず、製造品質にさえ影響を及ぼす可能性だってあるのです。
標準作業書には品質のポイント、こなすべき標準時間、安全上のポイントなどが記されることになります。それを実行すれば、現行考えられる最高の物流作業ができることになるのです。
さて物流事業者におけるSLA(サービスレベルアグリーメント)や工場内物流における標準作業書ですが、これはある意味でバイブル的存在で、それがなければ仕事をしてはならないくらいの位置づけであるべきだと思います。
確かにこれらのドキュメントを作成するためには時間を要します。しかし、それについて手を抜くということは仕事の手抜きと同様、あってはならないことだと考えるべきではないでしょうか。しっかりと時間を取り、自分たちも、そして顧客側も納得のいくものを作り上げることが重要です。
これらのドキュメントが全くない場合、初めのうちは少々大変かもしれませんが、一回作成すればあとはそれを改定する形で作成できるため、だんだんと作成時間は効率化されていくことでしょう。
ではこれからSLAの内容のポイントについて一緒に考えていきましょう。最初に仕事の受注についてみていきましょう。SLAには次のようなポイントを織り込むとよいでしょう。
- 顧客からの受注時刻:例えば前日午後3時を受注締切とする、それを超えた場合は翌日分とするか追加価格を徴収する、といった決め事を明記しましょう。
- 緊急オーダー:納入リードタイムが〇〇時間を下回るオーダーについては価格を2倍とする、などメリハリある契約内容にするとよいでしょう。

3.物流量・到着時刻・貨物損傷
◆ 物流SLA記載事項のポイント
物流契約にあたり、最もキーとなる物流量の記載について考えてみましょう。
◉日当たり物流量は〇〇トンとする。この量が2倍を超えて上回るか、2分の1を超えて下回った場合は価格について見直すものとする。
このように物流量の変動は物流事業者に大きな影響を及ぼすため、一定の制約を設けておくことが望ましいと思われます。 これを日当たりで定義するのか、月当たりで決めるのかは当事者間で定めればよいでしょう。また物流量に応じた価格をあらかじめ定め、それをマトリックスにして表示しておくことも一つではないでしょうか。
次に、到着時刻についてはどうでしょうか。
◉あらかじめ定めておいた時刻を30分以上遅れ、あるいは早まった場合は○○する。
このように物流の命であるデリバリーについては、きちんとした定めが必要だと思います。この「○○」の部分ですが、当事者間で取り決めをしておきましょう。指定した貨物が届かずに顧客に影響を与えてしまった場合は、賠償を求められることもあり得ます。その時のルールはあらかじめ決定しておくべきでしょう。高額の賠償を求められた場合には会社の存続にも...