
3. SCM構築が進まない最大の理由:SCM構築の必要性と目的が曖昧
理由2:本質的な意味においてSCMの目的とは何かが曖昧
4. SCM目的が不明確な多くのプロジェクト
5. そもそも本質的な意味においてSCMの目的とは何か
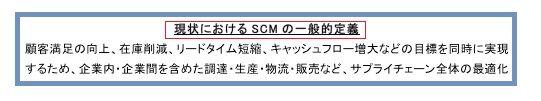

TOP



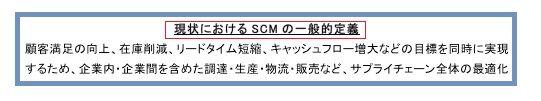


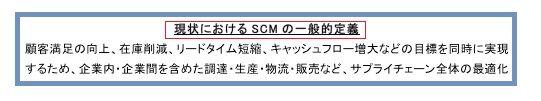

続きを読むには・・・

現在記事
「サプライチェーンマネジメント」(工業調査会)を私が出版したのは1998年ですが、それ以来日本国内のジャストインタイムやロジスティクスの分野で実績のある...
「サプライチェーンマネジメント」(工業調査会)を私が出版したのは1998年ですが、それ以来日本国内のジャストインタイムやロジスティクスの分野で実績のある...
生産財メーカーの今後の経営モデルをサプライチェーンの原理原則からみると、熟練をベースとした人間系と情報技術(ICT)の融合といえます。「BTB(ビジネス...
生産財メーカーの今後の経営モデルをサプライチェーンの原理原則からみると、熟練をベースとした人間系と情報技術(ICT)の融合といえます。「BTB(ビジネス...
企業活動は製造業であれ、流通サービス業であれ、物の流れであるサプライチェーンを経ながら付加価値が加わっていき、このことをバリューチェ...
企業活動は製造業であれ、流通サービス業であれ、物の流れであるサプライチェーンを経ながら付加価値が加わっていき、このことをバリューチェ...
物流作業は物流部門だけが行うとは限りません。製造部門が自ら物流業務を行うこともあるはずで...
物流作業は物流部門だけが行うとは限りません。製造部門が自ら物流業務を行うこともあるはずで...
◆ 物流価格値上げと契約解除申請 サプライチェーンにとって、コスト増と輸送能力の減少は大きな問題です。この要因としてドライバー不足...
◆ 物流価格値上げと契約解除申請 サプライチェーンにとって、コスト増と輸送能力の減少は大きな問題です。この要因としてドライバー不足...
前回のその2:物流に表れる 生産・調達・営業の結果に続いて解説します。 1. 物流部門からの情報発信 物流は往々にして何らかの行動の結果と...
前回のその2:物流に表れる 生産・調達・営業の結果に続いて解説します。 1. 物流部門からの情報発信 物流は往々にして何らかの行動の結果と...
コヒーレント・コンサルティング
SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします


