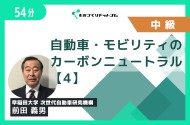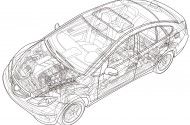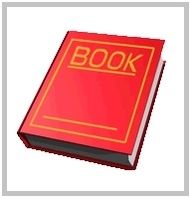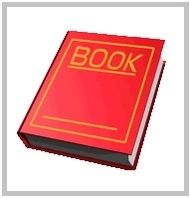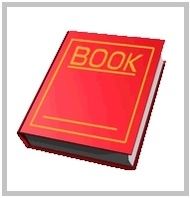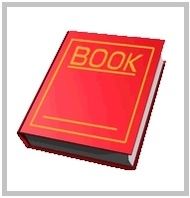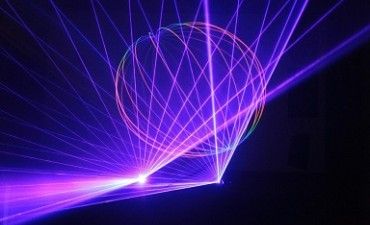【中止】自動車の電動化に向けた中国の取組みと国際社会への示唆
★電動化は自動車産業が生き残る唯一の道!
★中国の躍進は「他山の石」!
※本セミナーはZoomを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。
セミナー趣旨
脱炭素化は世界的な流れである。日本も中国も例外ではない。実現するには、あらゆる分野での脱化石燃料化が不可欠である。当然、石油系内燃機関車(ICEV)から新エネルギー自動車(NEV:電気車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)と水素燃料電池車(FCV)を含む。ハイブリッド車(HV)を含まない)への転換という自動車の電動化は避けて通れない。
日本は、2019年ノーベル化学賞受賞者吉野彰氏が指摘したように、リチウムイオン電池等部品や素材の技術開発で世界をリードしているが、最終製品の産業化や国際競争力の面で立ち遅れてしまった。それに対し、中国は、脱炭素社会の実現と自動車「大国」から「強国」への変貌の一環として、NEVの産業育成と普及を戦略的に推進し、世界最大のNEV生産・販売国、保有国、輸出国に成長した。2023年1~6月では、中国の自動車輸出台数が日本を抜いて世界首位となった。決して偶然ではない。内燃機関車が退場していくにつれ、業界の勢力図が大きく変わり、中国が自動車強国になるのはもはや夢物語ではなくなりつつある。
本講座では、なぜ中国が自動車の電動化で世界の先頭に躍り出られたのか、NEV世界一の座を維持し続けられるのか、世界全体の自動車電動化、日本を含む先進国中心の自動車業界にどのような影響を与えうるのかなどについて解説する。また、NEV普及に不可欠な充電・電池交換インフラの整備、NEVによる脱炭素化に欠かせない化石電源から再生可能エネルギー電源への転換、車載用蓄電池に必要なリチウム資源確保、車載用蓄電池の安定供給、使用済み蓄電池の処理(回収・再利用・リサイクル)等の万国共通の課題に向けた中国の取組みも紹介する。合わせて、米国カリフォルニア州の取組みを参考に導入したNEV販売目標規制とクレジット取引制度、中国の実情や固有性を踏まえて展開している「NEV下郷(NEVを農村部に普及させる)」事業についても解説する。
本講座の目的は、受講者に、中国の自動車電動化の戦略目標、取組みと将来展望および世界における立ち位置を体系的に明示するとともに、それに対して日本企業はどう対処すべきか、ご自身の会社が生き延びるためにはどうすべきか、関連ビジネスをどう展開ないし転換すべきか、などについて考えるきっかけを提供することである。
受講対象・レベル
・自動車部品から完成車製造、使用済み蓄電池処理までの自動車産業関係者
・エネルギー産業、ガソリンスタンド業界、充電インフラ業界、商社
・中国の自動車電動化の真相を知りたい方
・日本の自動車産業の再興と炭素排出実質ゼロの実現のヒントを得たい方
・学術界、研究機関、コンサルタント業界
習得できる知識
・中国の自動車電動化の戦略目標、取組みと将来展望および世界における立ち位置を
体系的に把握できる。
・自動車ビジネスで生き残るためのヒントが得られる。
・中国と自動車関連ビジネス(部品や電池調達なども含む)を展開する場合のヒントが
得られる。
・中国における自動車関連ビジネスに関する示唆が得られる。
・ご自身の会社の比較優位性、比較劣位性を確認する手掛かりが得られる。
・自動車電動化における日中の違いなどを確認することができる。
セミナープログラム
1.自動車電動化は中国の国家戦略
1.1 自動車電動化は石油安全保障の確保に欠かせない
1.2 自動車排ガス汚染を根絶するには自動車の電動化しかない
1.3 自動車分野の脱炭素化を実現するには自動車の電動化しかない
・中国が国連に提出した温暖化防止目標の推移
・なぜ脱炭素「3060目標」が設定されたか?
1.4 自動車「大国」から「強国」への転換は電動化を避けて通れない
1.5 NEV技術開発を国家戦略として推進:「863計画」
・内燃機関車では比較優位性がない
・電動化なら勝算ある:NEVは内燃機関車の延長線上ではなく、新世代の車
・中国の電動化はハイブリッド自動車(HV)を含めない
1.6 NEV産業育成と普及に向けた政府の取組み
・2009年から政府補助によるNEV導入実験事業を展開
・購入時補助金は2023年に廃止
・NEVに対する自動車税が2012年から免除、現在に至る
・2013年から利用促進事業を86都市に拡大、その後全国展開
・2014年からNEVに対する自動車取得税を免除、減免は2027年まで
・2014年からNEV充電インフラ整備を本格化
・NEV目標規制とクレジット取引制度を導入:自動車産業政策革命
・NEV下郷(NEVを農村部に普及させる)」事業を2020年から展開
・中長期目標と実現ロードマップの明確化
2.自動車電動化の世界における中国の位置付け:先頭に躍り出た中国
2.1 中国はNEV生産・販売・保有台数が2015年から8年連続世界最大
2.2 BYD等中国系は世界トップのNEVメーカーの列に
2.3 CATL等中国系が世界トップの車載用蓄電池メーカーの列に
2.4 世界における車載用電池部材の供給動向:
中国抜きにしてリチウムイオン電池の4大部材の安定供給を語れない
・正極材
・負極材
・電解液
・セパレーター
2.5 世界におけるNEVモーター材料の供給動向:
中国抜きにしてレアアースの安定供給を語れない
2.6 世界におけるNEVパワー半導体材料の供給動向:核心鉱物の脱中国依存は困難
2.7 リチウム資源確保に向けた中国の取組み
・資源量は世界の上位:残存可採埋蔵量は4位、発見量は6位
・資源の地域分布、種類別分布と品位
・リチウム産業発展に関する政府の基本方針と中長期計画
・リチウム市場動向:生産量、需給バランス
・使用済みリチウムイオン電池からの資源回収
・海外リチウム開発における中国の取組み
3.なぜ中国が世界の自動車電動化の先頭に立っているか:中国モデル
3.1 ICEV販売台数は2017年をピークに減少
3.2 なぜNEVが売れているか
・補助金の役割はもう終わった
・ICEVが大都会で規制されているから、NEVが売れたとは、本当か
・多様なニーズに対応できるNEVの提供:車種・型式数、価格帯、航続距離分布
・ICEVに対するNEVの比較優位性:取得コスト、保有コスト、走行コスト
・NEV利便性の向上:航続距離の延伸、充電・電池交換インフラの充実
・NEV目標規制とクレジット取引制度がNEVシフトを後押し
3.3 なぜ中国製NEVが海外で売れているか
・価格性能比でみる国際競争力の高さ
・認知されつつあるBYD等中国系NEVブランド:輸出と現地生産
・NEVサプライチェーンの強靭性による安定供給力
・炭素排出実質ゼロに向けた取組み強化が追い風
・グローバルサウスに再生可能エネルギー電源とNEVを同時に提供できる
3.4 NEVシフトの中国モデル:特徴と課題
・特徴1:自動車電動化を国家戦略として推進
・特徴2:理論的に有効、または国際的に有効と実証された対策を貪欲に導入
・特徴3:中国の実情や固有性に合わせた対策を試行錯誤的に模索し続ける
・課題
4.中国が電動化で世界一の自動車強国になれるか?
4.1 どこが自他ともに認められている自動車強国なのか
4.2 自動車強国とは何か
4.3 将来展望:中国にとって自動車強国はもはや夢物語ではなくなりつつある
4.4 「弱肉強食」を促すNEV目標規制とクレジット取引制度の2023年改正
・制度改正のポイント
・2024年は後発者にとって中国市場で生きられるかどうかの正念場
4.5 今後の課題
5.国際社会への示唆
5.1 暫定的示唆:中国の経験は「他山の石」
5.2 進む電動化と先頭に立つ中国にどう対応すべきか
・NEVシフトを総力戦で挑む
・先行者との連携
・中国事業の整理、撤退
・中国のNEVクレジット取引市場の活用で捲土重来を図る
付録 自動車電動化に関するよくある誤解
・「火力発電中心だから意味がない」のではなく、電動化と電源脱炭素化を同時推進
・「NEV増えれば電力不足」ではなく、電力を再生可能エネルギー電源で供給できる
・「電動化で雇用を守れない」のではなく、電動化しなければ会社が生き延びられない
キーワード:
電気自動車,EV,市場,政策,オンライン,WEBセミナー
セミナー講師
国立大学法人長岡技術科学大学 大学院 情報・経営システム系
教授 博士(経済学) 李 志東 氏
【専門】
脱炭素システム論、エネルギー経済学、環境経済学、計量経済学
【活動】
エネルギー・資源学会代議員、環境経済・政策学会理事を歴任、日本エネルギー経済研究所客員研究員と中国国家発展改革委員会能源(エネルギー)研究所客員研究員を兼任。「参議院国際・地球温暖化問題に関する調査会」会議で参考人として、経済産業省・外務省・環境省等関連官庁と経済同友会など業界団体主催の温暖化防止やエネルギー安全保障関連会議で出講者として、証言や情報発信と意見交換を行った。NHKクローズアップ現代プラスや日本テレビ深層NEWS等にも出演。
セミナー受講料
49,500円(税込、資料付)
■ セミナー主催者からの会員登録をしていただいた場合、1名で申込の場合46,200円、
2名同時申込の場合計49,500円(2人目無料:1名あたり24,750円)で受講できます。
(セミナーのお申し込みと同時に会員登録をさせていただきますので、
今回の受講料から会員価格を適用いたします。)
※ 会員登録とは
ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。
すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。
メールまたは郵送でのご案内となります。
郵送での案内をご希望の方は、備考欄に【郵送案内希望】とご記入ください。
受講について
Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順
- Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。
- セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。
- 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。
- セミナー資料は開催前日までにPDFにてお送りいたします。
- 無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
受講料
49,500円(税込)/人