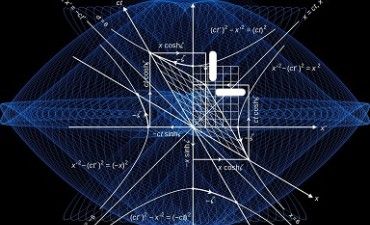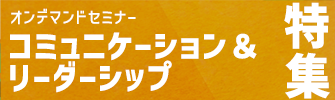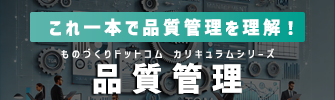講師の企業経験に基づいた実践的な手法
セミナー趣旨
「プラント一式の計画と立ち上げを担う」これは、特に若い技術者への講師の希望です。プラントの計画と立ち上げは(1)新規製品の工業化や既存事業の拡大、或いは(2)技術の合理化・革新を目的として行われるものです。したがって、これを担当することは「事業(経済)」と「技術」の両面で社業に貢献することに他なりません。(1)と(2)はどちらも「スケールアップ」がうまくいってこそ成就するものですから、技術者は「その方法論」をよく学んでおくことが必要です。
そこで、本講ではスケールアップの対象として「撹拌槽」を採り上げ、講師の経験を踏まえて「実践的なスケールアップ手法」について解説します。
受講対象・レベル
・撹拌プロセスに従事する技術者・研究者
・撹拌槽のラボレベルからのスケールアップに従事する技術者・研究者
・スケールアップ全般に関心のある方
・現象のモデル化に関心のある方
・プロセス・エンジニアとしてキャリアを積もうとしている技術者
習得できる知識
・反応槽、または反応を含まない撹拌槽のスケールアップ技術
・撹拌動力と混合特性に関する実験・解析方法
・反応槽のシミュレーション:その有効性
・講師の企業経験に基づいた実践的な技術論
セミナープログラム
1.スケールアップ総論
1.1 スケールアップとは
1.2 スケールアップの流れ
1.2.1 実験と解析の準備
1.2.2 原型機による実験
1.2.3 実験データの解析とスケールアップ基準因子の見極め
1.2.4 実機仕様の決定(基本設計)
1.2.5 実機の詳細設計と設計変更への対応
1.2.6 実機の水運転と実液運転
1.2.7 スケールアップの検証とその結果の継承
2.撹拌槽のスケールアップ:スケールアップ比の決定・基準因子の見極め
2.1 撹拌性能を決定する重要な諸元
2.2 スケールアップ比の決定
2.3 スケールアップ比と撹拌特性倍率
2.3.1 スケールアップの基準因子(幾何学的相似の必然性)
2.3.2 原型機と実機の撹拌特性の対比
2.4 スケールアップの基準因子を読み解く
3.原型機による撹拌実験
3.1 序論(核心は撹拌動力の決定と混合特性の同定)
3.2 撹拌動力の測定と結果の適用
3.2.1 測定方法
3.2.2 撹拌動力数-レイノルズ数線図
3.2.3 撹拌動力の決定
3.3 混合特性の同定(完全混合の見極め)
3.3.1 ステップ応答法による解析
3.3.2 1段完全混合槽の残存濃度曲線
3.3.3 可視化実験による混合時間の測定
3.3.4 無次元混合時間-レイノルズ数線図
4.実機によるスケールアップの検証
4.1 撹拌動力
4.1.1 モーター動力の推算方法
4.1.2 水運転と実液運転による検証
4.2 混合特性
4.2.1 水運転による検証(槽列モデル)
4.2.2 実液運転の想定
5.スケールアップに関連する技術検討
5.1 撹拌翼を増設するときの動力推算法
5.2 原型機-実機間の幾何学的相似を外すときの考え方
5.3 反応のシミュレーション
5.3.1 連続塊状重合の例
5.3.2 回分式懸濁重合の例
5.4 立ち上げを想定した事前検討(シミュレーションの適用)
5.4.1 スタートアップ手順
5.4.2 エマージェンシーへの対応
6.教訓(スケールアップを振り返る)
6.1 「サイズ効果」という原型機の落とし穴
6.2 失敗しないためのポイント
<質疑応答・名刺交換・個別相談>
※途中、小休憩を挟みます。
セミナー講師
技術コンサルタント 博士(工学) 藤本 清二 氏
■ご略歴
1973年 住友化学工業(現住友化学)(株)入社、主に合成樹脂や機能性フィルムの製造プロセス並びにR&Dに従事
2006年 大倉工業(株)入社、主にフィルム加工プロセスのR&Dに従事し、技術教育も担当
2022年4月以降、フリーの立場で技術記事の執筆、技術指導を行うと共に、セミナー講師も務めながら現在に至る
セミナー受講料
1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講について
- 感染拡大防止対策にご協力下さい。
- セミナー会場での現金支払いを休止しております。
- 新型コロナウイルスの感染防止の一環として当面の間、昼食の提供サービスは中止させて頂きます。
- 配布資料は、当日セミナー会場でのお渡しとなります。
- 希望者は講師との名刺交換が可能です。
- 録音・録画行為は固くお断り致します。
- 講義中の携帯電話の使用はご遠慮下さい。
- 講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方の迷惑となる場合がありますので、極力お控え下さい。
場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承下さい。(*PC実習講座を除きます。)
受講料
41,800円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
PFAS(ピーファス)を分かりやすく解説!有機フッ素化合物の基礎知識
【目次】 PFAS(ピーファス)という言葉を耳にしたことはありますか?PFASは「パーフルオロアルキル物質」の略で、主に有機フッ素化... -
弾性限界とは?定義や求め方を応力ひずみ曲線を用いて解説!
【目次】 弾性限界(弾性限度とも呼ばれる)は、材料が外部からの力に対してどのように反応するかを理解する上で重要な概念です。特に応力ひ... -
ロボット工学とは何か?構成技術、学習方法、応用分野、AIとの相乗効果も!
ロボットといえば大昔はSF小説や漫画・アニメ・特撮の世界のものでしたが、現代では社会のさまざまな分野に浸透し、その姿や機能も多種多様なものとなっていま... -
プラスチック分解微生物とは?求められる背景や仕組みについて解説
プラスチックは私たちの生活に欠かせない素材ですが、その便利さの裏には深刻な環境問題が潜んでいます。毎年膨大な量のプラスチックが廃棄され、海洋や土壌に蓄...