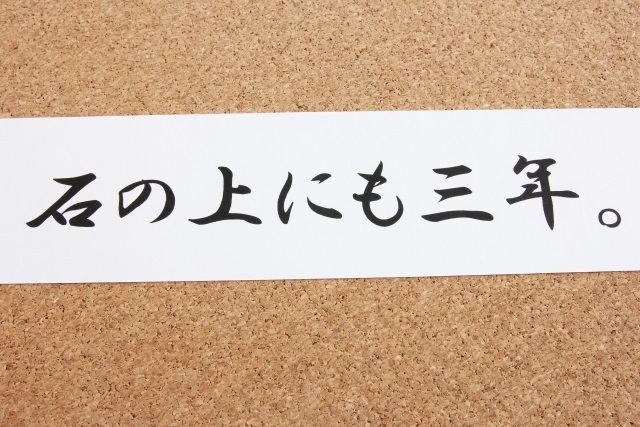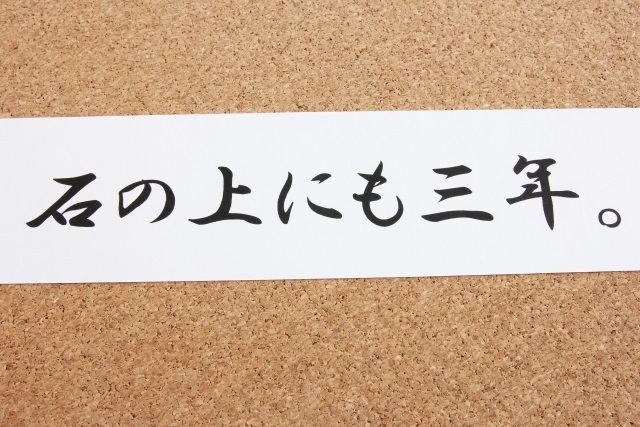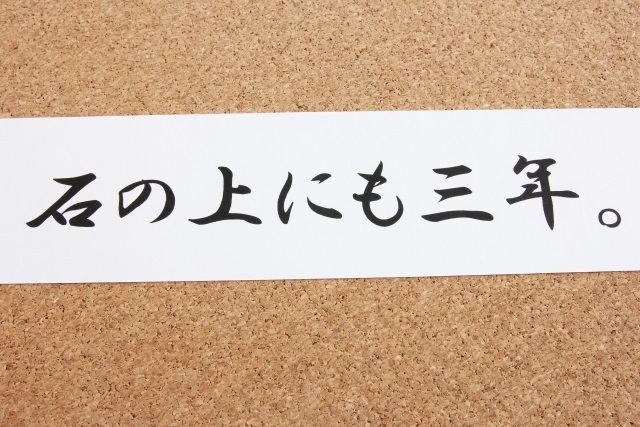今回の記事では、A3判の用紙1枚で作成した業務の概要版の利用方法として「概要版をデータベースにして活用する」について書きます。
1. データベースにして活用する
知人が勤務する建設コンサルタントの会社注)(A社とします)では、自分が担当した業務が終わったら、A3判の用紙1枚でその業務の概要版を作成しています。この目的の1つは「概要版をデータベースとして活用すること」です。
A社では、A3判の用紙1枚で作成した業務の概要版をデータベース化し、それらを社内LANを使ってパソコン上で誰でも自由に見ることができるようにしています。
概要版の作成は社内のすべての部署が対象です。そのことから、全部署で作成した概要版を誰でも自由に見ることができます。概要版を読むと、自分が所属する部署以外の部署で行っている業務を知ることができます。
A社の社員の方に聞くと、概要版を読むと、他部署で行った業務でも自分の業務を進めるうえで参考になる業務があることに気が付くそうです。
また、様々な人が作成した概要版を見ることで概要版の作成方法を学ぶことができるそうです。
自分の業務を進めるうえでのメリットもあります。
自分が担当する業務(A業務とします)を行う場合、その業務と類似した内容の業務(B業務とします)を他の社員が既に行っていることがあります。このようなとき、A業務を行ううえでB業務の結果が参考になります。
B業務の結果を調べる場合には、B業務の担当者にその内容を聞くのが最も確実な方法です。しかし、担当者が人事異動などでいないためB業務の結果をその担当者から直接聞くことができないこともあります。このような場合には、B業務の結果を調べるためB業務の業務報告書を読む必要があります。
このとき、B業務の概要版が作成されていないと、B業務の全体の流れを確認しながら業務報告書を読むとともにその内容を理解する必要があります。
しかし、B業務の概要版がA3判の用紙1枚で作成してあれば、この概要版を読むことでB業務の全体の流れがすぐに頭の中に入ります。B業務の全体の流れが頭の中にあればB業務の結果が理解しやすくなります。
2. 継続することが重要
前回の記事で書いたように、A3判の用紙1枚で業務の概要版を作成することで
わかりやすい文書を書く力がレベルアップします。更に、記述式の問題が出題される試験の試験対策になります。また、この概要版をデータベースにすることで得られる効果については今回の記事で書きました。
このようにA3判の用紙1枚で業務の概要版を作成することは、技術者個人にとっても会社にとってもメリットがあります。
しかし、この概要版の作成には時間がかかります。
A社の社員の方に、「A3判の用紙1枚で業務の概要版を作成することは大変ですか?」と聞いたことがあります。...