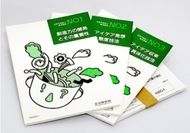▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
職場で、新しい視点や提案に、どこか冷たい反応が返ってきたことはありませんか?反対に「面白い視点だね、試してみよう」と受け入れられた場面もあるかもしれません。実はこれ、組織の中にある「メンタルモデル」の違いが影響しているのです。今回は、長い歴史と成功・失敗の体験から形成されるメンタルモデルのお話です。メンタルモデルを見直す勇気が、成長の扉を開きます。新しい視点を受け入れ、組織と自分を進化させましょう。あなたの耳と心の扉は、今どちらに向いていますか?
1. メンタルモデルとは?
メンタルモデルとは「私たちはこうあるべきだ」「このやり方が正しい」という暗黙の前提や思い込みのことです。私たちは、過去の成功体験や文化の影響で、知らず知らずのうちにこうしたモデルを築いています。私がメンタルモデルのお話をするときには「問題の捉え方と対処方法」という説明の仕方もします。
例えば、ある会社では「とにかく現場主義」が美徳とされ、外部の意見を「非現場的」として退けがちです。逆に、別の会社では「新しい意見こそチャンス」と捉え、積極的に取り入れる文化が根付いている――これがメンタルモデルの違いです。
(1)閉じた扉と開かれた扉
私が出会った二つの組織の話をしましょう。A社では「現状維持」が暗黙のルール。提案をすると「その意見はリスクがある」「これまでの方法で十分」と返されることが多い組織でした。会議の空気も固く、新しい発想を出す人は少数派。外部からの提案は「余計なこと」とみなされ、ほとんど進展しませんでした。
一方、B社は違いました。「それってどういうこと?もっと詳しく聞かせて」と、興味深そうに耳を傾けてくれるのです。リーダー自身が「うちはまだまだ伸びる余地がある」と公言しており、メンバーも...