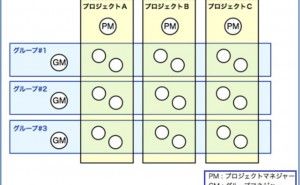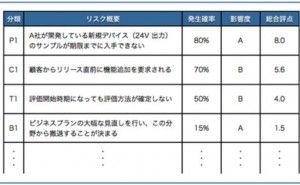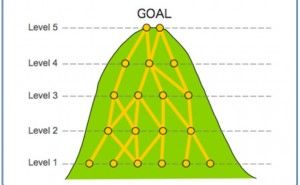製造企業に必須なプログラムの一つに保有技術の棚卸しというステップがあります。このステップは今後、何をやるにしても通過しなければならない重要なステップです。今回はこのステップにおける主なポイントを挙げてみます。
1)技術の所在追究は商品化のプロセス、技術変遷、製造工程、施工工程などから捉えていきます。例えば開発プロセスは企画から初期流動解除まで。また必要に応じて実作業者やOBから所有技能を探ることも有効でしょう。
2)顕在化された技術について体系化区分を明確にし、漏れの無いように体系化していきます。体系化区分は次の4項目で構成されます。
- 技術領域(設計技術、製造技術等)
- 技術分野(電子技術、躯体技術等)
- 技術区分(大、中、小区分等)
- 技術項目(技術名)
3)対象となる技術を一言で表現します。これを技術名(項目)として捉えますが、その留意点として、技術はその対象となる機能に対して項目を捉えます。ものは技術ではないので、例えば炊飯器のしゃもじは設計技術ではなく、攪拌表面形状技術、把持技術などに分解します。
4) 潜在技術(埋もれた技術)は、技術資料として残っていない場合が多いので、調査分析しないといけません。これらの技術には、顕在化された技術項目の派生的、発展系、特定部位で潜在技術が埋もれている場合があると考えられます。
5)棚卸をしてみると実は、技術というより技能に分類されるものが多かったりします。そこで技術と技能を明確にする必要があります。まず技術に分類されるものは、ある論理(自然科学)に基づいて生産物を生み出すための方法で、且つ手順化されているものと考えます。
一方技能というのは個人特有の能力であり、生産物を生み出す際にその人の経験、知恵、技、勘などが人より優れており、一般的な応用が難しい或いは波及されていない方法論と考えます。現場の作業などに多く見受けられる技能は、その人についていて資料になっていないことが多いため、応用を目指すのは意外と難しいものです。そこで技能については、技術に変換するという作業が必要となります。
6)明らかになった自社技術について定義付けをします。実はこれらの技術は、しっかり定義されておらず曖昧なため技術評価が出来ません。自社技術として特定したり技術...