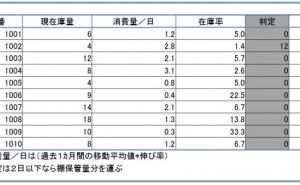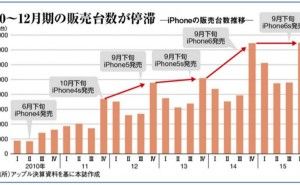1. 国内物流と海外物流
メーカーの海外進出は大企業にとどまらず、中小メーカーでも一般的になりました。工場を建てて日本で培った技術をベースに高品質のものづくりを行う。これが多くの会社で実現しているのです。しかし注意点があります。それが物流です。日本国内にあってもメーカーで物流はまだまだ二の次の存在です。
これが悪循環を生んでいます。『物流に回す人財がいない ⇒ 物流人財が育たない ⇒ 物流を変えられない』いつまでたっても物流がよくならないのです。このような状態で海外進出するとなると各社の頭を悩ませる存在が「物流」なのです。
仮に社内に物流がわかる人財がいたとしましょう。もし海外に工場を建設するとなると、その物流は物流がわかるそのスタッフの仕事になると思われます。そのスタッフは海外工場に関わる物流を一手に引き受けて仕事をこなしていかなければなりません。たとえば工場内物流について考えてみましょう。
工場の中の物流ではまず敷地内の工場建屋と工場内道路の設計が必要です。ここでよく見かけるおかしな現象について紹介しましょう。工場で部品を受け入れる際に雨濡れは絶対に避けなければなりません。そのためトラックが入ってきたらトラックがすっぽりと入る屋根が工場建屋に必要になります。おかしな現象の1つ目は「トラックが屋根のあるエリアからはみ出している」という状況です。なぜこのような現象が起きるのでしょうか。
それはこのスタッフが日本のトラックをベースに設計しているからです。現地では日本より大きなトラックが一般的です。この現象は致命的ですね。別のおかしな現象も付随的に発生してしまうのです。それがプラットホームの無い工場です。海外ではトラックはリヤゲートから積み降ろしをすることが一般的です。それは日本でよく見かけるウイングボディーのトラックが無いからです。
日本人スタッフはどこでもウイングボディーを調達できると考え、平地でフォークリフトを使って積み降ろしをすることを考えます。だからプラットホームの無い工場を設計してしまうのです。これが2つ目のおかしな現象です。これもまた大変なことになります。トラックのリヤゲートからの荷役を平地でやらなければならないのです。こういった現象はなぜ起きてしまうのでしょうか。それは日本の物流しか知らない人が設計をしてしまうからなのです。
2. 国内物流では通用しない海外物流設計
日本だけの知識では海外で仕事をすることはできません。前回お話したような「おかしな現象」を引き起こしてしまっては効率を阻害しかねません。私たち日本人が注意しなければならないことは「海外で通用する物流」を研究することではないでしょうか。できれば物流担当者であれば海外に出かけて行って、自分の目で海外物流を確認することが大切だと思います。
北米では鉄道でダイナミックな輸送を行っていますし、トレーラー輸送も一回に運べる量が多く、混載による効率輸送に適しています。もし中国でビジネスを行うのであれば、この北米物流を参考にすべきではないでしょうか。多くの日本の物流指導者が日本の物流が最も進んでいるような話をしますが、これは間違っています。
日本では道路舗装の状況もよく、輸送距離も短距離です。日本列島が小さく、人のモラルも高いため、物流が最もやりやすい国ではないでしょうか。日本では倉庫でものが無くなるということは多くはありません。輸送途上でものが盗まれたり、強盗に出会ったりすることもほとんど無いでしょう。
これほど余分なことに気を使わずに物流の仕事をできる国は珍しいかもしれません。その国で行っている物流の方法をそのまま海外で当てはめようと考えている人が多いことに驚きます。日本では性善説が成り立っても、海外でそれが成り立つとは限りません。悲しいことかもしれませんが、従業員による窃盗は考慮しておかなければならないのです。
メーカーが海外で工場を建設する際には港とのアクセスや顧客への配送を考慮して立地を検討する必要があります。通関にかかる日数や輸出入のリードタイムを考えて在庫設定をする必要があります。物流作業者のための作業標準をしっかりと定め、その通りに業務を行うような指導プログラムも必要になってくることでしょう。
日本では部下がある程度上司の思いを察して仕事をしてくれます。ここは「腹芸」が効いていて、事細かな指示が無くても仕事が進む傾向があります。しかし海外ではこのようなことは成り立ちません。現場監督者は特にきっちりしとした指示を出さなければ部下は期待外れの仕事をする可能性があります。
これは部下の責任でしょうか?いいえ、ほとんどが監督者の責任だと考えて間違いないと思います。海外で物流業務を行うのであれば、まず監督者の教育が必要です。