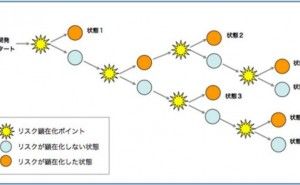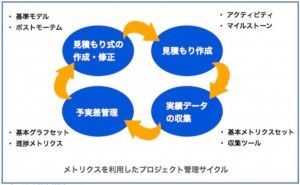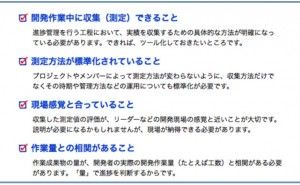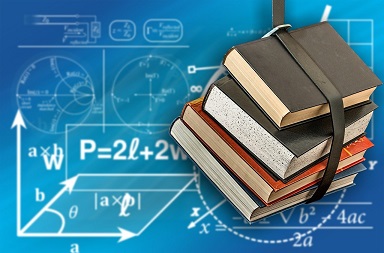
1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法
私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考えることを優先させてしまいがちです.
難易度の高い技術へのチャレンジは技術者にとってのモチベーションの原動力とも言えますからこれは当然のことです.しかし,どんなに新規性のある難しい技術を実現したとしても,それがお客様のニーズに合っていなければ製品とのしての価値はないに等しいのです.各社横並びのHOW競争時代ばコストを現状維持しながら性能10%向上のようなスペック向上型の開発も有効でしたが,お客様の期待を超える製品を実現することが求められる今の時代では,お客様は自分がほしいものを知らないことを前提として,Voice of Customerを創造することが必要になります.
そこに有効な技法が福原流QFDです.
福原流QFDではお客様の生の声であるRaw Voice(RV)とVoice of Customer(VOC)を明確に分けます. 例えば複写機やプリンタでの代表的なRVである「印刷が遅い」に対して直接的に応える開発目標の設定は簡単です.印刷開始ボタンを押してから印刷開始するまでの待ち時間への寄与が最も大きい定着モジュールを対象に,その温度上昇率を現状よりも10%高くするというような目標を設定することは一般的に行われていると思います.このような性能改善を継続することはもちろん必要ですが,それだけでは横並び競争から脱することが難しくなります.またRVのほとんどはお客様の不満の声ですから,それに対応することは不満の解消でしかなく,お客様の期待を超えるレベルまでには至りません.
そこで温度上昇率を飛躍的に高める新たな定着方式を実現し,お客様の期待を超えることを目指すわけですが,その前にお客様の真のニーズを定義することでまったく別の技術手段を考案する可能性を広げることも有効なのです.お客様が本当にほしいものは定着モジュールの温度上昇率ではありません.「印刷したいときにいつでも印刷できること」が真のVOCです.このVOCは温度上昇率のような定量性がなく抽象的なので,VOCそのものから具体的な技術開発テーマを設定できないというデメリットがありますが,技術手段を考案する対象範囲を拡大するというメリットもあります.
例えばお客様がマシンに近づいたらそれをセンサーで検知し,お客様が印刷開始ボタンを押す前に定着モジュールに電力を投入してしまうというような発想です.このような発想は不満の声であるRVからはなかなか出てきません.不満の解消ではなく,メリット言葉で表現した真のニーズであるVOCをイメージすることで新たな技術手段が生まるチャンスが増えると思います.福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法です.
2. ダイソンの扇風機、羽のない扇風機が創られた時の目標設定とは
ダイソンの羽のない扇風機ですが、あのような革新的な製品を創り出す組織の仕組みや文化に興味があり調べたことがあります.日本企業とは異なるいくつかの仕組みや文化があることは間違いなさそうです.その中の一つが開発目標の設定です.
目標管理制度を導入した日本企業のほとんどはできるだけ数値化された定量的目標の設定が要求されます.しかも個人レベルかつ半年単位です.ありがちな目標設定は「消費電力を現状維持しながら風量10%UP」のような一元的品質と当たり前品質の両立改善かと思います.
手段は羽の形状の最適化です
このような目標設定が横並び競争を引き起こすわけですが,そもそも目的特性の計算が可能で手段が特定の設計空間内の形状最適化であれば,自動最適化ツールが最適解を出してくれます.技術者の創造性は必要ないのです.
ダイ...