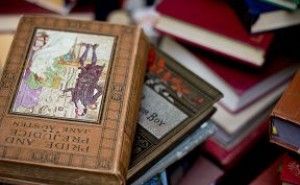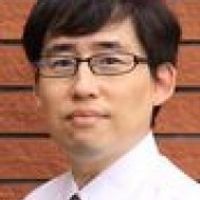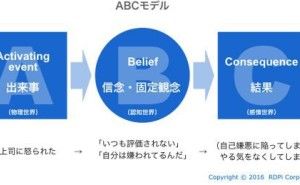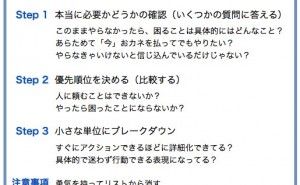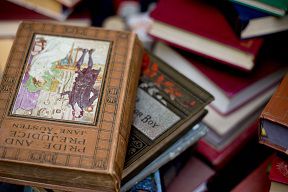
何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。
「あなたのお仕事は勉強する事」、と母に言われて嫌々勉強をしていました。大学進学を、本当の意味で自分で選択するまでは成績も悪かったようです。何故そんな私が大学へ進学したのか、それは、単に実家を出て一人暮らしをしたかったからです。親や祖母がその大学なら(物理的に通うのは現実的でないという理由だけでは無く)一人暮らしをさせてでも、そのコストを払ってでも学歴社会だった当時はベストな選択だと思ってくれていましたので目的はともかく双方の利害は一致したのです。
就職してからも基本的には自分のために頑張ります。愛社精神は建前で自分が評価され給与を上げてもらうために頑張っていたと思います。もちろん頑張って結果を出すこと、それが評価に繋がる事は、やり甲斐にはなりました。
一方で自分のためだけなら何時でも手を抜けます。給与が変わらないならあくせく働くのはアホらしい、適当に時間を潰して残業で稼ごう・・・そう言う考えもありました。セミナーや学会に参加して業務上の知識やスキルを得るのも自分の為でしたら気分が乗らない時は手を抜けました。出張報告書を書くための最低限の情報だけ得られれば良いと思ったら、途中で居眠りしたり中座したりもありました。
自分のためだけなら表層上の理解で良いですし、気分が乗らなければ途中で辞める事も可能です。当然学びの質も低いですし、一週間も経てば半分以上忘れてしまいます。然しながら第三者に教えなければならないとなったらそれはもう姿勢が変わります。
なんとなくの理解では当然ながら自分の言葉に変換して話をする事は出来ませんし、仮に講師の言葉を100%コピー出来たとしても理解してないので少し突っ込んだ質問が来たらタジタジです。
私が品質管理や
統計手法を自分の専門に出来て、独立した今でも仕事として活かせているのも元々は部下に教えなければならない、関係部署の人に講師として教えなければならないと言う責任を背負った形で学んでいたからです。午前様で帰宅した後で、明け方まで宿題に取り組み寝ないで会社に行った事も当然の事でした。
自分以外に教える事を前提で学ぶ、さらにその責任を背負うと言う事は学びの質を大いに上げる事になります。学んだ後も教育者として更に精進するのでどんどんレベルアップしていきます。苦労して学んだ事を...
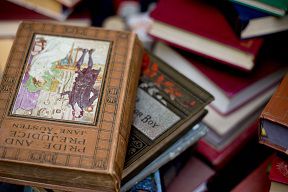 何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。
何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。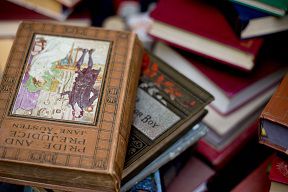 何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。
何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。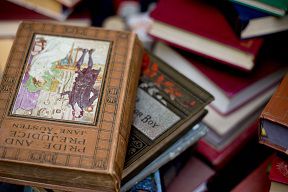 何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。
何かしら学ぶ時、それはあなた自身の為に行う事がほとんどだと思います。遡れば小学校からの義務教育は親からの強制の有無は別にしても自分の為に行ってきたと思います。自分の為に行うからこそ、嫌になれは平気で手を抜けますし、最悪途中で辞める事も可能です。親が喜ぶからとやっていた人でも大学に入学した途端に遊び呆けるのでは無いでしょうか。