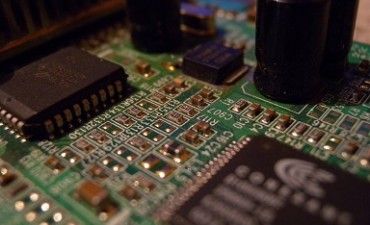ものづくり企業の皆様と危機感、危機意識を共有し、企業体質強化をしていただきたいと思い記しました。大手企業は多くの場合、東南アジアに幾つか工場を持っています。また、大手以外でも海外進出している企業はあります。
ものづくり企業の皆様と危機感、危機意識を共有し、企業体質強化をしていただきたいと思い記しました。大手企業は多くの場合、東南アジアに幾つか工場を持っています。また、大手以外でも海外進出している企業はあります。これらの企業は、海外の自社工場を指導する中で様々な情報が入手しやすく、また他社情報も入手できると思います。従って複数の国に工場を持つことで危機意識を持ちやすく、相互に情報交換したり、企業内競争をしながら品質、コスト、納期などのレベルを日常的に高める活動をしています。その結果、現場の体質も強化されていきます。
しかし、国内でそのような情報入手の機会がない企業は、危機意識は薄く日々淡々と生産活動に没頭してしまいがちではないでしょうか。こうなると見えない敵、つまり競争相手を意識することは少ないと思います。そして現場体質の改善にも本腰が入りません。
私が国内や東南アジアのものづくり現場でクリーン化指導してきた中で、危惧することは、東南アジアの現場が格段に綺麗に管理され、現場の体質が強くなってきているということです。そしてオペレータの品質意識も高くなったと感じます。つまり、『日本の現場を追い越している!』と感じることです。
東南アジアに、ものづくりの現場をお持ちの企業では認識されていると思いますが、それは一部に限られています。情報が入りにくい企業では、経営者や管理監督者がそのことに気づいていないのです。
東南アジアでは、中国、タイ、シンガポール、インドネシアなどで指導してきました。中国では蘇州、無錫に多く通いました。また指導ではありませんが、香港、深せんなどの工場も見てきました。その過程で、日本のものづくりは大丈夫かと心配になりましたが、行けば行くほどその危機感は強くなりました。
日本でこれだけ徹底して、綺麗に管理されている現場がどれだけあるのだろうかという危機感です。これは負けていると感じました。
東南アジアの現場の素晴らしさを見て、帰国後その凄さを写真やデータなども活用し、できる限り伝えようとするのですが、上手く伝えることが出来ません。なぜなら、「あなたのいうことは大げさだ」とか、「そんなに進んでいるとは思えない」などと言ってなかなか真剣に聞いてくれないのです。そういう先入観を持ち続けているんです。それが障害になっているのです。東南アジアをいまだ上から目線で見続け、聞く耳を持たないのです。
費用節減のため、海外出張はいつも一人でした。本当は後継者育成も含め、現場や指導方法を見せることが大切です。まさに“百聞は一見にしかず”です。私が訪問した幾つかの工場の作業者からも、「日本に勉強に行ったが、あまり参考にならなかった」とか、「日本の工場の方が汚れていた。」或いは、「私たちが教えて貰ったのだから、今度は日本に恩返しとして指導に行きます。」などと言われたことがありました。
指導に行った先方から日本に指導に行くと言われるのですから、かなりのショックです。もちろんこれらの現場を指導してきたのは日本企業です。海外では素直に聞いて取り入れるので、障害も少なく速やかに導入できますが、日本では東南アジアというだけで、そんなはずはないという先入観もあって、話が伝わらないのです。何だか“ウサギとカメ”のようです。
そしてこれらが伝えられない、逆には受け入れないので、上から目線で見ることが続き、益々差が開くのかも知れません。自分の会社がどのくらいのレベルかを認識する機会がない中では、危機感も感じないので危機意識も持てないのだと思います。
一方、日本国内では、色々なTV番組や報道を見ますと、日本の技術力は高いというような内容が目立ちます。これらを見ると日本は凄いんだと意識をしてしまい、油断が生じます。
確かにすごいと感じる部分もありますが、これは一部のことであって日本全体の姿ではありません。それを勘違いすると、安心してしまいます。でも現実は...