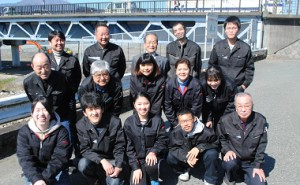3.マンネリ対策にはどんなものがあるだろうか
マンネリから脱却するには、まず頭をつねにプラス方向に回転させなければならなりません。プラス思考の六つの基本姿勢をあげると、現状に疑問を持つこと、何かに気づくこと、練ること、実行すること、粘ること、楽しむことです。また自惚れ、安心、満足感が心の中に起きた時には、感度と感性が鈍るので、謙虚な気持ちを持って感度とか感性を磨くには、以下のような点がポイントです。
(1) まずなんと言っても好奇心があること、好奇心を持つことです。これは、如何に自分の仕事の使命に燃えているかに尽きます。すなわち、その使命を楽しんでいるかということです。マンネリ化状態ではとても無理であり、快、不快の印象を大切にすることが大事です。
(2) そして自分の仕事範囲を常に拡大していることが重要になります。これによって始めて新鮮な情報が入りやすくなり、視点を変えた観点も養われます。仕事の拡大といっても難しいことを考える必要はありません。自分が興味あること、楽しいと思えることに積極的に取り組めばよいのです。そうすることによって、自分の守備範囲が広がっていきます。情報、知識吸収、責任感、人脈もおのずと拡大していきます。
(3) また今までの常識を捨て、白紙の状態で自然体になることです。これは好奇心を持つことにも通じるわけですが、要は子供心を持つことです。単純な誠実さと過去の通説で物事を解釈しているようでは低感度化、低感性化していくだけです。 肩の力を抜き頭を休ませ常識を疑う。音楽にも休止符があります。休止符による間の取り方で、次のフレーズがフレッシュに聞こえるのです。
(4) 他人の話に充分耳を傾け、よく聞く態度を持つことです。過去の常識にたけている人ほどよくしゃべり、他人の話を聞きません。人間は耳がふたつ、口が一つ、自分の話す量の倍の量を聞く態度が大切です。また他人の行動をよく観察できることも大きな能力です。よく聞き、よく見ることが変化を捉える感度を養います。
(5) 異分野の世界に関心を持つことです。同一分野ばかりに没頭しても、それはあくまで平面の世界です。異なる分野の知識、体験そして異なる分野の人との交流は視点を拡大し、あるいは複合視点を形成し、同一分野の平面世界と比較すると立体の世界を覗くことになります。平面的感度から立体的感度になるわけですから、より鋭い感度を養うことになります。誠実、勤勉、真面目人間は変化に弱いですが、自分と違う立場の人を知り、認め合うことです。
また、過去の経験に足を取られるないことも重要です。経験を積み重ねると、いたずらに恐れを抱かず落ち着いて物事に立ち向かうことができ、これも非常に大切なことです。 しかしそれは逆に言えば、うまくいって成功した経験、または悪くなって失敗した経験が数多く蓄積されるということ。この蓄積が時として大きな障害になります。 自分の中に積み重なっている蓄積、すなわち常識が顔を出してきて、その判断に引きずられそうになるのです。 経験がなく未熟であるほど勢いを生みます。経験を基本にすれば、その時々は賢明な判断に見えても、長い目で見れば活気や勢いを失っていくことになり挑戦を妨げます。 捨てることで新しい道が開けるし、可能性を追い続けることになります。
さらにはファミレス現象に陥るなということもあるでしょう。 ファミレスの品揃えは無難第一という現象です。極端な保守派とも言え、大きなはずれがないかわりに、極めて珍しいもの、心を揺さぶる感動を得にくい状況を指します。
更なるマンネリ化対策もいろいろあるでしょう。自然に素直になること、よい環境の中で感動を味わうこと、末端、現場を知ろうとする心、旅をすること、歴史をふり返ること、古典を学ぶことなどなど。
また進歩の障害は無知でなく、知っていると思い込むことです。我々はよく、「そんなことは分かっているよ」とか、「知っているよ」ということが多いのですが、それこそが進歩のもっとも大きな障害です。知っていることはもう古い、そう思わないと自分の進歩をストップさせます。無知と思い、謙虚な人ほど進歩するし、ゆでガエルになりにくい、マンネリ化しにくいのです。
ドリルで板に穴を開ける話があります。日曜大工のあなたが、板に穴を開けたくてドリルを買い、そして穴を開けます。あなたの使ったお金はドリルを買うためなのか、穴を開けるためでしょうか?ドリルは手段であり、穴のためにお金を使ったのです。購入したいモノにお金を払うのか、実現したい目的にお金を払うのでしょうか。品物を買うのではありません。その品物の問題解決能力(解)を買うのです。
4.少し別の面からのマンネリ対策
(1) 一点(つぼ)を抑え集中的に考える習慣をつけます。世の中つまらないことが多々あり、本当に重要なことは少ないのです。この習慣が好奇心と感度を養成し、マンネリ化を防ぎます。
(2) 改善と改革という言葉があります。改善は連続的なもの、改革は非連続的なものです。日常の連続線上での変化でなく、今までとは断続した局面でいろいろ考えると、好奇心や感度を高めることが出来ます。
(3) 大きいことを考え、小さいことからはじめよ(着眼大局、着手小局)という概念があります。大きな概念から入ると、「好奇心」が生じて「感度」を高め、「感性」を豊かにします。単眼志向の世界から複眼志向の世界へ導くことで、いろいろな角度からものが見えるようになります。二つ以上の視点があることで距離感ができるのです。大きな概念から入り、ロマンを持ち、ビジョンをはっきりさせ、大きな目標を明確にすれば、多くの人が参加しやすく爆発的な力を生みます。目標は大きいほど...