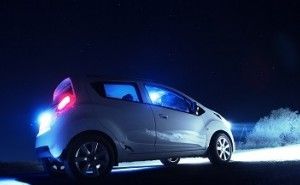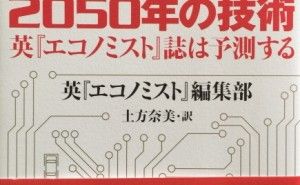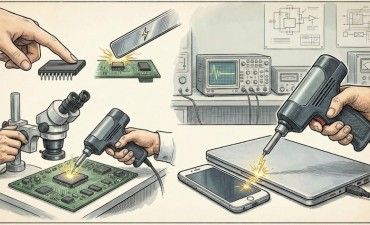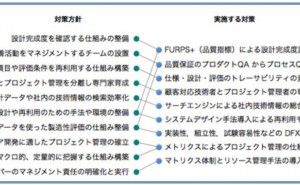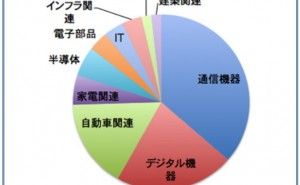【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】
◆ 情報コンテンツの消費形態
1. テレビは4K8K
ここ数年、日本に出張したときに家電量販店のテレビ売り場を覗いて驚くのは、売っているテレビの多くが4Kだということです。HD・2Kのテレビは、32インチ以下が大部分です。店員に尋ねたら、HDだと画素の粗さが目立って苦情が多いので、メーカーが4Kモデルにシフトしたのだそうです。
アメリカでも、半分以上は4Kになっていますが、まだHDモデルも売っています。50インチ超えの大画面になれば確かに画素の粗さは目立ちますが、広いリビングで離れてみれば特に問題はなでしょう。それよりも値段が安いほうがよい人たちも大勢いるということです。
図1. アメリカと日本の量販店
2. 世界のコンテンツビジネス
日本では4K8K放送が始まっていますが、実は世界で4K8Kのテレビ放送をしているのは、日本と韓国だけです。日本と韓国以外で4K放送を計画している国はありません。それでは、なぜアメリカやヨーロッパで4Kテレビが売られているのでしょうか。
放送以外で4Kを見る方法は、UHDブルーレイ・ディスクかインターネットのストリーミングです。ハリウッド映画もUHDブルーレイ・ディスクで一部の作品を4Kで提供しています。また、HuluやNetflix も自前で4Kソースを制作しています。
ハリウッドでは、デジタル時代のコンテンツ配信がいま最もホットな話題の一つになっています。ハリウッドのビジネスモデルは、コンテンツの制作、配給、そして、それをお金に換えることを基本にしています。ところが、デジタルになると、配給だけでなく配信が加わるので、“お金に換える”プロセスを再構築する必要があるからです。
一方でここ数年、ネットの広告収入の85%はGoogleとFacebookに流れているといわれています。ネットの広告収入は、いまや最も稼ぎのよいビジネスモデルになっているのです。ハリウッドもFacebookも、ユーザーにより多くの時間コンテンツを消費してもらうことが直接収入増につながることを知っているのです。テレビだけでなく、PC、タブレット、スマホ、AR/VR、なんでもいいからユーザーが画面を見ている時間を増やすことが、彼らの至上命題なのです。
3. OTT Video
そこで注目されているのが、OTT Video です。OTTは “Over the Top” の頭文字なのですが、これを聞いてもなお意味不明でしょう。一言でいえば、インターネットでのストリーミングのことなのですが・・・。インターネットは、すでに(ストリーミングとは)別の目的でサーバーや光ファイバーが構築されています。ケーブルTVもすでにセットトップボックスとケーブルネットワークが構築されています。そういった既存のインフラを使って、その上でビデオコンテンツを流す、という意味で Over the Top と言っています。Youtube、Hulu、Netflixなどが代表格です。
4K放送を実現するには、専用の通信衛星を用意して、専用の伝送プロトコルを開発して、専用のチューナーをユーザーに買わせなければいけません。同じことをHDTVへの移行で一度やっているので、世界の国はもうそんなことはやりたくない(コストに見合わない)と思っています。だから、OTT Video を解決策として使おうとしているのです。
4. OTT Video で変わる社会
OTT Video が普及すれば、テレビ放送はなくなる(もしくは、いらなくなる)と言われています。
実際、わが家でもリアルタイムの“放送”でテレビをみることは極端に少なくなっています。ドキュメンタリー番組やドラマは、Huluなどネットでのオンデマンドサービスでまとめてみることができます。リアルタイム性を求めるのは、ニュースとスポーツくらいではないでしょうか。YouTube 世代の子供たちには、テレビ番組というコンセプトを知らない子もいるようです。
...