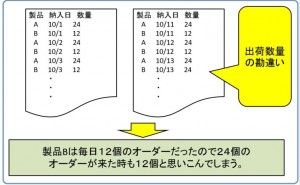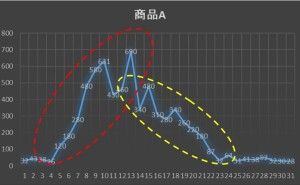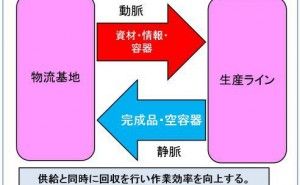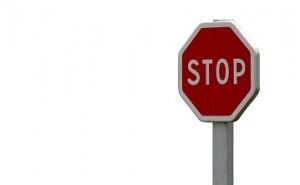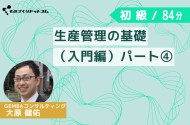製造業再編の発生理由は、サプライチェーン上での存在意義をどうするかという、企業のポジショ二ングのし直しといって良いでしょう。
これまでの、技術上の特殊性にもとづく製品の差別化、ビジネス戦略の差別化といった、製品と市場を共通にした会社同士の同業企業間の競争はむしろ安泰でした。現在は同業という左右の競争者との戦いに加え、サプライチェーンの上流・下流の上下が競争者となる時代です。経営戦略のどのような差別化が新しい産業やビジネスを生むかを考えなければならない、グローバルな大競争・規制緩和・情報ネットワーク時代なのです。
デル・コンピュータ、フェデックス、菱食、ウオルマートなどサプライチェーンマネジメントの事例に登場する各社をみると、単純に従来の製造業、物流業、流通小売業の区分ではカテゴライズできません。
デルはPCのメーカーです。しかしインターネットによる「通信販売」で、インテルやマイクロソフト、日本の液晶メーカーなどのベストクラスのコンポーネントを組み立てて配達している「通販業者」とも言えます。菱食は加工食品の卸問屋ですが、メーカーから納入したケースごとの商品を、コンビニエンス・ストアの日別・棚別・カテゴリー別に陳列する「部品」としてみることで、小口多頻度の受注に応じて組立て・配送するメーカーともいえるでしょう。これらの企業は両業種のなかでともに抜群の業績を上げていますが、業界の中で苦戦して撤退する企業と比べて、新しい画期的新産業に属しているわけでもありません。かつての右肩上がりの成長経済時代は、商品力(技術)と価格中心がコア・コンピタンス(自社ならではの価値を提供する中核的能力)でしたがすでに過去のものといわざるをえません。
上下左右のサプライチェーンの中で自社が生き残る場所を探さなければならないこれからの産業再編は、これまでの製品と市場を確保して安心できた再編とは異なります。すなわち、技術コンサルタント的付加価値サービス業に徹してユーザーに密着するか、スピードとベストクラスの技術のアセンブラー(組み立て屋)として組立産業となるか、グローバル市場の機械部品メーカー...