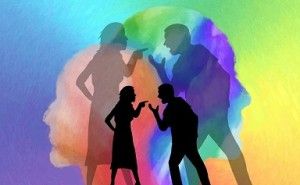1.「なぜ?」にもいろいろ
「なぜ?」を使って原因分析を進めるには、日頃から信頼関係を深めよう。問題解決の時に使う「なぜ?」という言葉は、相手の思考を入れるスイッチにもなるし、相手を疑ったり否定する言葉にもなるので、人のモチベーションを「上げることも」「下げることも」できます。
できれば、部下や後輩のモチベーションを上げる側の「なぜ?」を使いこなしたいものですね。とはいいつつも、つい使いたくなるのが「なぜ?」です。相手のモチベーションを下げないようにするには、どのようにすればよいのでしょうか?
今回は、問題解決を円滑に進めるための、雰囲気作りについておはなしします。心理的安全性を高め、問題解決にも強い職場に成長します。
会社の雰囲気や職場の雰囲気は、千差万別です。例えば「なぜ?」と言葉を使うと、職場の雰囲気がだんだん悪くなり、だれも発言しなくなるケース。
その逆に「なぜ?」という言葉を使っても、ひとり一人が活発に言葉を発して、情報交換が続くケース。問題解決をするときには、明らかに後者が有効な雰囲気で、できれば、この雰囲気で問題解決に挑みたいものです。
2.「心理的安全性」とは
この2つのケースを観察すると、明らかに、心理的安全性が関わることが解ります。心理的安全性とは「リスクを負ってでも、発言が出来る雰囲気」という意味があります。
- 「これを言ったら、全部、私の所に仕事が回ってくるんだろうなぁ~。」
- 「これを言ったら、きっと課長の機嫌が悪くなるんだろうなぁ~。」
- 「これを言ったら、みんなに嫌われるだろうなぁ~。」
このような言葉が、頭の中にまるで”電光掲示板の文字”の様に流れる状態だと、その職場は「心理的安全性」が確保されていません。
自分にとって不利になること(リスク)が予測されながらも、あえて言葉を発することができる雰囲気。これが「心理的安全性」です。「なぜ?」という言葉を使っても、対話が活発に行われるチームも「心理的安全性」が高いといえるでしょう。
この2つのチームを比べてみると、どうやら日頃からの「人と人との関係性」が絡んでいるようです。日頃から、リーダーがチーム内で「ラポール形成」を維持し続けているチームは「なぜ?」という言葉に「ネガティヴに反応」が起きず、前向きな問題解決に取り組みやすい様です。
逆に「ラポール形成」が形成されていないチームでは、問題解決もズタズタです。
3. 協力的な関係を築く
ラポールとは、相手との信頼を確立し、協力的な関係を築くことを指します。
この信頼関係があると、ちょっとトゲのある「なぜ?」という言葉でも、ネガティヴに受け入れられることが少なくなり、良い雰囲気を維持しながら問題解決に挑むことができるのです。ラポール形成には、日頃から次の様なコミュニケ...