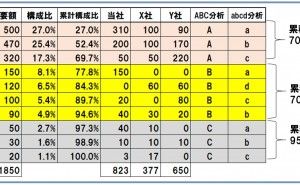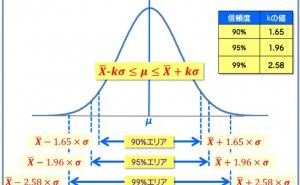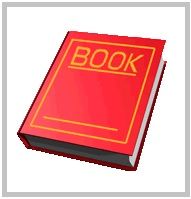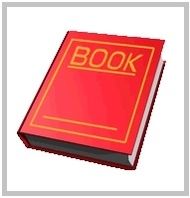前回の、その1に続いて、生産財マーケティングの考察です。 一口に生産財メーカーと言っても、利益率のバラツキは各企業で大きいものです。同じカテゴリーの製品を扱っていても、営業利益率が数%というメーカーもあれば、30%、40%という高い利益率をたたき出しているメーカーもあります。
一口に生産財メーカーと言っても、利益率のバラツキは各企業で大きいものです。同じカテゴリーの製品を扱っていても、営業利益率が数%というメーカーもあれば、30%、40%という高い利益率をたたき出しているメーカーもあります。
高い利益率はどのように達成できるのでしょう。シンプルに考えれば、当然のことですが、品質などで競合企業に負けず、かつギリギリの低コストで製造し、その製品の価格を高く設定して販売できればよいわけです。そのような製品を大量販売できれば、確実に利益が上がります。
一般的に製品を製造する際の低コスト化は、原材料の調達をはじめ、設計・開発、生産、物流などの各段階において、それぞれ実現できる“のりしろ”をもっています。改善活動や海外生産などの取り組みからもわかるように、従来から多くの日本企業は実行してきていて、今後も継続的に取り組まれていくことでしょう。
では、もう一方の製品の価格を高く設定することについては、うまく行えているでしょうか。この問いに対して、自信をもって「イエス」と答えられる企業は多くないように思われます。製品の価格設定は、原価を積み上げた後に、社内で決定した利益(率)を乗せて計算するケースや、市場における製品カテゴリーの参照価格を基準に、製品の独自性などを考慮して価格を調整するケースなどがあります。
しかし、このような従来型の価格設定の方法だけでは、実は逸失利益を見逃している可能性も否定できません。では、製品の価格をユーザーが離反しない範囲で、より高く設定するにはどうしたらよいでしょう? そのためには、製品の企画・開発の「考え方」から変えてみる必要があります。
まず確認すべきは、生産財の顧客は企業であり、顧客自身も売上、利益を上げることを目的として事業を行っているということです。その事業目標の達成に役立つのであれば、顧客は費用対効果を考えて、製品自体の価格が他の価格よりも多少高かったとしても製品を購入するものです。逆に事業目標の達成に役立たないと判断すれば、いくら相場よりも安い製品であろうと買うことはないでしょう。
企業は消費者と違って合理的な判断の下で購買するのであり、意味のない衝動買いはまずありません。生産財の場合、もし自社製品がなかなか売れないのであれば、顧客企業の重要事業課題の解決に自社製品がマッチしていないのではないかと考えることが大事なポイントになります。
顧客企業の事業課題を見出すためには、バランスド・スコアカードの4つの視点による分析が有効です。具体的には、顧客企業の事業を「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つの視点から体系的に分析していきます。自社が顧客の業務プロセスの効率化、生産性の向上に役に立つ可能性のある製品を扱っているのであれば、分析では顧客が現時点でどのような手法で業務を行っているのか、そこでは「人と工数」「1回当たりの費用」がどのくらいの“頻度”で投入されているのかを把握します。これを把握できれば、総コストも見積もることが可能です。
業務にかけている総コストを見積もった上で、製品購買における「予算枠」を大きく決める。もし、顧客が多額のコストをかけて業務をこなしているのであれば、このコストの低減は顧客とっての重要な事業課題なはずです。したがって、自社製品がこの重要な事業課題の解決に有用であれば、その製品価格が市場の相場価格より多少高くても、全体としての費用対効果を考えて、顧客は高い価格で購入してくれる可能性が高くなります。
つまり、製品の価格を高く設定するためには、顧客企業において彼らが解決しなければならないと考えている重要な事業課題が「存在」するかどうかをまず探索することが第一歩です。こうした情報は、当然のことながら市場調査レポートなどには掲載されておらず、Go...