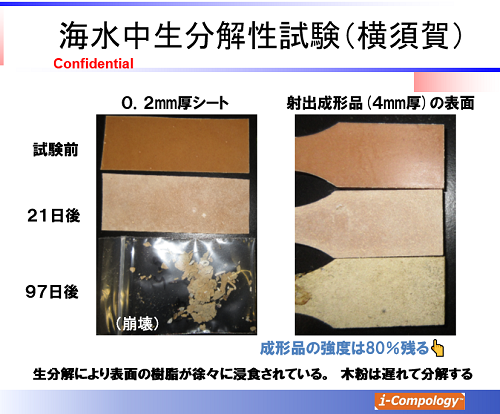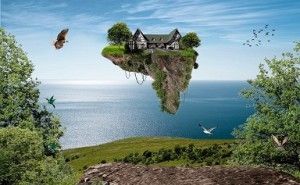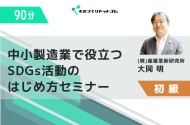陸と海の環境保護と中山間地域における持続可能な産業の創出に
アイ-コンポロジー株式会社(東京都品川区)

目次
1.陸と海の生態系から考えるSDGs
2.バイオマス粉と樹脂複合材料で射出成形が容易に
3.間伐材など使い、森林保全や新たな産業の創出に
4.バイオマス由来(カーボンニュートラル)かつ、自然界でCO2と水に分解
5.温暖化、海洋プラ、SDGs、環境に配慮した経済を
1. 陸と海の生態系から考えるSDGs
世界的に続く森林減少や砂漠化に歯止めをかけるため、SDGs(持続可能な開発目標)でも「陸の豊かさを守ろう(目標15)」をはじめとした多くの目標が掲げられています。日本国内でも間伐(ばつ)で発生した木質バイオマスの有効利用は林業や木材産業を守るほか、森林保全にもつながるなど、大きなリサイクルを生み出します。また、森がCO2を吸収することで「気候変動に具体的な対策を(目標13)」にもつながります。さらに、森林環境や地域社会に配慮する製品を生み出すといった視点では「つくる責任つかう責任(目標12)」にも当てはまるなど、森林環境の分野は多くの目標にかかわっています。
一方、海を汚染するだけでなく、そこに住む生物にも悪影響を与えることから、問題視されている海洋プラスチックごみ問題は、SDGs目標の14「海の豊かさを守ろう」の中でも取り上げられています。2019(令和元)年の環境白書によると、毎年800万トンのプラスチックが海に流れ出していると試算され、プラスチック海洋中のマイクロプラスチック(5mm以下、原料はPE「ポリエチレン」やPP「ポリプロピレン」など)は、人間を含め、魚や鳥など生態系全体への悪影響が確認されるなど、迅速な対策が求められています。
2.バイオマス粉と樹脂複合材料で射出成形が容易に
環境調和バイオマス複合プラスチック材料を開発するアイ-コンポロジー(東京都品川区・三宅仁代表取締役)では「環境問題に意識の高い消費者と環境を守る企業をつなぐ」ことを目的に、間伐材を使ったバイオマス複合プラスチック材料「i-WPC(イノベーティプ・ウッド・プラスチック・コンポジット)」と、海洋生分解性バイオマス複合プラスチック「Biofade(ビオフェイド)」を研究開発し、環境保護と中山間地域における持続可能な産業の創出に向けて貢献しています。
2019(令和元)年には、(国研) 科学技術振興機構(JST)が創設した、社会課題を解決する優れた取り組みを表彰する「STI for SDGsアワード」で優秀賞を受賞しています(STI:科学技術イノベーション・Science, Technology and Innovation)。
同社の創業は2016年。大手石油会社で主に石油化学の研究開発や新規事業の開発に携わっていた三宅仁代表と小出秀樹氏が「これまで人類はエネルギーを石油・石炭に頼ってきたが近い将来、石油事業から天然資源に転換しなければならない時代が来る」と研究と開発を続け、木粉などのバイオマス粉とプラスチックの複合材を改良し、これまで難しいとされていた射出成形やブロー成形を可能にする製造技術を確立しています。
三宅代表は、バイオマスプラスチック開発に行き着いた理由に①「日本の天然資源(未利用バイオマス)を十分に活用でき、環境保全にもつながる」②「欧州で提唱された「バイオエコノミー」の考え方は必ず世界に広がる」を挙げ「日本は欧米と比べ、温室効果ガス問題などで遅れを取っているうえ、海のプラごみ問題も抱えているため、私たちはサスティナブル(持続可能な)な材料の開発にこだわり、次世代につなげたかった」と話しています。
3. 間伐材など使い、森林保全や新たな産業の創出に
【i-WPC】
これまで、木粉とプラスチックを原料とした複合材「ウッドプラスチック(WPC)」はウッドデッキ板材などとして活用され、生産は樹脂の流動性にあまり影響がない押出成形で製造されていましたが、i-WPCは、従来の間伐材や端材といった国内にある豊富な原材料を活用しながら、ウッドプラスチックでは難しいとされていた射出成形等での量産を可能としています。
同社ではi-WPCの特長として①環境調和性②さまざまな成形が可能(成形性が高い)③間伐材など、国内の豊富な未利用原材料が生かせる④優れた材料特性―を挙げます。
まず、環境調和性ですが、石油由来の樹脂材料を減らし、植物由来の材料を増やすことで、焼却処分する際、燃焼時のCO2大幅削減が可能といった「カーボンニュートラル(脱炭素)」が...