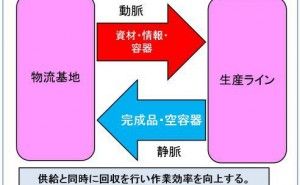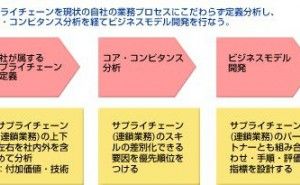1.付加価値作業
◆ ピッキング作業の効率化:探す時間を短縮する
自社の倉庫や預け先の倉庫を問わず「倉庫内の物流作業についてもっと改善したらいいのに」と感じる方はたくさんいらっしゃると思います。しかし、その倉庫で長年作業を行っているとそれが当たり前になってしまいます。さらにその期間が長くなると、作業方法を変更することに大きな抵抗を覚えることになるものです。そういった会社に中途入社すると、新鮮な目で有様を目にするため「何でこんな無駄なことをやっているのだろう」と感じることがあるものです。
今回は、倉庫における物流作業はどうあるべきかについて考えてみたいと思います。
まずピッキング作業について考えていきましょう。ピッキング作業は一種の出庫作業です。つまり、在庫の中から顧客の指示に基づき、必要なものを必要な数量取り出して出庫する作業のことです。このピッキング作業ですが、大半の倉庫で商品棚をずらっと並べ、そこから必要なものを取り出すやり方を取っています。この作業方法ですが、顧客のオーダーごとに実施するケースが多いと思われますが、その場合歩行が増える傾向にあります。
つまり「顧客のオーダーごと」の作業になりますから、たとえ同じ商品であっても顧客のオーダーが「1つ」であれば「1つ」だけピッキングします。次の顧客が同じ商品をオーダーしていても、その分をまとめて取り出すことはしません。もう一度、同じ棚に歩いて行き、取り出すことになります。しかし特に多くのオーダーがかかる商品であれば「商品単位のピッキング」を行い、顧客ごとに仕分けをした方が効率が良い場合があります。
顧客ごとにピッキングを行うことは間違いが少なく、品質を保持するには良いやり方ですが、効率の面では劣る場合があるのです。またレイアウトもピッキング作業効率を左右する大きな要素となります。物流の原理原則として、流動量の多いものは出入り口の近くに、動きの少ないものはできるだけ奥に配置するという考え方があります。
この原則と実態が合っているかどうかについてもチェックする必要がありそうです。ピッキング作業の付加価値を生み出す瞬間は「物を取ってカートに入れる時」です。商品を探したり歩き回ったりすることは、付加価値作業に当たりませんので、この部分をいかに縮めるかが、倉庫内物流作業効率向上のキーとなるのです。
2.稼働分析
◆ 付加価値作業比率を向上させる
「倉庫作業の中での付加価値作業はピッキング作業である」ことを前述しました。顧客の指示に基づく入出庫作業であったり、保管作業ということになりますが、倉庫内作業で注意しなければならないことは、低付加価値作業と無付加価値作業を明確化し、それらを減らしていくことにあります。
それでは、低付加価値作業、無付加価値作業とは何でしょうか。「作業」ですから人の動きに注目してみましょう。倉庫の中で最も気を付けなければならないことは「探す」という行為です。この行為からは全く付加価値が生じません。付加価値があるかないかの判断基準として「お客様にお金を払っていただけるかどうか」という考え方があると思います。一番手っ取り早いのは、自分がお客様だったとしたら目の前で行われている作業に対して「対価」を払えるかどうかを考えてみることです。
先ほどの「探す」作業、倉庫内を「歩き回る」動作、他の作業者との「立ち話」などは、いずれもお金を払って欲しいと思わないものではないでしょうか。こういった作業の有無は、動作の中でも付加価値作業を行うにあたり、付随的にやらざるを得ないものがあると考えられます。
たとえば、ピッキング作業における棚間歩行やオーダーシート確認、カート運搬などです。これらを改善することはできますが、必ずしも無くすことができるとは限りません。しかし、まずは無くす方法をとことん考えましょう。少なくとも「探す」作業は撲滅が必要です。そのためにはロケーションの明確化や分かりやすい表示付などで解消が可能です。
普段、当たり前に実施している倉庫内物流作業について、一度は稼働分析をやってみるとよいでしょう。稼働分析を実施することで、付加価値作業の比率がいかに低いか驚くのではないでしょうか。稼働分析結果をグラフにして現場に貼り出し、全員で今のレベルを認識することが必要です。これを徐々に改善し、付加価値比率を向上することで、作業員の方たちのモチベーションを上げていくことも重要だと思います。
ピッキングミスを減らすことで誤出荷低減につながります。誤出荷を発生させてしまうと、正規商品の再発送と誤品の引き取りが発生し、会社の評判も悪くなることが考えられますから、物流品質にはくれぐれも注意したいところです。そのために、他商品との違いを分かりやすく表示したり、類似商品の置場所を離したりすることも倉庫内改善の一つです。
3.積極的な作業改善のすすめ
(1)作業改善:倉庫内作業~通路幅の理想は1m未満
倉庫内作業で気を付けなければならないことがあります。それは効率的にエリアを使う手法です。エリアが十分にある事例は必要以上に「のびのびと」使うことが考えられます。エリアが不足している事例も困りものですが、広すぎても効率を落としがちです。ちょっときつめかな、と感じるくらいの提案が丁度(ちょうど)良いと考えられます。
皆さんの会社でピッキング場の通路幅はどれくらいでしょうか。本当に効率を上げようと考えている会社では1m未満が大半です。しかし効率を真剣に考えずに設計すると、1.5m~2mくらい取ってしまいます。よくある理由が「2台の台車がすれ違えるため」といわれますが、これは意味はないと思います。
まず、台車同士がすれ違う現象がどれくらいの頻度で起こるのか、ということを考えてみましょう。一般的にはそれほどないと思われますが、一日に何度もあるようでしたら「人が多いのではないか」と疑ってみる必要がありそうです。むしろ通路幅を縮め、一方通行にするとともに作業編成を考え、人と人が干渉しないように業務指示を行うべきだと思います。
(2)作業改善:梱包作業場~作業者が動かない工程設計を
梱包作業場も一緒です。エリアがあるからといってのびのびと使うのではなく、極力「間締め(まじ...