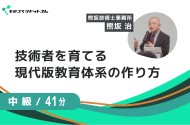1. 区別
私たちは日常生活の中で色々な区別をします。若者と年配、上司と部下など様々です。仕事の場合は役割によって区別することが多いです。また若者と年配のように自分の意志に関わらず生まれた年によって区別することもあります。このような区別は日常生活や仕事を進めるうえでよく見られます。この時に客観的に〇〇と□□を並べる時は特に意識しませんが、自分と誰かを並べると相手は自分とは違う人として区別するという側面もあります。
自分と相手が違う人というのは当たり前に聞こえるかもしれません。しかし例えば、自分と別の部署の人などを想像してみると、関係性のとても低い人、全然関係ない人のように思います。全然関係ない人に対しては思い入れがありません。情がうすくなりやすいです。親しい人よりも優先順位が下がったりします。しかし、あまり関係性のない人でも「立場は...