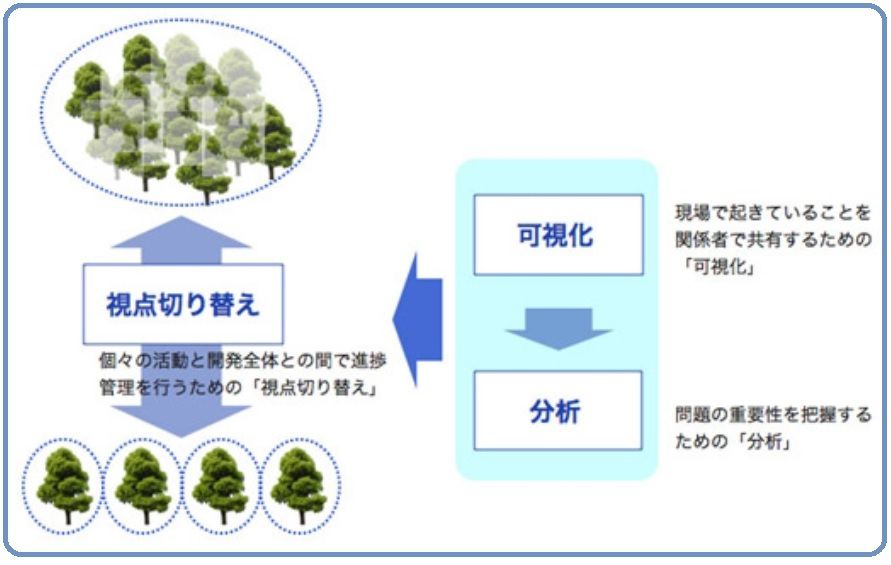
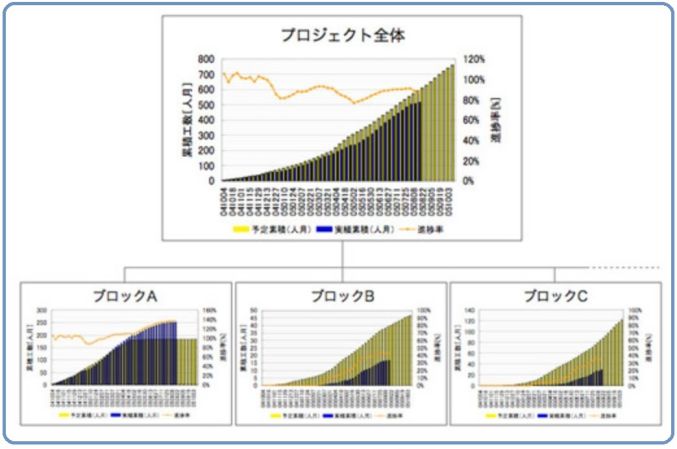
TOP


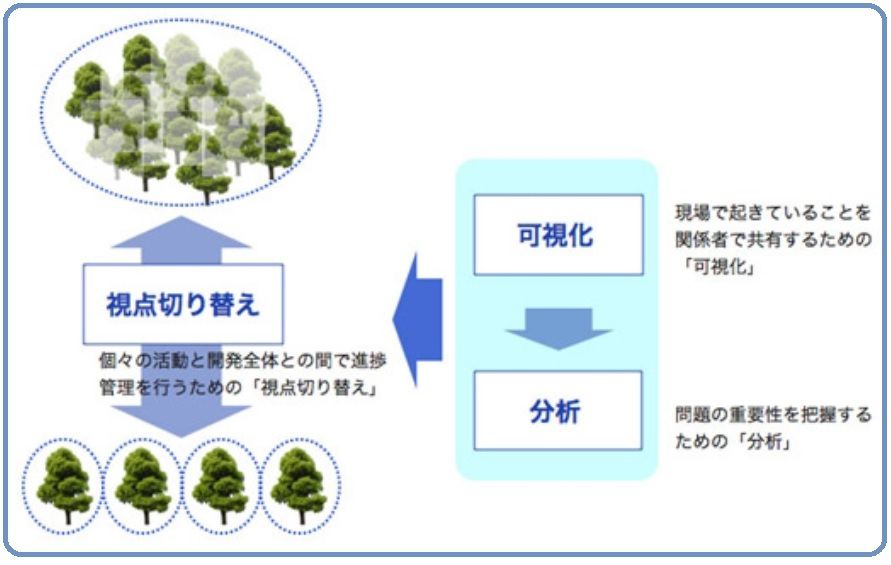
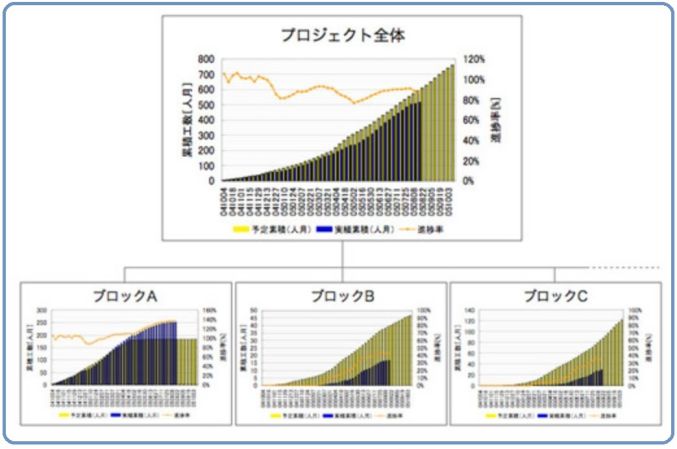
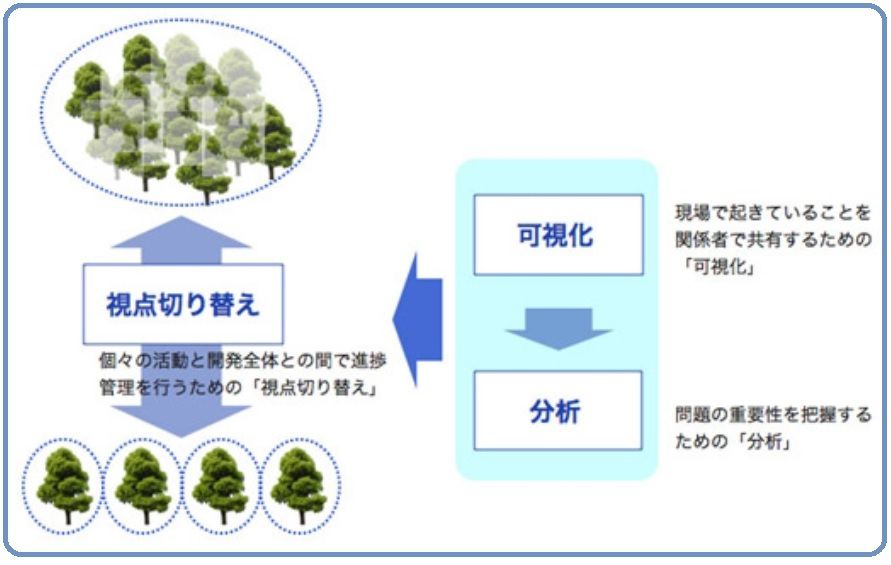
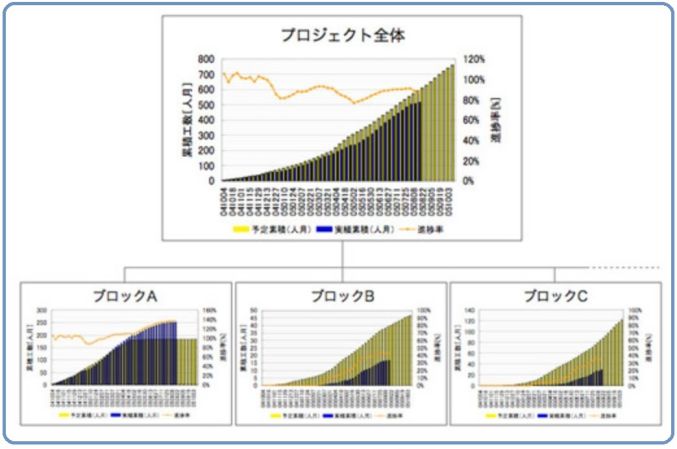
続きを読むには・・・
石橋 良造
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事
1. 企画の承認が得られない悩み 商品・R&D開発テーマの企画提案について、なかなか承認が得られないという相談を受けました。この悩みは大企...
1. 企画の承認が得られない悩み 商品・R&D開発テーマの企画提案について、なかなか承認が得られないという相談を受けました。この悩みは大企...
イノベーションを起こすための自分の知識や経験を整理する重要なフレームワークとして「本質」と「それ以外」があると思います。「本質」を見...
イノベーションを起こすための自分の知識や経験を整理する重要なフレームワークとして「本質」と「それ以外」があると思います。「本質」を見...
前回はKETICモデルのK(Knowledge)の知識の3つの要素の内、「自社の強み」の中の...
前回はKETICモデルのK(Knowledge)の知識の3つの要素の内、「自社の強み」の中の...
ものづくりの世界において、大企業の製品はもちろんのこと、海外Makersの新製品情報も早々に目に入ってくるようになりました。KickStarter等のク...
ものづくりの世界において、大企業の製品はもちろんのこと、海外Makersの新製品情報も早々に目に入ってくるようになりました。KickStarter等のク...
◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...
◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...
前回のその2:CMMIの要件管理に続いて、プロジェクトの計画策定について解説します。CMMIでは次のことができている必要があります。 ...
前回のその2:CMMIの要件管理に続いて、プロジェクトの計画策定について解説します。CMMIでは次のことができている必要があります。 ...
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします


