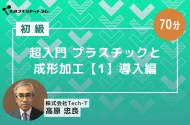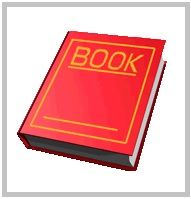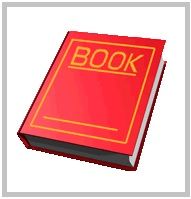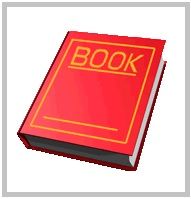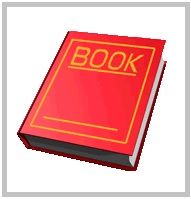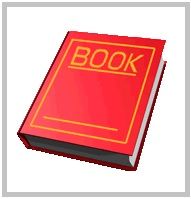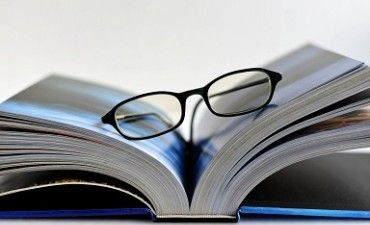【中止】容器包装のLCA/環境負荷算定と循環型包装技術の動向
環境負荷の低減につながる、LCA視点での容器包装の設計素材選定の考え方
これからの海外輸出では対応が必須! 回収・再生再利用を考慮した包装技術や循環型プラスチック採用に関する世界の動向が分かる
セミナープログラム
【10:30~13:00】
【第1部】 容器包装におけるLCAと環境負荷算定
(国研)産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 総括研究主幹 門奈哲也 氏
【講座主旨】
LCA(ライフサイクルアセスメント)は、製品の素材の原料採掘から製造、輸送、消費、廃棄(リサイクル)までの、製品すべてのライフサイクルにおける環境影響を定量的に評価する手法です。社会の持続性の視点では、単に製品を作る段階や見た目での良し悪しではなく、ライフサイクル全体で製品を設計する必要があります。その中で容器包装は、商品広告や中身の保護の目的はありますが使い終わったらゴミになってしまう宿命があります。そのため、容器包装は、表示の簡素化、軽量化など進められていますが、真の環境負荷低減を目指すには、LCAの視点で設計することが大切です。
本講座では、LCAの初心者を対象に、LCAの目的から、容器包装におけるLCAの算出に関するケーススタディまでを幅広くコンパクトに解説いたします。
【講座内容】
1.背景
・社会背景
・LCAの必要性
2.LCAについて
・LCAとは、歴史
・LCAの必要性、枠組み、規格
3.LCAの実務
・目的、調査範囲、機能単位の設定
・インベントリデータ
・算出ルール
・結果の解釈
4.包装での事例
・ケーススタディ
・LCA視点でみた素材の選定
5.LCAを取り巻く最近の状況
【質疑応答】
【14:00~16:30】
【第2部】環境対応の循環型包装を目指した容器包装技術
住本技術士事務所 所長 住本充弘 氏
【講座主旨】
世界は地球環境対策及び資源の節約に向けて活発な活動をしている。包装においても、従来の考え方を変えて今までの内容物保護の包装設計にプラスαとして包装設計の段階で使用済み包材の回収・再生再利用の面を考慮しなければならなくなっている。特にプラスチックを利用する包装は今まで循環型プラスチック利用の概念はなかった。これからは循環型プラスチック使用が必須の条件となる。国内はまだ動きが鈍いが海外は循環型プラスチックの利用に向けて積極的に動いている。特に輸出包装の場合は、循環型プラスチックの使用が必須となり、輸出ビジネスでは非常に重要な課題である。今から国内でも対応を図っておかないと間に合わなくなる。国内での対応の参考に、今回は特に海外事例を説明する。
【講座内容】
はじめに
1.循環型パッケージとは
1.1 循環型パッケージの必要性
1.2 循環型パッケージの社会システム構築
1.3 循環型パッケージの包装設計思想
2.容器包装の種類
2.1 容器包装の形態
2.2 循環型パッケージに向けた包装事例
3.PETボトル
~PETボトルの再生再利用は世界中で進んでいる。再生樹脂の確保が課題となっている。再生利用における課題と事例を説明。
3.1 メカニカルリサイクル
3.2 ケミカルリサイクル
3.3 PEFの利用
4.プラスチック成形容器
~各種の樹脂が利用されているが循環型パッケージに向けての課題と回収・再生技術・事例を紹介
4.1 オレフィン系
4.2 PET系
4.3 PS 系
4.4 多層系
5.軟包装材料
~再生型パッケージの確立で難しい対応に迫られている軟包装の現状と今後の対応方向を説明
5.1 小ロット対応の製造体制
5.2 ラミネーション技術
5.3 バリア性技術
5.4 耐熱性OPP利用
6.紙器
~紙器も古紙再生性を考慮した包装設計が必要である。パルプ利用の技術から紙器・液体容器までの古紙再生可能な事例を説明
7.再生技術
~開発中も含めた再生技術とその具体的な国内外の利用事例
7.1 プラスチック製包装の再生技術
7.2 メカニカルリサイクル
7.3 ケミカルリサイクル
8.Recyclable とは
9.FDA, FEFSAの動き
10.Certification の必要性
11.循環型パッケージの事例
12.今後の循環型パッケージの予想
まとめ
【質疑応答】
セミナー講師
【第1部】(国研)産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 総括研究主幹 門奈哲也 氏
【第2部】 住本技術士事務所 所長 住本充弘 氏
セミナー受講料
聴講料 1名につき60,500円(消費税込/資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき55,000円〕
受講について
- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
- 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test - 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。 - Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。 - パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
- セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。 - 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
- 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、
録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。 - 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。 - Zoomのグループにパスワードを設定しています。
部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
受講料
60,500円(税込)/人