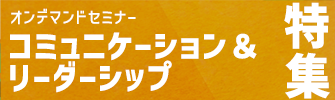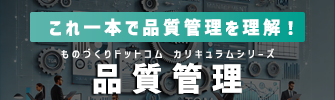薬物の消化管吸収について-評価・予測<消化管吸収の評価系およびモデルによる吸収率予測の違い>
~ 消化管吸収の評価系/モデルによる吸収率予測の違いをExcelによる演習で理解を深めます ~
消化管吸収の評価系およびモデルによる吸収率予測の違いを、Excelを用いて演習することにより、消化管吸収を理解することを目的にしています。
■みなさんは、以下の問題点に答えることができるでしょうか?
Q:ヒト吸収率(Fa)はどのように求められているのか?
Q:膜透過係数が、in vivoとin vitroで違っているのはなぜか?
Q:吸収予測モデルは複数ありますが、予測性に違いはあるのか?
Q:膜透過係数と消化管滞留性に種差がある場合、どのような影響があるのか?
Q:生理学的モデルに展開するため非臨床データをどのように扱えばよいのか?
Q:市販ソフトウェアの予測精度の検証はどのように行えばよいのか?
■本セミナーは「初中級、中級向き」
【レベル3】初中級 解析業務経験あり
※業務経験が実際にあり動かしている方
【レベル4】中 級 簡単なモデリング&シミュレーション経験がある方
セミナー趣旨
医薬品の多くは、経口剤として開発されています。消化管からの吸収が低い薬物では、効率が悪いばかりでなく、吸収の個体間差や薬物間相互作用のリスクが高まります。そのため、創薬段階から溶解性、膜透過性、P糖タンパクによる排出試験等が行われ、ラット等の動物を用いた試験も行われています。
しかし、これら非臨床データから臨床における吸収率(Fa)の予測を市販ソフトウェア以外で計算したことはあるでしょうか?
膜透過係数とFaの相関あるいは動物のFaとヒトのFaの相関から求めたことがある方はいると思います。
では、以下の問題点に答えることができるでしょうか?
■ヒト吸収率(Fa)はどのように求められているのか?
■膜透過係数が、in vivoとin vitroで違っているのはなぜか?
■吸収予測モデルは複数ありますが、予測性に違いはあるのか?
■膜透過係数と消化管滞留性に種差がある場合、どのような影響があるのか?
■生理学的モデルに展開するため非臨床データをどのように扱えばよいのか?
■市販ソフトウェアの予測精度の検証はどのように行えばよいのか?
吸収を担当している人でも知っている人は、限られているという印象を持っています。こういった知識は、教科書に書かれておらず、複数の論文から知識を得、自ら計算しない限り、理解するのは難しいと思います。
本セミナーでは、消化管吸収の評価系およびモデルによる吸収率予測の違いを、Excelを用いて演習することにより、消化管吸収を理解することを目的にしています。
セミナープログラム
1.消化管吸収について
2.吸収率(Fa)の評価
・マスバランス試験による評価、バイオアベイラビリティからの評価
3.In vivo評価 effective permeability(Peff)
・バルーン法による評価
4.In vitro評価 apparent permeability(Papp)
・経細胞輸送による評価
5.Amidonの3つのパラメータ(Absorption number(An), dose number(Do), dissociation number(Dn))
6.吸収率の予測(演習)
・Peff、Papp、An、Do、Dn、Faの計算
・one-compartmentモデル、multi-compartment モデル、tubeモデルによるFaの計算
7.P糖タンパクの吸収に及ぼす影響
8.消化管代謝の考え方
9.デコンボリューション法による解析結果の見方(演習)
10.質疑応答
セミナー講師
略歴
1987年 中外製薬入社 非臨床薬物動態部門配属
1995-1997年 東京大学製剤学教室研究生
1999年 薬学博士取得
2019年 中外製薬退職
2005年 日本薬物動態学会奨励賞受賞
2019年 日本薬物動態学会創薬貢献・北川賞受賞
専門分野:薬物動態全般、薬物速度論、薬物間相互作用、ヒトクリアランス予測、PK/PD解析、バイオ医薬品の薬物動態
セミナー受講料
※お申込みと同時にS&T会員登録をさせていただきます(E-mail案内登録とは異なります)。
55,000円( E-mail案内登録価格52,250円 )
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料
2名で 55,000円 (2名ともE-mail案内登録必須/1名あたり定価半額27,500円)
【1名分無料適用条件】
※2名様ともE-mail案内登録が必須です。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。
※請求書(PDFデータ)は、代表者にE-mailで送信いたします。
※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※他の割引は併用できません。
【テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【Live配信/WEBセミナー受講限定】
1名申込みの場合:受講料( 定価:44,000円/E-Mail案内登録価格 42,020円 )
定価:本体40,000円+税4,000円
E-Mail案内登録価格:本体38,200円+税3,820円
※1名様でLive配信/WEBセミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
※他の割引は併用できません。
---
<過去シリーズ受講割>
過去に、同一セミナーを受講された方の特別割引を実施いたします。
※本割引は、各種割引との併用は不可となります(E-Mail案内登録価格との併用不可となるためご注意ください)⇒ 復習受講割(1名) 1日あたり定価:11,000円(本体10,000円+税)
過去に同一セミナーを受講されている方は上記価格にて受講可能です。お申込みの際、【復習受講割】を選択し【 通信欄 】に開催されたセミナー略称を必ずご記載ください。
<対象セミナー>
【2024年開催:薬物消化管吸収】
受講について
ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください)
アーカイブ配信 ►受講方法・視聴環境確認(申込み前に必ずご確認ください)
配布資料
- 製本テキスト:開催日の4,5日前に郵送にて発送予定
※セミナー資料はお申し込み時のご住所へ発送させていただきます。
※開催日の4~5日前に発送します。
開催前日の営業日の夕方までに届かない場合はお知らせください。
※開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、
開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
⇒Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。印刷物は後日お手元に届くことになります。 - 当日演習用Excel資料:マイページよりダウンロードして頂くか、E-Mailで送付いたします。
(開催前日~前々日を目安にダウンロード可、または送付)
受講料
55,000円(税込)/人