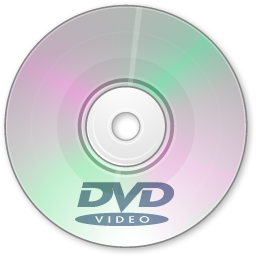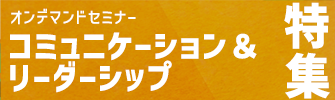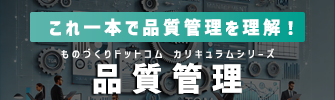電子実験ノートの導入と共有・利活用ノウハウ
効果的なデータ利活用のために
研究・実験データの共有・データ蓄積方法,電子実験ノートの種類・特徴,データ共有基盤のメリット/デメリット,データ蓄積での注意すべき点,蓄積されたデータ分析の注意点,データ蓄積を行うための意識改革,研究・実験データの共有、利活用を促進の体制・条件について,豊富な経験と研究に基づき,実践的に分かりやすく解説する解説する特別セミナー!
【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信(アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)付き)
セミナー趣旨
IoTやAIの普及により、製造工程以降のデータ利活用は急激に進展していま す。
一方、公的研究機関であれ、民間企業であれ、R&D部門におけるデータの取り扱いは 属人的なままであり、研究の信頼性が阻害されたり、効果的なデータの利活用がほとんど 進んでいないのが実態です。
本講演では、まず、R&D部門のデータ共有、利活用の実情 をお話しさせていただき、データ共有、利活用が進まない状況がなぜ発生してしまうの か?そのような状況にはどのような問題がはらんでいるのか?等を説明させていただきま す。次に、データ共有、利活用状況を改善するために必要な方策に関して、電子実験ノー トを導入する際に必要な要件及び、各個人に必要な意識改革や会社としての体制づくり等 を説明させていただきます。
最後に、電子実験ノートを導入、運用に陥りがちな落とし穴 とそれらの回避方法に関して解説させていただきます。
受講者の声
- 社内でDXの活用という方針は示されたものの、活用の仕方が不明瞭なまま見切り発車感があったが、この状態に対する何かいいヒントが得られればと思い、本セミナーに参加いたしました。内容が求めていた答えに近く、今後どのように進めていったらよいかが見えてきました。これから様々な方面に働きかけて、良い方向に進めていきたいと思いました。この度はありがとうございました。
- 電子実験ノートの導入が進行中であり、今回の研修で得た情報を作成中のCSV計画書やユーザー要求仕様書に活用したいと思います。
- DX・AI導入における現実的な課題と、そのために必要な準備・対応策を学ぶことができ、大変勉強になりました。
- 大変分かりやすく有益な情報がえられました。質問もたくさんできましたので参加できてよかったです。
受講対象・レベル
・データ管理でお困りの方
・自社及び他の一般的なR&D部門のデータ管理、利用、活用状況を知りたい方
・R&D部門のデータに対して、AIを活用したい、させたいと考えられている方
・R&D部門のデータの利用、活用を推進することのメリットを具体的に知りたい方 など
必要な予備知識
特に必要ありません。
R&D部門の自社での実情を知っていたり、知りたいと思っていることが必要です。
習得できる知識
1)研究・実験データの共有、利活用状況を改善するためのデータ蓄積方法
2)電子実験ノートの種類とその特徴
3)電子実験ノートを含む様々なデータ共有基盤のメリット、デメリット
4)データ探査、分析を意識したデータ蓄積での注意すべき点
5)蓄積されたデータを使ってデータ分析を行う時の注意すべき点
6)データ探査、分析を意識したデータ蓄積を行うための意識改革
7)研究・実験データの共有、利活用を促進するためのシステムと体制の条件 など
セミナープログラム
1.はじめに
講演者のR&D実績とデータ共有の取り組みについて
2.R&D部門のデータ共有の実情
2.1 R&D部門のデータ共有状況
2.2 属人的データ共有状況が引き起こす問題
2.3 属人的データ共有状況が生み出される原因
3.データ共有状況を改善するために必要な方策
3.1 属人的データ共有状況を脱するために必要な方策
3.2 データ共有基盤としての電子実験ノートのメリット、デメリット及び選択基準
3.3 データ探査、分析を意識したデータ蓄積方法
3.4 データ分析は、どのようにして行うのか?
3.5 データ共有、利活用状況を改善するために必要なプロジェクトチームの作り方
3.6 プロジェクトメンバーに求められる資質
4.電子実験ノートを導入、運用する場合の注意点
4.1 電子実験ノート導入によるデータ共有、利活用の改善例
4.2 電子実験ノート導入時に陥りがちな落とし穴とそれを防ぐ方策
4.3 電子実験ノート運用後に陥りがちな落とし穴とそれを防ぐ方策
5.まとめ
質疑・応答
セミナー講師
株式会社キャトルアイ・サイエンス 代表取締役 上島 豊 先生
博士(工学), 元 日本原子力研究開発機構
1992年3月 大阪大学工学部 原子力工学科 卒業
1997年3月 大阪大学大学院工学研究科 電磁エネルギー工学専攻 博士課程修了
1997年4月 日本原子力研究所 博士研究員
2000年4月 日本原子力研究所 研究職員
2006年3月 日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所) 退職
2006年4月 キャトルアイ・サイエンス設立 代表取締役 就任
主な参加国家プロジェクト
文部科学省e-Japanプロジェクト「ITBLプロジェクト」、「バイオグリッドプロジェクト」
総務省JGNプロジェクト「JGNを使った遠隔分散環境構築」
文部科学省リーディングプロジェクト「生体細胞機能シミュレーション」
主な受賞歴
1999年6月 日本原子力研究所 有功賞 「高並列計算機を用いたギガ粒子シミュレーションコードの開発」
2003年4月 第7回サイエンス展示・実験ショーアイデアコンテスト文部科学大臣賞「光速の世界へご招待」
2004年12月 第1回理研ベンチマークコンテスト 無差別部門 優勝
著作
培風館「PSE book―シミュレーション科学における問題解決のための環境 (基礎編)」
培風館「PSE book―シミュレーション科学における問題解決のための環境 (応用編)」
培風館『ペタフロップス コンピューティング』
臨川書店『視覚とマンガ表現』
技術情報協会『研究開発部門へのDX導入によるR&Dの効率化、実験の短縮化』
技術情報協会『実験の自動化・自律化によるR&Dの効率化と運用方法』など
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
テキスト:PDF資料(受講料に含む)
受講料
49,500円(税込)/人