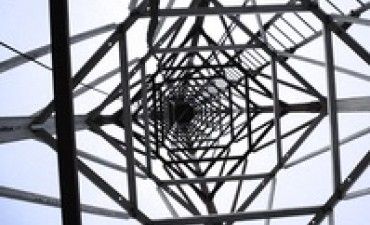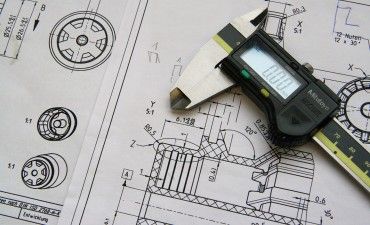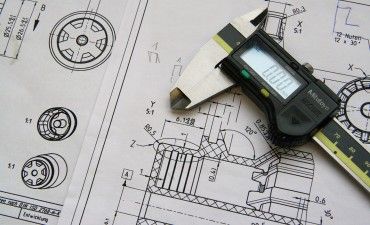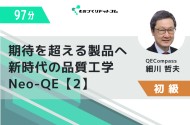1.福島第一原発の衝撃
2011年に発生した福島第一原発の衝撃的な事故は、日本の技術者に重い課題を提示しました。予想を超える地震とそれに伴う大津波、その他想定外の事態など大事故の発生を防げなかった理由は、さまざまに語られています。しかし、信頼性に携わる技術者は言い訳をしてはいけないでしょう。想定できなかった理由を聞いても、被害を受けた人には何の役にも立たないばかりか、逆に憤りが増すだけです。
では、信頼性技術に関わる技術者たちは、どうすべきでしょうか。あえて不謹慎を承知で言えば、信頼性の今後を考えるには、原発事故は絶好の題材です。日本の信頼性工学は大きく転換すべきだ、という啓示であると受け取るべきでしょう。
2.責任追及しないことが肝要
信頼性技術を議論する場合に気をつけなければならないことは、責任の追及とは一線を画すべきという点です。責任を追及する態度では純粋に技術的な議論が難しくなり、かえって原因を不明確にすることになります。
したがって今後の議論においても、だれの責任かという視点は極力除外します。同じ立場になれば、だれでも同じような判断ミスを犯しかねないという認識で、技術の本質を議論する方が建設的であり、信頼性の本来の進め方でもあるはずです。
3.なぜ安全性が見過されたのか
工業製品を開発する作業では、製造段階、流通段階、使用段階そして廃棄段階の全工程で様々な状況を想定し、そこで起こりうる現象を予測し、不具合が発生しないような対策を考えることが求められます。しかし現実には、想定されるすべての事態において機能を満足できるような対策は、時間的にもコスト的にも不可能です。したがって、ある仮定に基づいて、考慮範囲を設定せざるを得ません。この地域ではマグニチュード9以上の地震は起きないと決めることが、この仮定に相当します。そう決めなければ設計の作業は際限がなく広がってしまいますし、逆に、そう決めれば設計の作業範囲が確定でき仕事が進められるからです。
つまり妥協ないしは仮定に基づいて作業...